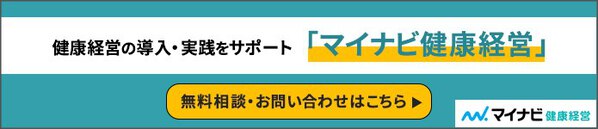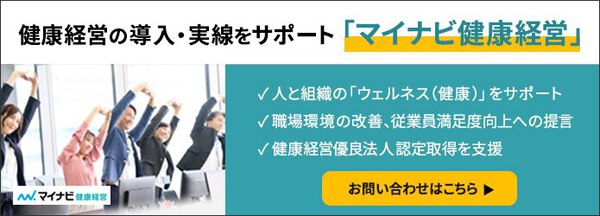ウェルビーイング(Well-being)とは?会社に導入するメリットと取り組み事例を紹介
ウェルビーイングはなぜ重要視されてきているのでしょうか。ウェルビーイングを測定する指標や具体的な取り組み方のほか、メリット、事例などについて紹介します。
目次[非表示]
- 1.ウェルビーイングとは?重要視される背景や実施方法を詳しく解説
- 2.WHOによる健康の定義として登場したウェルビーイング
- 3.ウェルビーイングとウェルフェアとの違い
- 4.ウェルビーイングを測るさまざまな指標
- 4.1.PERMA
- 4.1.1.<PERMAによる幸福度を論理的に測る要素>
- 4.2.SPIRE
- 4.2.1.<SPIREを構成する5つのモデル>
- 4.3.世界幸福度報告
- 4.3.1.<世界幸福度報告の評価項目>
- 4.4.ギャラップ社の指標
- 5.今、ウェルビーイングが重要視される背景
- 5.1.世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)
- 5.2.OECD Education 2030
- 5.3.コロナ禍を背景とした健康意識の向上
- 5.4.新たな経済概念の誕生
- 5.5.人材の確保
- 5.6.SDGsの項目
- 6.日本でのウェルビーイングへの関心の高まり
- 7.企業がウェルビーイングを実践するメリット
- 7.1.従業員の満足度アップによる業績向上
- 7.2.離職数の減少
- 7.3.優秀な人材の確保
- 8.ビジネスの現場におけるウェルビーイング
- 9.経済産業省によるウェルビーイング経営(健康経営)の促進も後押しに
- 9.1.味の素株式会社の事例:味の素グループ健康宣言
- 9.1.1.・全員面談
- 9.1.2.・自社製品を活用したスクリーニング検査
- 9.2.株式会社イトーキの事例:健康経営宣言
- 9.3.楽天株式会社の事例:「楽天主義」を軸に企業文化を醸成
- 9.4.株式会社アシックスの事例:自社開発の健康増進プランを提供
- 10.経済産業省が、2,000法人の評価結果を一括開示
- 11.ウェルビーイングで無形資産の価値を高めよう
ウェルビーイングとは?重要視される背景や実施方法を詳しく解説
豊かさを測定する指標GDP(国民総生産)が高まる一方で、国民の幸せ度は低下しているといわれています。環境問題が深刻化して地球そのものの存続が危ぶまれていること、価値観の多様化によって「幸せの尺度」の個人差が大きくなっていることなどによって、より多面的かつ主観的な「幸せ」が求められるようになっているからです。
そこで注目されているのが、自分自身の幸せの尺度を問い直す「ウェルビーイング」です。企業の経営戦略にも大きなプラスの効果を生み出すウェルビーイングを測定する指標や、具体的な取り組み方のほか、メリット、事例などについて詳しくご紹介します。
WHOによる健康の定義として登場したウェルビーイング
ウェルビーイングという言葉は、世界保健機関(WHO)が設立された1946年、世界保健機関憲章の中で「健康の定義」として初めて登場しました。世界保健機関は、「単に疾病がないことを健康というのではなく、肉体的、精神的、社会的に満たされてこそ健康だ」として、医学的な観点にとどまらない健康促進の重要性を提唱したのです。
日本でも、働き方改革の推進やESGの浸透、価値観の多様化といった社会的変化を背景として、ウェルビーイングが重視されるようになりました。厚生労働省はウェルビーイングを「個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念」と定義しています。
また、厚生労働省による雇用政策研究会において、就業面におけるウェルビーイングの向上は、労働者一人ひとりの能力発揮、企業の生産性向上に寄与するものであるとされています。さらに、雇用政策研究会は「ウェルビーイングは、多様な人々が活躍できる社会の実現と相互補完的な関係性にある」とし、人的投資の一環として労働者の主体的なキャリア形成を支援する必要性も強調しました。
【参照】雇用政策研究会「雇用政策研究会報告書人口減少・社会構造の変化の中で、ウェル・ビーイングの向上と生産性向上の好循環、多様な活躍に向けて」|厚生労働省(2019年7月)
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000532355.pdf
ウェルビーイングとウェルフェアとの違い
ウェルビーイングと混同されがちな言葉に「ウェルフェア」があります。ここでは、ウェルビーイングとウェルフェアの違いを確認しておきます。
ウェルビーイングとウェルフェアには関連がありますが、意味は異なります。ウェルフェアは、貧困や障害などがある人の生活を保障する「福祉」の意味が含まれた言葉で、会社組織に関する文脈では「福利厚生」の分野で使われることが多いでしょう。
企業における福利厚生とは、従業員の労働環境や生活を改善し、仕事に対するモチベーションや企業に対するエンゲージメントを向上させる目的で行うものです。福利厚生には、法律で決められている「法定福利」と、企業独自の制度を指す「法定外福利」があります。それぞれの違いは下記のとおりです。
法定福利
法定福利は、企業に負担義務がある福利厚生のことです。例としては、下記のようなものが挙げられます。
<法定福利の例>
社会保険:健康保険、厚生年金保険、介護保険
労働保険:雇用保険、労災保険
法定外福利
法定外福利は、企業が任意で設定した福利厚生のことです。内容は企業によってさまざまで、自社で提供するものと外部から提供してもらうものがあります。
<法定外福利の例>
自社で提供するもの:通勤費、家族手当、社員食堂、資格取得手当
外部から提供してもらうもの:自己啓発や能力開発のためのセミナー、フィットネスジムや託児施設の利用、健康診断補助
ウェルフェアが充実すると従業員の満足度が上がり、ウェルビーイングにつながります。ウェルフェアはウェルビーイングを実現するための手段であり、ウェルビーイングは最終的な目的であるといえるでしょう。
ウェルビーイングを測るさまざまな指標
幸福度を科学的根拠のある指標にもとづいて評価することは、その国のウェルビーイングの実体を明らかにする上で重要です。続いては、ウェルビーイングを測る3つの指標をご紹介します。
PERMA
心理学には、組織や個人、社会の幸せにフォーカスし、持続性のある幸せを手に入れる方法を研究するポジティブ心理学という学術領域があります。
「PERMA」は、ポジティブ心理学を推進したアメリカのマーティン・セリグマンが提唱したモデルです。PERMAは、幸福度を論理的に測る要素として、下記の5つで構成されています。
<PERMAによる幸福度を論理的に測る要素>
- Positive Emotion(ポジティブな感情を持つ):おもしろい、楽しい、うれしい、気分が良い、希望が持てる など
- Engagement(何かに没頭する、自発的に従事する):夢中になって何かに取り組む、時間を忘れて集中する など
- Relationship(他者との前向きな関係):援助する・してもらう、協力する、意思疎通する など
- Meaning(人生の意義をモチベーション高く追求する):生きる意味・意義、社会貢献 など
- Accomplishment(達成)/何かを達成する、成果を出す
SPIRE
SPIREは、ポジティブ心理学の第一人者の一人、タル・ベン・シャハ―博士が提唱したモデルです。全体の幸福度を、下記の5つのモデルに分けて分析します。
<SPIREを構成する5つのモデル>
- Spiritual Well-Being:精神のウェルビーイング
- Physical Well-Being:身体のウェルビーイング
- Intellectual Well-Being:知性のウェルビーイング
- Relational Well-Being:人間関係のウェルビーイング
- Emotional Well-Being:感情のウェルビーイング
SPIREモデルは、PERMAの法則と同様に、5つのバランスがとれた状態を目指しています。
世界幸福度報告
世界幸福度報告は、国際連合(国連)の「持続可能な開発ソリューション・ネットワーク(SDSN)」が刊行するレポートで、世界の約150ヵ国を対象として毎年行われています。下記の項目ごとに最高で10、最低で0のスコアをつけ、その総合点によって順位を算出します。
<世界幸福度報告の評価項目>
- 1人当たりの国内総生産(GDP)
- 社会的支援(Social Support)
- 健康寿命(healthy life expectancy)
- 社会的自由(freedom to make life choices)
- 寛容さ(Generosity)
- 汚職の無さ・頻度(Perceptions of corruption)
- ディストピア(人生評価/主観満足度)+残余値(Residual)
最後の評価項目にあるディストピアとは「架空の国」を意味します。「各項目が最低値となると仮定されるディストピア(架空の国)」と、どれほどの差があるか(Residual)を測る項目です。
世界幸福度報告の最終的なランキングは、上記7つの評価項目を国や地域ごとに数値化・分析し、その平均値で決まります。
日本は、客観的に見ると安全で平均寿命も長く、平和であるにもかかわらず、先進諸国の中では最下位に位置しています。2022年は54位で、「社会的自由」「寛容さ(他者への寛大さ)」「人生評価/主観満足度」が低く、「1人当たりの国内総生産(GDP)」と「健康寿命」が高い結果となりました。
なお、経済協力開発機構(OECD)が11項目で国民生活の幸福度を評価する「より良い暮らし指標(Better Life Index)」でも、日本は一部要素で非常に低いスコアを示し、先進国の中では下位に位置しています。
ギャラップ社の指標
ギャラップ社とは世論調査やコンサルティングを行うアメリカの企業です。同社は、各国・地域において世論調査を行い、ウェルビーイングに関する調査に役立つデータを提供し続けています。
そのギャラップ社は、ウェルビーイングの指標として、下記の5つを示しています。
-
Career well-being(キャリア ウェルビーイング)
この場合のキャリアは、一般的にいわれる「仕事上の経歴」だけを指すものではありません。自分の人生そのものをキャリアと捉えるため、育児や勉強、趣味なども含まれます。日々の時間を多く費やしている事柄に、どれだけ充実した気持ちで取り組めているかを測る指標です。
-
Social well-being(ソーシャル ウェルビーイング)
ここでのソーシャルは、人間同士のつながりを指します。家族、同僚、恋人などとどれだけ深い信頼関係を築けているか、またその関係性の在り方に満足しているかが問われます。
-
Financial well-being(フィナンシャル ウェルビーイング)
ここでのフィナンシャルは、経済的な満足度を指します。不安なく人生を歩むための効果的な資産運用ができているか、満足できる報酬を得られているかといったことが該当します。
-
Physical well-being(フィジカル ウェルビーイング)
この場合のフィジカルとは、身体と精神が健康な状態にあることです。身体的な理由でやりたいことに制限をかけず、存分にパワーを発揮できる状態を指します。
-
Community well-being(コミュニティ ウェルビーイング)
コミュニティは、地域社会とのつながりに対する幸福度を指します。住んでいる地域のコミュニティと深く関わり、良い関係にある場合、コミュニティ ウェルビーイングが高いといえます。
【参照】nnovator Japan Editors「ウェルビーイングって何だろう?【実現に必要な5要素を紹介!】」|OMOSAN(2022年7月)
https://www.innovator.jp.net/blog/articles/what_is_well-being_2022
今、ウェルビーイングが重要視される背景
近年になってウェルビーイングが注目され始めた背景には、どのような理由があるのでしょうか。いくつかの理由のうち、ここでは6つの背景をご紹介します。
世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)
2021年に行われた「世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)」において、同フォーラムの創設者であり会長でもあるクラウス・シュワブ氏は以下のように述べました。
「第2次世界大戦後から続くシステムはもはや時代遅れだ。環境破壊を起こし、持続性に乏しい。人々の幸福を中心とした経済に考え直すべきだ」
同年のダボス会議のテーマは「グレート・リセット」でした。人々の幸せを前提として社会経済システムのすべてを刷新するグレート・リセットを実現するには、ウェルビーイングの見直しが必要です。ダボス会議の影響力は大きく、世界にウェルビーイングへの流れを加速させました。
OECD Education 2030
「OECD Education 2030」は、2030年の教育の展望に対して、38ヵ国の先進国が加盟するOECD(経済協力開発機構)がまとめたものです。
不確実な時代を生きる子供たちは、好奇心や想像性、強靭さ、自己調整といった力とともに、他者のアイディアや見方、価値観を尊重したり、その価値を認めたりする力が重要であるとして、自分だけでなく家族、友人、知人、地球全体のウェルビーイングを考えることの必要性を述べています。
【参照】文部科学省「OECD Education 2030 プロジェクトについて」|文部科学省(2018年5月)
https://www.oecd.org/education/2030-project/about/documents/OECD-Education-2030-Position-Paper_Japanese.pdf
コロナ禍を背景とした健康意識の向上
新型コロナウイルス感染症の拡大によって、ニューノーマル(新しい常態)な社会が到来し、個人レベルでウェルビーイングについて考える機会が増えたことも、ウェルビーイングが重要視される背景のひとつです。
アフターコロナを見据えた健康意識、ひいては「生き方」への意識の高まりは、ウェルビーイングの浸透に大きく影響しています。
新たな経済概念の誕生
世界では、ウェルビーイングの観点から誰のための経済なのかを考えた「ウェルビーイング・エコノミー」「ドーナツ経済学」「ステークホルダー資本主義」といった新しい経済概念が次々に誕生しています。
2018年に開催されたOECDのフォーラムでは、幸福な経済を構築するという共通の目的を前進させるために「Wellbeing Economy Governments」という機関が発足しました。本機関には、スコットランド、ニュージーランド、アイスランド、フィンランド、ウェールズが加盟するなど、世界経済全体の動きもウェルビーイングに向かって加速しています。
人材の確保
人手不足が進む現代社会の中で優秀な人材を確保し続けるには、健康的に安心して働ける環境が不可欠です。ウェルビーイングで従業員のメンタルヘルスやモチベーションを高め、多様な働き方を選択できるようにすることで、既存人材の定着も期待できるでしょう。
SDGsの項目
世界各国が取り組む「持続可能な開発目標(SDGs :Sustainable Development Goals)」の目標のひとつとして、「GOOD HEALTH AND WELL-BEING(すべての人に健康と福祉を)」が掲げられています。
これにより、ウェルビーイングは時代に合った経営のキーワードとして、広く認知されるようになりました。
日本でのウェルビーイングへの関心の高まり
日本国内でも、ウェルビーイングへの関心は確実に高まっています。政府、企業間でも、ウェルビーイングに注目した発言や取り組みが多く聞かれるようになりました。
例えば、自民党が実施する「日本Well-being計画推進プロジェクト」です。同党は、満足度・生活の質に関する調査と、新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化・ウェルビーイングに関する関係省庁の連携などを進めています。
ウェルビーイングという言葉は、内閣府による「経済財政運営と改革の基本方針2019」(いわゆる、骨太の方針2019)から登場し、2021年にはウェルビーイングに関するKPIを定めることが示されました。
また、デジタルの力で地方の個性を活かし、社会課題の解決を図るデジタル庁の「デジタル田園都市国家構想」でもウェルビーイングに着目しています。
【参照】内閣府「第2回Well-beingに関する関係府省庁連絡会議」|内閣府(2022年6月)
https://www5.cao.go.jp/keizai2/wellbeing/action/20220621/agenda.html
【参照】内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2019」|内閣府(2019年6月)
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2019/decision0621.html
【参照】デジタル庁「デジタル田園都市国家構想」|デジタル庁(2022年10月)
https://www.digital.go.jp/policies/digital_garden_city_nation/
企業がウェルビーイングを実践するメリット
ESGの観点で企業を見る意識が浸透する中、事業戦略にウェルビーイングを取り入れる企業が増加しています。企業がウェルビーイングを実践すると、どのような効果やメリットが期待できるのでしょうか。
従業員の満足度アップによる業績向上
企業がウェルビーイングに取り組むことの第一のメリットは、従業員満足度の向上です。ウェルビーイングの向上によって、従業員は心身ともに健康な状態で働けるようになり、モチベーションも高まるはずです。そんな好循環が生まれると生産性が高まり、業績アップも期待できるでしょう。
離職数の減少
企業が、ウェルビーイングを重視して従業員を守る意思を示すと、従業員の企業への信頼度が高まることが期待されます。既存人材のエンゲージメントが高まれば、自然と離職数の減少にもつながるでしょう。
優秀な人材の確保
近年、若い世代を中心として、ウェルビーイングを重視して仕事を探す人が増加しています。終身雇用制が事実上崩壊し、人材の流動性が高まる中、健康的に働けることは企業にとって重要なアピールポイントのひとつです。ウェルビーイングに取り組むことは、優秀な人材を確保するための施策としても有効だといえます。
ビジネスの現場におけるウェルビーイング
元々、医療・福祉の分野の用語だったウェルビーイングは、現在ではビジネスの現場における環境や働き方の状態を示す指標のひとつになっています。世界での関心の高まりに加えて、働き方改革関連法案の施行に伴う働き方の多様化とそれに対する意識の変化、経済産業省によるウェルビーイング経営(健康経済)の促進などが後押しになっていると考えられます。
それでは、ビジネスの現場におけるウェルビーイングは、具体的にどのように取り組めば良いのでしょうか。企業の取り組み例としては、下記の6つが挙げられます。
ビジネス現場でのウェルビーイングの取り組み例
- コミュニケーションの促進:個人面談の実施、イベント開催、サークル活動
- 職場環境の改善:フリーアドレス、リモートワーク、コミュニケーションスペースの導入
- 福利厚生の充実:フィットネスクラブなどの割引利用
- 人事評価方法の見直し:従業員が自身の評価方法に対して納得できているか
- セルフチェック、セルフケアの促進:心身の健康に関するセルフチェックの実践方法を周知
- 社内教育の強化:コミュニケーションスキル研修、フォロワーシップ研修の実施
経済産業省によるウェルビーイング経営(健康経営)の促進も後押しに
経済産業省がウェルビーイング経営を推進していることも、ビジネスの現場におけるウェルビーイングの促進に一役買っています。
ウェルビーイング経営とは、健康経営の指標となる無形資産のうちのひとつであり、企業のウェルビーイングへの取り組みが従業員のエンゲージメント向上に与える効果に注目した経営手法です。従業員が身体的・精神的に健康な状態で働けるようサポートするとともに、社会的に満たされるような環境と制度を整え、従業員の満足度と企業に対する信頼をさらに高めて結びつきを深めます。
企業は自社の利益だけでなく、組織に関わるすべての人の幸せに寄与することで、企業価値を高めることができるでしょう。ウェルビーイング経営を実現できれば、生産性向上、離職防止、優秀な人材の獲得といった効果が期待できます。
続いては、実際のビジネスシーンにおいてウェルビーイングがどのように取り組まれているのか、具体的な事例を見ていきましょう。
味の素株式会社の事例:味の素グループ健康宣言
味の素株式会社は、2018年に健康経営宣言を制定。創業時から掲げている「おいしく食べて健康づくり」という志を勤務環境にも反映し、「社員のこころとからだの健康を維持・推進できる職場環境づくり」を進めています。実際にどのような取り組みを行ったのか、特徴的なものを挙げてみましょう。
・全員面談
最低でも年1回は、国内全従業員と産業医・保健師・看護師との面談が行われます。健康診断の結果では見つけにくい潜在的な心身の不調も見逃さず、適切な保健指導などにつなげるためです。
また、過剰労働による健康への影響を未然に防ぐため、時間外労働の削減、長時間労働者への医療スタッフの面接指導なども徹底しています。
・自社製品を活用したスクリーニング検査
悪性腫瘍の早期発見に有効な自社製品「アミノインデックス」を定期健康診断の任意検診項目として導入。早期発見につながった事例もあるようです。
【参照】味の素「味の素グループ サステナビリティデータブック 2017」|味の素株式会社(2017年)
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/activity/csr/pdf/2017/79-80.pdf
株式会社イトーキの事例:健康経営宣言
オフィスをはじめとしたさまざまな場所での快適な勤務をサポートする株式会社イトーキ。同社は、2017年2月に「健康経営宣言」を制定しました。
社員が健康的に働ける環境づくりにも尽力し、スタンディングワークの推奨や歩数がアップするレイアウトの工夫などによって、働きながら健康になれる「Workcise(ワークサイズ)」を提唱・実践しています。
【参照】イトーキ「イトーキ健康経営宣言」|イトーキ(2019年11月)
https://www.itoki.jp/company/health.html
楽天株式会社の事例:「楽天主義」を軸に企業文化を醸成
楽天株式会社は、どんなに優れたビジネスモデルでも、成功するか否かは人次第という考えにもとづいて、自社で働く人のウェルビーイングに創業当初から取り組んできました。
軸にあるのは、企業独自の価値観をまとめた「楽天主義」です。「何をウェルビーイングな状態とするか」の指標に楽天主義を置き、創業メンバーの一人がCWO(Chief Well-being Officer)となって、その傘下で3つの部門による取り組みを進めています。
<ウェルビーイングを促進する3つの部門>
-
ウェルネス部
ウェルネス部は、ウェルビーイング促進につながるイベント企画・運営、仕組みづくり・環境づくりなどを担当。カフェテリアやフィットネスジムなどで、従業員の肉体的・精神的な健康をサポートします。
-
エンプロイーエンゲージメント部
エンプロイーエンゲージメント部は、楽天主義の浸透を図る部門です。企業と組織のつながりを深めることを目指します。
-
サスティナビリティ部
サスティナビリティ部は、ESG情報の発信等を通じて、ソーシャルウェルビーイングの実現に取り組みます。
【参照】楽天株式会社「従業員の健康・ウェルネス」|楽天株式会社
https://corp.rakuten.co.jp/sustainability/employees/wellness/
株式会社アシックスの事例:自社開発の健康増進プランを提供
スポーツや健康に関する商品・サービスを提供する株式会社アシックス。同社は従業員の健康を最重要視し、事業内容と企業風土に即した取り組みで従業員と家族のウェルビーイング実現を目指しています。下記は、同社が推進しているウェルビーイングへの取り組み例です。
<ウェルビーイングへの取り組み例>
-
健康増進プログラムを提供
自社開発の健康増進プログラムを従業員に提供し、一人ひとりに合った健康増進プランで健康づくりをサポートしています。
-
運動推進セミナー
プレミアムフライデーやノー残業デーを活用し、セミナーを通じて従業員の運動機会を創出。
-
メンタルヘルス研修
グループに所属する全員に向け、セルフケア、ラインケアなどのメンタルヘルス研修を実施しています。
【参照】株式会社アシックス「アシックスの健康経営」|株式会社アシックス(2022年10月)
https://corp.asics.com/jp/csr/wellbeing
経済産業省が、2,000法人の評価結果を一括開示
ウェルビーイングは、日本でも着実に浸透してきています。経済産業省は、健康への投資のさらなる促進を目的として、「2021年度健康経営度調査」の評価結果開示に同意した2,000社分の各種データ、健康経営の「偏差値」が項目別にわかる成績表を公表しました。これまで、個別に送付して取り組み改善に役立てていた評価結果(フィードバックシート)の開示可否を各社に確認し、同意が得られた場合に開示することで各企業のステークホルダーによる活用を促すためです。
健康経営は企業の持続的成長に欠かせないものとして、投資家や求職者からの注目も高まっています。結果の公表に同意し、経済産業省のサイトなどを通じて取り組み状況が可視化されれば、企業に対する評価が向上することも期待できます。
健康経営の結果として生じた職場風土は、重要な無形資源になりうるものです。企業は積極的に結果を公表するとともに、その内容を丁寧に見直し、自社の勤務環境の改善を図り、ステークホルダーからの信頼をより高めていくことが期待されています。
【参照】経済産業省「令和3年度健康経営度調査に基づく2,000社分の評価結果を公開しました」|経済産業省(2022年3月)
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220315004/20220315004.html
ウェルビーイングで無形資産の価値を高めよう
これからの時代の投資家は、健康経営の成果である職場風土という無形資産を評価し、企業が持続的に自社の価値を高めていけるかどうかを見極めます。
企業は、「従業員がウェルビーイングの実現に向けた企業の姿勢を従業員がどう評価しているか」「従業員は安心して考えを述べられているか」「従業員同士の信頼や結びつきは強いか」といったことを指標として、無形資産の向上に努める必要があります。
ウェルビーイングにはさまざまな取り組み方がありますが、ウェルフェアとして健康増進につながるサービスを取り入れるのも有効な方法のひとつです。
「マイナビ健康経営」では、福利厚生サービス「ウェルネスサポート」を提供しています。この機会にぜひ、導入をご検討ください。
<監修者> |
&res=1280x720&is_new_uid=true&_tcuid=202504031603210038&_tcsid=202504031603210100)