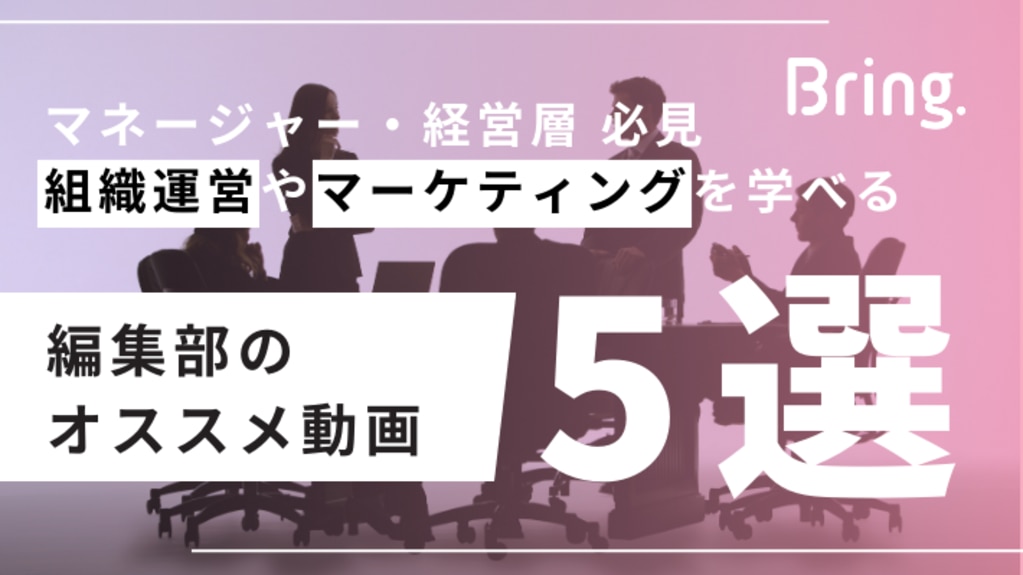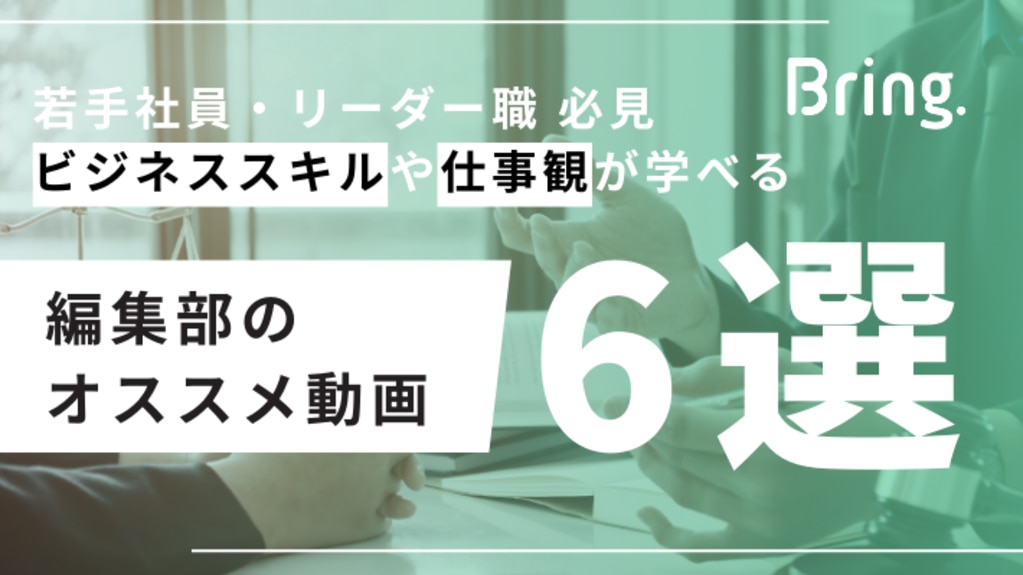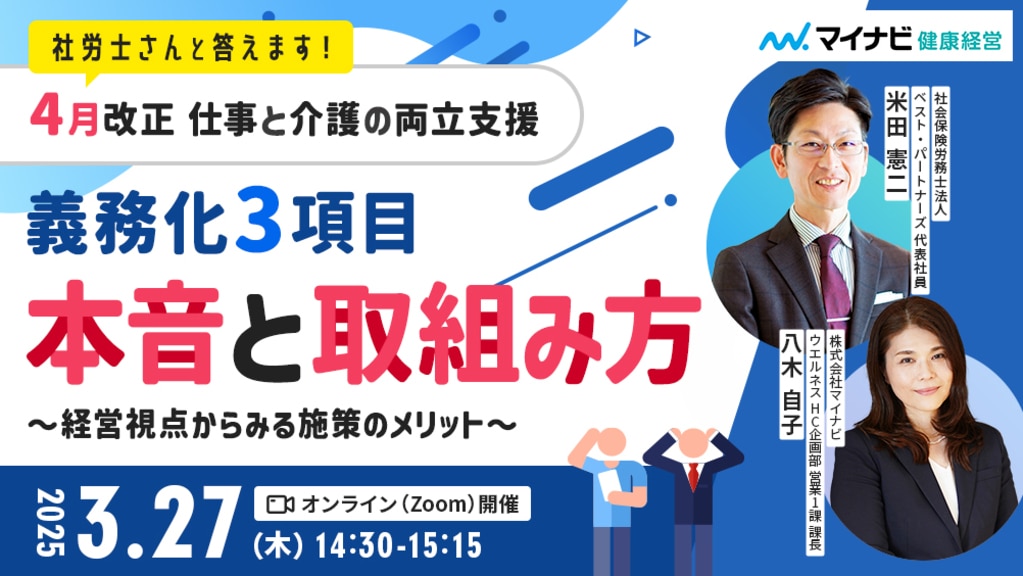セカンドキャリアとは?転職までの準備や、企業側の採用メリット・注意点を解説
近年、セカンドキャリアの概念が変わりつつあります。働き手が重視したいセカンドキャリアの目的や、セカンドキャリア推奨で生まれる企業のメリット、注意点を解説します。
目次[非表示]
- 1.セカンドキャリアとは?その目的や企業側のメリット、注意点を解説
- 2.時代によって変わるセカンドキャリアという概念
- 3.年代別・セカンドキャリアの背景と目的
- 4.セカンドキャリア転職に必要な準備
- 4.1.長期的なライフプランを共有する
- 4.2.働き手は、自分の現状を知る
- 4.3.学びや経験の量を増やす
- 4.4.セカンドキャリア支援セミナーなども活用する
- 4.5.キャリアアドバイザーを活用する
- 5.セカンドキャリアで注目すべき2つの概念
- 6.セカンドキャリア人材の採用を行う企業のメリットと注意点
- 6.1.育成の手間やコストをかけずに優秀な人材を採用できる
- 6.2.人手不足と経験値不足が解消できる
- 6.3.受け入れの環境整備が必要である
- 7.在籍出向・転籍出向(移籍)という選択肢もある
- 8.働き手も企業も、セカンドキャリアという選択肢を積極的に検討しましょう
セカンドキャリアとは?その目的や企業側のメリット、注意点を解説
かつて「セカンドキャリア」といえば、引退したスポーツ選手や、定年退職した会社員の第二の人生を指すのが一般的でした。しかし近年、働き方の多様化に伴ってその意味は拡大し、セカンドキャリアは現役ビジネスパーソンの働き方と密接に関わるものになりつつあります。
ここでは、働き手における年代別のセカンドキャリアの目的や、セカンドキャリアを推奨することで生まれる企業側のメリット、注意点などを解説します。
時代によって変わるセカンドキャリアという概念
セカンドキャリアは、「second」と「career」からなる和製英語で、「第二の人生における働き方」のことです。元々は、プロスポーツに従事していた人が引退し、別の仕事を始めることを指す場合が多い言葉でした。プロスポーツ選手の場合、最初のキャリアを完全に終わらせて次のキャリアを築いていくことから、「2つ目のキャリア」の意味で「second」という言葉が使われるようになったと考えられます。
一方、ビジネスシーンでは、定年退職したり早期退職したりしたビジネスパーソンの新しい働き方を意味し、これまでの経験やスキルを活かして新しいキャリアを開拓する際に使われていました。
これも、新卒一括採用、終身雇用といった日本型雇用システムのもと、「新卒で採用された会社に一生尽くす」「年齢に応じてキャリアアップし、定年まで働く」といった勤務スタイルが一般的だった時代の「2つ目のキャリア」の意味合いが強いでしょう。
しかし、最近では、多くの人が転職を経験したり、早期退職して起業したりするようになり、日本型雇用システムに沿ったキャリアを選ぶ人は減りつつあります。また、雇用期間が長期化するほど企業の負担が増える終身雇用は、経済が停滞する時代においては維持することが難しくなっている側面もあります。
こうした変化に伴い、セカンドキャリアは、キャリアチェンジの中でも人生が変わるような大きな転換点を指すようになりました。現在では、30代、40代であっても、長期的なキャリアプランにもとづいて新しいステップを踏み出すことをセカンドキャリアと呼ぶようになっています。
年代別・セカンドキャリアの背景と目的
セカンドキャリアは年代によってどのような状況が想定されるのでしょうか。年代別にセカンドキャリアの背景や目的について見ていきましょう。
30代:経験を武器に、本来やってみたかった仕事を探せる
就職活動の際にしっかりと企業研究をしたとしても、実際に働いてみなければわからないことは多いものです。社会や組織、仕事に慣れることに必死だった20代の頃と比べると、経験を重ねて落ちつきが生まれる30代だからこそ見えてくることはあります。本来やってみたかった仕事や、目指したいキャリアパスが見えてきて、現職で働き続けることに迷いが生まれることもあるでしょう。
30代は、これまで携わってきた仕事を時系列で振り返り、得てきたスキルや成果を洗い出す「キャリアの棚卸」にかかる時期であり、納得できるセカンドキャリアに向けて歩き始められる時期です。これまで培ってきたものをベースに、経験やスキルを活かした転職を目指す人が多いです。
なお、キャリアの棚卸で洗い出すのは、数値に表れる実績に限りません。日々コツコツと行ってきたことについても書き出すと、自身の思わぬ特徴が見つかり、可能性が広がることがあります。
40代:将来を見通してスキルアップを考えられる
40代になると、ファーストキャリアで積んだ経験や実績、その人自身の志向性にもとづいて、マネジメントクラスにステップアップする人や、現場でスペシャリストを目指す人など、ある程度キャリアの方向性が分かれる時期です。同時に、ファーストキャリアをこのまま継続した場合のゴールが見えてくる時期でもあるでしょう。
40代がセカンドキャリアを考える際には、「今の自分」と「実現したいゴール」について具体的に考え、将来を見通したスキルアップができる道を見つける必要があります。
特に、まったく違う業界でゼロからキャリアを開拓していきたいと考えている場合は、業界・業種を超えて活かせる自分の強みを見つけておくことが大切です。
40代は、「今の自分にできることは何か」「これから身につけられることは何か」「これから何をやりたいか」を深掘りした上で、実現可能性のある将来像を描いていく時期となります。
また、家庭を持っている場合は、自身のセカンドキャリアを考える時期と、子供の進学などが重なるケースがあります。自分のために生きるのはもちろん大切ですが、家族の未来も設計した上で無理のない計画を立てることが大切です。キャリアプランと同時にマネープランも見直し、家族の同意を得て方向性を決めることをおすすめします。
50代:自分のための新しい生き方を選ぶことも可能となる
50代となると、現職でキャリアを積み上げて悠々自適の老後に向かうのもひとつの選択肢ですが、これまでの実績に期待してくれる会社に転職し、新規事業に関わったり、得意分野で起業したりすることもできます。キャリアの総決算のつもりで身につけたスキルを洗い出し、幅広い可能性を考慮してセカンドキャリアを考えるといいでしょう。
すでに子供が手を離れている場合は、自分やパートナーためのライフプランを考えられる年齢でもあります。長年勤めた会社での制約や、親の責務から少し解放されることで、今まで考えもしなかった新しい夢が思い浮かぶこともあるかもしれません。
50代は、老後をどこで、どんな風に過ごしたいかといった長期的なライフプランと並行して、セカンドキャリアの可能性を模索できるはずです。
セカンドキャリア転職に必要な準備
セカンドキャリアに限らず、新しい挑戦にはリスクがつきものです。想定されるリスクを洗い出し、適切な対策を立てて、リスクの最小化を図りましょう。
ここでは、セカンドキャリアを実現するためにやっておきたい準備についてご紹介します。
長期的なライフプランを共有する
セカンドキャリアは、そのままキャリアのゴールにつながる可能性が高いといえます。働き手が「今やりたいこと」だけにフォーカスすると将来的にずれが生まれてしまうこともあるため、企業と働き手とで、長期的なキャリアプランとライフプランの両立を共有しておきましょう。
なお、下記の7つは、明確に答えを言語化しておくべき事柄です。
<言語化しておくべき事柄>
- 結婚するか、しないか
- 結婚するならいつ頃か
- 仕事と育児のバランスをどうするか
- どんな領域で働くか
- いつまで働くか
- どんな仕事をしたいと思っているのか
- 最終的に、どんなキャリアのゴールを迎えたいか
働き手は、自分の現状を知る
セカンドキャリアを実現する上で、働き手は「自分の現状を知る」ことも欠かせません。理想的なセカンドキャリアをつかみ取るために、今の自分を正確に知ることが必要です。
まずは、「今の自分にできること(can)」「できるようになりたいこと(will)」「希望どおりのキャリアを実現するにはできなければならないこと(must)」の3つの観点から、自身の経験とスキルを客観的に見直します。その上で、「can」はさらに伸ばし、「will」と「must」は習得する努力をします。
例えば、セカンドキャリアに資格が必須の場合は、資格取得にかかる時間や費用、学ぶ方法について調べ、現職と並行できそうなら勉強を始めてみてはいかがでしょうか。
企業も、セカンドキャリアを目指す働き手に必要な経験とスキルを整理し、「何が足りないか」、「何を習得すべきか」を明確化しておきましょう。
学びや経験の量を増やす
セカンドキャリアを考える人は、これまでの経験やスキルに一定の自信を持っているのではないでしょうか。しかし、世の中の常識や技術、知見は日進月歩であり、少しでも油断すれば時代に置いて行かれてしまいます。特に、変化の早いIT業界などではそうした傾向が強いといえます。
そのため、企業もセカンドキャリアの人材が学び続けられる環境は整備しておく必要があるでしょう。常に新しいことを学び、積極的にチャレンジし続ける姿勢を共有することは、働き手にとっても企業にとっても質の高い人材の充実につながります。
セカンドキャリア支援セミナーなども活用する
「漠然とやりたいことはあるけれど、何から手をつけていいかわからない」「同じ夢を持つ仲間が欲しい」といったことを考えている働き手は、民間企業やハローワークで実施しているセカンドキャリア支援セミナーに参加するという選択肢もあります。セミナーに参加することで、人脈ができてセカンドキャリアの可能性が広がったり、同じ悩みを持つ仲間の存在に励まされたりと、良い効果が期待できるでしょう。
企業もセカンドキャリア支援セミナーを展開していけば、向上心の高いセカンドキャリア人材と出会う確率が高まります。
キャリアアドバイザーを活用する
人材紹介会社の無料転職相談では、キャリアアドバイザーが相談者である働き手の経験やスキルを整理し、その人にマッチする企業を紹介してくれます。相談することで自分のキャリアを再確認でき、セカンドキャリアのビジョンが広がるかもしれません。
企業が人材紹介会社を利用する際は当然ながら料金はかかりますが、自社が求める人材を選定し続けてくれるため、効率的に自社にマッチした人材と出会えます。
セカンドキャリアで注目すべき2つの概念
充実したセカンドキャリアのために知っておきたい概念として、「リカレント教育」と「リスキリング」があります。ここでは、それぞれがどのような意味を持つものなのかを確認していきましょう。
リカレント教育
リカレント教育とは、学校教育から離れた後、個々のタイミングで学び直し、仕事で求められる能力を身につけていくことです。厚生労働省は、経済産業省、文部科学省と連携して、下記のような施策を展開しています。
<官庁によるリカレント教育の施策>
「職場における学び・学び直し促進ガイドライン」の策定
厚生労働省は、「職場における学び・学び直し促進ガイドライン」を策定しています。職場における「人への投資」の充実に向け、基本的な考え方などを体系的に示しています。
学びにかかる費用の支援
厚生労働省は、「学びにかかる費用の支援」も行っています。対象講座を修了した場合に自ら負担した受講費用の20~70%を支給する教育訓練給付金、一人親で育った方が国家資格やデジタル分野の資格取得に向けた修学をする場合に月10万円(※)を支給する高等職業訓練促進給付金などで学び直しをサポートします。
(※)住民税課税世帯は月7万5千円、修学の最終年限1年間に限り4万円加算
【参照】厚生労働省「リカレント教育」| 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18817.html
労働者が受講できる公的職業訓練
厚生労働省は、職業スキルや知識などを無料で習得できるトレーニングを実施しています。また、事業主が従業員の人材教育の一環としてリカレント教育を行う場合、訓練経費や制度導入経費等の助成が受けられる「人材開発支援助成金」や、訓練を低コストで実施できる「生産性向上支援訓練」、無料でキャリアコンサルタントにコンサルティングが受けられる「企業内のキャリアコンサルティング導入支援」などを活用することもできます。
【参照】厚生労働省「職場における学び・学び直し促進ガイドライン」|厚生労働省(2022年6月)
https://www.mhlw.go.jp/content/11801000/000957888.pdf
【参照】厚生労働省「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について」|厚生労働省(2022年3月)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062986.html
リスキリング
リスキリングは、「新しい職業に就くため、または今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得すること(させること)」と定義されます。
リカレント教育が新しい学びのためにいったん仕事と距離を置くのに対し、リスキリングは必ずしも転職や職種の変更を目的とせず、現職で学べる点が特徴です。多くの場合、企業が従業員に働きかけて行われます。
【おすすめ参考記事】
少子高齢化に伴う人材不足が続く中、従業員の能力アップをサポートするリカレント教育、企業と国のグローバルな競争力向上を実現する人材を育成するリスキリングが果たす役割は非常に大きいといえるでしょう。
企業には、自社のためだけでなく社会のために、従業員の主体的な学びを支援する姿勢が求められます。
セカンドキャリア人材の採用を行う企業のメリットと注意点
企業の視点で見ると、セカンドキャリア人材の採用には、メリットと注意点があります。それぞれどのようなことが想定されるのかを確認していきましょう。
育成の手間やコストをかけずに優秀な人材を採用できる
セカンドキャリア人材は、十分なスキルと経験値を持っています。そのため、セカンドキャリア人材の採用を行った企業は、それほどオンボーディングに時間とコストをかけることなく優秀な人材に即戦力として活躍してもらうことができます。人材育成に手間やコストが比較的かからないのは、企業にとって大きなメリットです。
人手不足と経験値不足が解消できる
少子高齢化に伴って労働力が不足する中、「定年退職はしても、何かしら社会の役に立つ仕事がしたい」「働ける限りは働き続けたい」と考えるアクティブなシニアは増加しています。こうしたシニア層をセカンドキャリア人材として採用することで、企業は労働力不足と現場の経験値不足を一度にカバーできるというメリットがあります。
受け入れの環境整備が必要である
セカンドキャリア人材の採用の注意点としては、人材を受け入れるための環境を整備する必要が挙げられます。中でも、年功序列で働いてきたシニア世代を採用した場合、賃金をどれだけ負担するかは大きな課題となる点に注意が必要です。
在籍出向・転籍出向(移籍)という選択肢もある
企業がセカンドキャリアの人材を迎え入れる、もしくは送り出す際には、「在籍出向」と「転籍出向」を検討することもできます。出向をセカンドキャリアの選択肢のひとつとして活用すると、どのようなメリットが得られるのか確認していきましょう。
企業における在籍出向のメリットと注意点
在籍出向とは、出向者が「出向元」の企業に籍を置いたまま、出向先の企業で勤務する働き方です。出向期間満了後は自社に戻ってくるため、他社で身につけた経験や知見を自社に還元してくれることが期待できます。条件を満たせば、政府からの助成金を受け取れる可能性もあるため、メリットは多いです。
なお、在籍出向を行うにあたっては、出向対象の従業員の同意を得るように注意してください。
特に、下記の2点を確認した上で、出向する従業員を選定するようにしましょう。
<在籍出向を活用する際の注意点>
- 出向先の仕事と、従業員のキャリアの志向性がマッチしていること
- 出向によって、従業員、出向元、出向先の3者に利益があること
【おすすめ参考記事】
企業における転籍出向(移籍)のメリットと注意点
転籍出向とは、従業員が出向元企業との労働契約関係を解消した上で、出向先企業と雇用関係を結び直す出向の形です。報酬が高いシニア層などを解雇せずに人件費を削減でき、当該の従業員には新しい勤務先を用意できることが企業にとっての最大のメリットです。
ただし、転籍出向をする従業員は、企業の意向で労働環境を変えなければならず、その点は負担となります。従業員に社会通念上不当な不利益が起こらないことを前提とし、必ず従業員の同意を得て行うように注意しましょう。
【おすすめ参考記事】
働き手も企業も、セカンドキャリアという選択肢を積極的に検討しましょう
超高齢社会に突入した日本において、労働人口の多くを占めるミドル・シニア層のセカンドキャリアを考えることは喫緊の課題です。
企業には、働き手が幸せに働き続けられる社会をつくることで未来の日本に貢献するため、セカンドキャリア支援への取り組み強化が求められています。これからは、出向という選択肢も視野に入れ、ミドル・シニア層が活躍し続けられる社会をつくっていきましょう。
なお、セカンドキャリアを検討する上で、出向という選択肢もお考えの方は、お気軽に「マイナビ健康経営」にご相談ください。セカンドキャリアの導入についてより詳しく知りたい方は、下記の記事もご参照いただくことをおすすめします。
【おすすめ参考記事】
<監修者> 丁海煌(ちょん・へふぁん)/1988年4月3日生まれ。弁護士/弁護士法人オルビス所属/弁護士登録後、一般民事事件、家事事件、刑事事件等の多種多様な訴訟業務に携わる。2020年からは韓国ソウルの大手ローファームにて、日韓企業間のМ&Aや契約書諮問、人事労務に携わり、2022年2月に日本帰国。現在、韓国での知見を活かし、日本企業の韓国進出や韓国企業の日本進出のリーガルサポートや、企業の人事労務問題などを手掛けている。 |
&res=1280x720&is_new_uid=true&_tcuid=202504011508397046&_tcsid=202504011508398301)