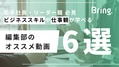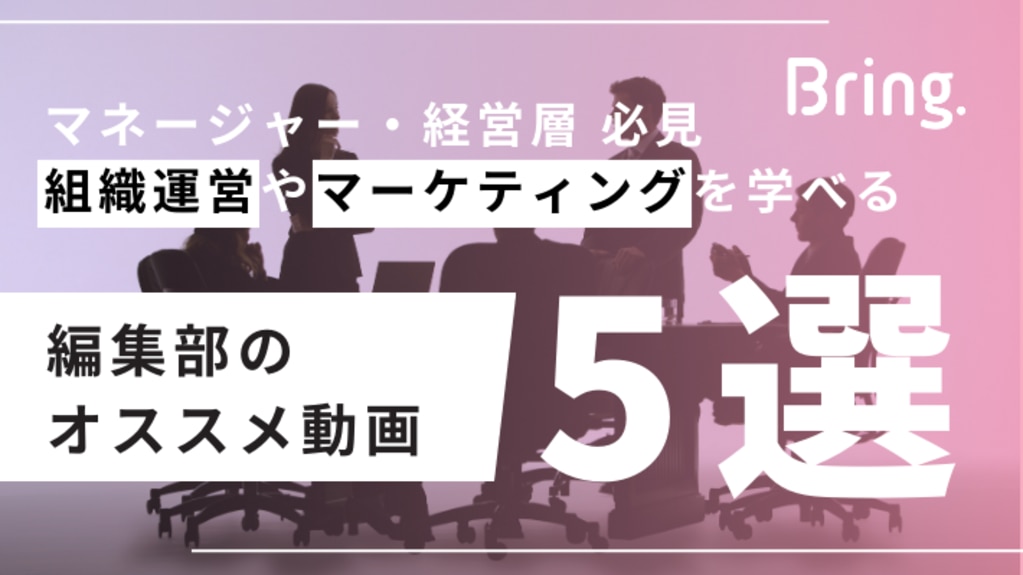健康経営の基本となる健康診断!受診率を上げるための対策
企業の持続的な成長には、従業員の健康管理が欠かせません。特に近年は、従業員の健康を経営戦略の一環として考える「健康経営」が注目されており、その実践には健康診断の受診率向上が重要な取り組みのひとつとなっています。健康診断の受診率を上げるためには、従業員に受診のメリットをわかりやすく提示し、就業規則にも受診について明記するなどの対策が必要です。
本記事では、健康診断の種類や費用、受診率を上げるための対策、さらに健康診断後に企業が行うべきことについて詳しく解説します。
目次[非表示]
企業には健康診断を実施する法的義務がある
企業は、労働安全衛生法第66条にもとづき、従業員に対して医師による健康診断を実施する法的義務があります。これは、従業員の健康状態を定期的に確認し、病気の早期発見や予防を目的とした制度です。
企業が健康診断を実施しない場合、労働基準監督署からの指導・勧告を受けることがあり、最大50万円の罰金が科せられる可能性もあります。また、従業員にも受診義務がありますが、個人が拒否した場合に法的な罰則はありません。ただし、企業の就業規則にもとづき、受診を義務付けている場合は、懲戒処分の対象とすることが可能です。
さらに、企業が従業員の健康診断の未受診を放置し、その結果として健康障害が発生した場合、労働契約法第5条に定められた安全配慮義務違反となる可能性があるため注意しましょう。企業は、単に健康診断を実施するだけでなく、受診を徹底し、従業員の健康を守る責任を果たすことが求められます。
【参照】厚生労働省「労働安全衛生法にもとづく健康診断の概要」|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/01/dl/s0119-4h.pdf
【参照】e-GOV法令検索「労働契約法(労働者の安全への配慮)第五条」
https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
健康経営のためにも健康診断は必須
企業が健康経営を進める上で、健康診断の実施と受診率の向上は不可欠な要素です。健康経営とは、従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に実践することを指します。これは、単に従業員の健康を守るだけでなく、組織の生産性向上や企業ブランドの向上にもつながる経営手法として注目されています。
経済産業省が推進する「健康経営優良法人認定制度」においては、健康診断の受診率は重要な評価基準のひとつです。例えば、大規模法人部門・中小規模法人部門のいずれにおいても、「従業員の健康課題把握と必要な対策の検討」という評価項目の中で「従業員の健康診断の受診(受診率実質100%)」が含まれています。
この基準を満たすことで、企業は健康経営優良法人として認定を受ける可能性が高まり、企業価値の向上や優秀な人材確保にもつながります。つまり、従業員の受診率を高めるための取り組みを行うことが、健康経営の成功には重要といえるでしょう。
【参照】ACTION!健康経営「申請について」|健康経営優良法人認定事務局
https://kenko-keiei.jp/application/
健康診断の対象者
企業における健康診断の対象者は、正社員だけではありません。労働安全衛生法では「常時使用する労働者」に健康診断を義務付けています。これには、雇用期間が1年以上、または更新により1年以上見込まれる契約社員やパート、アルバイトも含まれます(後述の一般健康診断の種類のうち、雇入時の健康診断と定期健康診断に限る)。ただし、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上の場合のみです。
また、週の所定労働時間が4分の3に満たない場合でも、2分の1以上働いている場合は、「健康診断の実施が望ましい」とされています。これは、従業員の健康管理を促進する目的で推奨されているものです。
一方、派遣社員については、派遣元である派遣会社が健康診断を実施するため、派遣先企業は実施義務を負いません。ただし、派遣社員の健康維持を支援するために、健康診断の受診を促すことは企業の責任の一環として重要です。企業は、健康診断の対象者を正しく把握し、適切な受診環境を整えることが求められます。
【参照】厚生労働省 山口労働局「パートタイム労働者※ の健康診断を実施しましょう」|厚生労働省(2024年8月)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/content/contents/001929184.pdf
健康診断の種類
企業が実施する健康診断には、「一般健康診断」と有害な業務に従事する従業員のための「特殊健康診断」があります。さらに、従業員の健康維持をサポートする手段として、企業ではなく健康保険組合や自治体などが実施する「特定健康診査(特定健診)」もあります。ここからは、それぞれの概要について解説しましょう。
一般健康診断
一般健康診断には、以下の5種類があります。特に、雇入れ時の健康診断と定期健康診断は、一部を除くすべての従業員に義務付けられており、企業は必ず実施しなければなりません。
■一般健康診断の種類と対象者
|
健康診断の種類 |
対象者 |
実施時期 |
| 雇入時の健康診断 |
常時使用する労働者 |
雇入れの際 |
定期健康診断 |
常時使用する労働者(深夜の特定業務従事者を除く) |
1年以内ごとに1回 |
| 特定業務従事者の健康診断 |
労働安全衛生規則第13条第1項第2号(特1)に掲げる業務に常時従事する労働者 |
左記業務への配置替えの際、6ヵ月以内に1回 |
海外派遣労働者の健康診断 |
海外に6ヵ月以上派遣する労働者 |
海外に6ヵ月以上派遣する際、帰国後および国内業務につかせる際 |
| 給食従業員の検便 |
事業に付属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者 |
雇入れの際、配置替えの際 |
また、雇入れ時健康診断および定期健康診断は、労働安全衛生規則で定められた以下の11項目の検査が実施されます。
<雇入れ時の健康診断・定期健康診断の項目>
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
- 血糖検査
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 心電図検査(安静時心電図検査)
※定期健康診断では、医師が認めた場合、身長や腹囲などの一部の項目について省略できます。
特殊健康診断
有害な業務に常時従事する従業員には、健康被害を防ぐための「特殊健康診断」が義務付けられています。これは、有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、石綿などの有害業務に常時従事する従業員を対象に実施されるものです。
また、有害業務に関連する健康診断には、「じん肺健康診断」と「歯科医師による健康診断」もあります。じん肺健康診断は、粉じん作業によるじん肺の早期発見と進行管理を目的とした検査です。さらに、歯科医師による健康診断は、塩酸や硝酸などの有害ガスや粉じんを扱う業務に従事する従業員の口腔内の健康を守るために実施されます。
これらの健康診断は、一般的な健康診断とは異なり、特定の職業リスクを考慮した検査項目が設定されています。企業は、該当する業務に従事する従業員に対し、適切な検査を実施することが必要です。
【参照】厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~」|厚生労働省(2013年3月)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf
特定健康診査
特定健康診査(特定健診)は、企業が実施する健康診断とは異なり、健康保険組合や自治体などが主体となって実施する健康診断です。40歳以上75歳未満の被保険者(健康保険組合・国民健康保険の加入者)を対象に、生活習慣病のリスクを評価し、メタボリックシンドロームの予防を目的として行われます。
また、「健康経営優良法人認定制度」の認定基準では、40歳以上の従業員の特定健診項目を含む健康診断のデータを保険者に提供することが求められています。さらに、特定健診の結果、生活習慣の改善が必要と判断された人に対し、企業が特定保健指導を案内し、支援体制を整えることも評価の対象です。
企業としては、定期健康診断と特定健診を同時に受診できる仕組みを整え、従業員の健康管理をサポートすることが望ましいでしょう。
【参照】厚生労働省「特定健診・特定保健指導について」|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html
【参照】株式会社日本総合研究所「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)今年度の概要」健康経営優良法人認定事務局(2024年8月)
https://kenko-keiei.jp/wp-content/uploads/2024/09/applicationvideo2025_chusho.pdf?utm_source=chatgpt.com
健康診断の費用
労働安全衛生法にもとづき企業に健康診断の実施が義務付けられている以上、その費用は企業負担となることが一般的とされています。これは、法令で明確に規定されているわけではないものの、行政の通達では「事業者が負担すべきもの」とされているためです。したがって、実務上ほとんどの企業が費用を負担しています。
また、受診にかかる時間の賃金についても、健康診断の種類によって異なります。一般健康診断(雇入れ時・定期健康診断)の受診時間については、労働時間として扱うかどうか、法律上の明確な規定はありません。ただし、企業が勤務時間内に受診を指示した場合は、労働時間とみなされる可能性があります。円滑な受診を促すため、受診時間分の賃金を支払うことが望ましいとされています。
また、有害な業務の従事者に向けた特殊健康診断では、受診時間は労働時間とみなされ、企業は賃金を支払う義務があります。従業員の受診を促すためにも、賃金の取り扱いを明確にし、スムーズな受診環境を整えることが重要です。
健康診断の受診率
企業における健康診断の受診率は、厚生労働省の「平成24年労働者健康状況調査」によると、81.5%にとどまっているというデータもあります。受診率が100%に達しない要因として、従業員の健康意識の低さや業務の忙しさなどが影響していることが少なくありません。
一方、先に説明した健康経営優良法人認定制度では、受診率「実質100%」が評価項目のひとつです。ここでいう「実質100%」とは、病気休職や育児休業などやむをえない理由を除いて、定期健康診断の受診率が100%の状態を指します。または、直近の受診率が95%以上で未受診者には適切な受診勧奨を行っている状態も含まれます。
企業は、従業員が健康診断を受けやすい環境を整え、積極的に受診を促す取り組みを進めることが重要です。健康診断の受診率実質100%を達成した企業の事例は、以下のおすすめ参考記事もぜひご覧ください。
【参照】厚生労働省「平成24年『労働安全衛生特別調査(労働者健康状況調査)』の概況」|厚生労働省(2020年9月19日)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/h24-46-50_05.pdf
▼健康診断の受診率100%企業事例
健康診断の受診率を上げるための対策
健康診断の受診率を向上させるためには、企業側の積極的な働きかけが重要です。ここからは、健康診断の受診率を上げるための対策を紹介します。
健康診断を受けるメリットを提示する
健康診断の受診率を上げるためには、健康診断を受けるメリットを従業員に示すことが重要です。健康診断を受けることで、病気の早期発見・予防が可能となり、治療や療養にかかる時間や費用の削減もできます。企業は、社内報や社内研修などを通して、こうしたメリットをわかりやすく伝えることで、従業員の健康診断に対する意識を高めることが大切です。
健康診断の日程を指定する
健康診断の受診は、業務の都合で受診が後回しになるケースも少なくありません。したがって、企業側が受診候補日を指定し、一斉受診できるよう調整することも効果的です。業務時間内に受診時間を確保したり、社内に巡回健診を導入したりすることで、従業員がスムーズに受診できる環境を整えるとよいでしょう。
健康診断の受診について就業規則に定める
従業員に健康診断の受診を義務付けるため、就業規則に受診に関する項目を盛り込むことも大切です。健康診断の未受診に対する、個人への法的な罰則はありません。しかし、就業規則に違反した場合の懲戒処分などの措置を明確にしておくことで、従業員に受診を促し、企業側の管理責任を果たすことにつながります。
健康診断にまつわる福利厚生を充実させる
健康診断の受診率を上げるためには、受診を促すような福利厚生制度の導入も選択肢のひとつです。例えば、健康診断を受けた従業員に対するインセンティブの提供や、受診結果にもとづく健康管理をアドバイスする相談窓口の設置などが挙げられます。また、ジムやフィットネス施設を従業員が割引価格で利用できる仕組みづくりも有効です。こうした制度を整えることで、従業員が健康管理に関心を持ち、積極的に健康診断を受ける風土を醸成できるでしょう。
従業員の健康をサポートする外部の検診サービスを利用する
健康診断の受診率を向上させるため、外部の検診サービスを活用するのも有効です。例えば、「けんさの窓口 福利厚生健診パッケージ」は、提携医療機関の医師または看護師が事業所を訪問し、従業員が勤務時間内に受診できる環境を提供できます。また、検査結果をWeb上で発行し、オンラインによる医師の診断を受けられるため、従業員が健診結果を手軽に確認できる点もメリットです。
検査項目には、生活習慣病、がんリスク、メンタルストレス、更年期障害などが含まれており、企業が従業員の健康管理を総合的にサポートできる仕組みになっています。こうした外部サービスの利用によって、忙しい従業員の健康維持や健康意識の向上につながり、健康診断の受診率アップにつながることが期待できます。
【けんさの窓口 福利厚生健診パッケージ】サービスページはこちら>
健康診断終了後に企業が行うべきこと
健康診断は受診して終わりではありません。企業は、診断結果の通知・管理や従業員へのフォローアップなどを行う必要があります。ここからは、健康診断終了後に企業が行うべきことを解説します。
従業員に検査結果を通知してデータを保管する
労働安全衛生法第66条の6にもとづき、企業は健康診断の結果を従業員に通知する義務があります。通知は文書で行い、封筒に入れるなどして個人情報の保護に配慮することが必要です。
また、健康診断の結果は、書面または電磁データで5年間保存する義務があります。特定健康診査(特定健診)の結果も、生活習慣病リスクの評価に活用できるため、定期健康診断と併せて管理することが望ましいでしょう。
所轄労働基準監督署に実施報告書を提出する
健康診断の結果は、一定の条件を満たす場合、労働基準監督署への報告義務が発生します。具体的には、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、「定期健康診断結果報告書」を提出する必要があります。
報告を怠ると、労働基準監督署から指導が入る可能性もあるため、実施後はすみやかに報告書を提出しましょう。
医師の意見を聞き従業員の働き方を精査する
労働安全衛生法第66条の4にもとづき、健康診断の結果、従業員に異常所見が見られた場合、企業は3ヵ月以内に医師の意見を聞く必要があります。医師の意見をもとに、就業場所の変更や作業転換、労働時間の短縮など、従業員の健康状態に応じた適切な措置を講じることが重要です。
【参照】厚生労働省 東京労働局「健康診断による健康管理を進めましょう」|厚生労働省
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_kenshin_0001.html
健康診断の受診率向上で健康経営を推進しよう
健康診断の受診率向上は、企業が健康経営を推進する上で不可欠な取り組みです。企業にとって、健康診断の実施は法的義務であるだけでなく、従業員の健康リスクを早期発見し、予防につなげる重要な施策でもあります。
また、健康経営優良法人の認定基準にも「健康診断の受診率実質100%」が評価基準のひとつとなっており、企業のブランド価値向上や人材確保の観点からも、受診率向上に取り組む意義は大きいといえます。外部の健診サービスなどを賢く活用しながら、健康診断の受診率を上げ、健康経営の実現に向けて取り組みましょう。
「マイナビ健康経営」は、人と組織の「ウェルネス(健康)」をさまざまなサービスでサポートしています。健康診断の受診率向上に関する取り組みについても、お気軽にご相談ください。
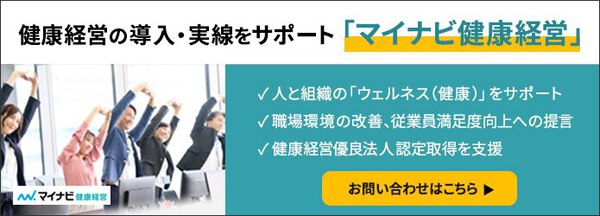
【免責及びご注意】 |
<監修者> |
&res=1280x720&is_new_uid=true&_tcuid=202504041432288020&_tcsid=202504041432282828)