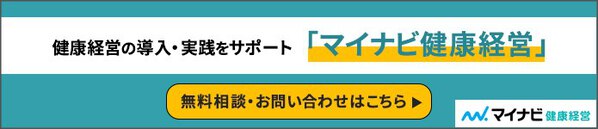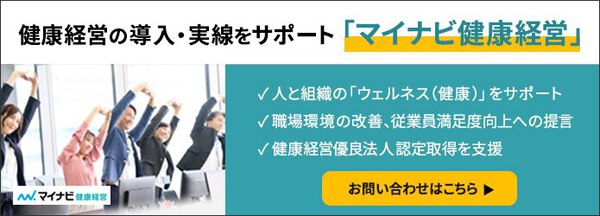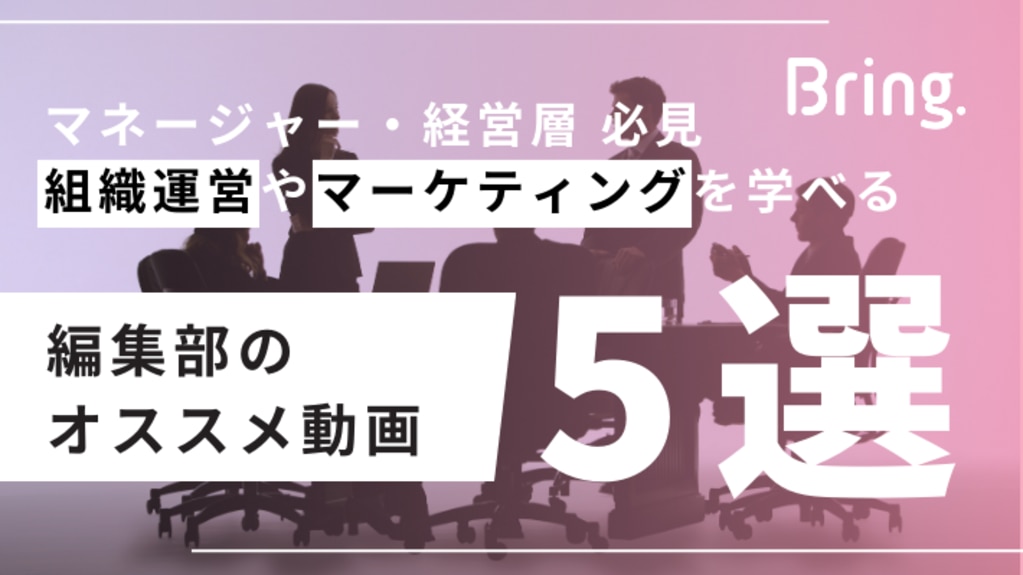コラボヘルスとは?導入ステップや成功のポイント、成功事例を紹介
健康経営に取り組む企業は年々増加しています。全社方針として健康経営の推進を明文化する企業や、経営トップが責任者として健康経営のかじ取りをする企業も目立つようになりました。
こうした現状を受け、企業がより効率的・効果的に健康経営を推進する方法のひとつとして、保険者と連携して従業員やその家族の健康づくりに取り組む「コラボヘルス」が注目されています。
本記事では、コラボヘルスの概要や導入の方法、導入することによるメリットなどについて詳しく解説します。
【参照】経済産業省「健康経営」|経済産業省(2024年3月)
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_keiei.html
目次[非表示]
- 1.コラボヘルスとは、企業と保険者が連携して従業員の健康管理を支援すること
- 2.コラボヘルスの仕組み
- 3.コラボヘルスが生まれた背景
- 4.コラボヘルスのメリット
- 4.1.保険者におけるコラボヘルスのメリット:保健事業の推進がよりスムーズになる
- 4.2.企業におけるコラボヘルスのメリット:健康経営を効率的に推進できる
- 4.3.従業員におけるコラボヘルスのメリット:疾病リスクの早期発見や、予防・改善につながる
- 5.コラボヘルス導入の基本ステップ
- 6.コラボヘルスを成功させるポイント
- 7.コラボヘルスを推進している健保組合と企業の事例
- 7.1.SCSK健康保険組合の事例:企業トップの強力なリーダーシップによって保健事業の参加率を向上
- 7.2.花王健康保険組合の事例:健保組合と事業主とが一体でコラボヘルスを推進
- 7.3.パナソニック健康保険組合の事例:事業主、労働組合、健保組合の三位一体でコラボヘルスを推進
- 8.コラボヘルスの今後の展望
- 9.コラボヘルスは、健康経営の推進に不可欠な取り組みです
コラボヘルスとは、企業と保険者が連携して従業員の健康管理を支援すること
厚生労働省は、コラボヘルスを下記のように定義しています。
「コラボヘルスとは、健康保険組合等の保険者と事業主(企業)が積極的に連携し、明確な役割分担と良好な職場環境のもと、加入者(従業員、およびその家族)の予防・健康づくりを効果的に実行することです。」
保険者は、これまでの保険事業において、加入者の健康データを蓄積してきました。このデータを活用すれば、従業員一人ひとりにカスタマイズした保健指導や効果的な予防・健康づくりを提供することが期待できます。これは、厚生労働省も推奨してきた「データヘルス」と呼ばれる取り組みです。
他方、高齢化による従業員の健康リスク増大、労働生産性の低下、自身の病気や家族の介護などと両立しながら働く人の増加といった変化にさらされている事業主側にとっては、「健康を害したら休ませる」のではなく「病気にならない体づくりを支える」ための健康投資が喫緊の課題です。
そのため、データヘルスを中心とした取り組みを保険者が進め、それを受けた事業主側が職場環境を整備する連携が求められてきています。両者が連携を強めれば、保険者は保険者としての機能を強化し、企業は健康経営を効率的に進めることができるでしょう。事業主が保険者の活動の意義を十分に理解して従業員を啓発することで、保険者が企画立案した事業が成り立つという図式も成り立ちます。
こうした相乗効果により、データヘルス、健康経営ともに実効性が高まり、医療費の適正化や従業員の生産性向上、保険事業の円滑な実施といった好影響につながることが期待できます。
【参照】厚生労働省保険局「データヘルス・健康経営を推進するためのコラボヘルスガイドライン」|厚生労働省(2017年7月)
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000171483.pdf
コラボヘルスの仕組み
コラボヘルスは、健康保険組合が持つデータヘルスと、企業に蓄積された労務データや健康診断データを共有・分析し、従業員一人ひとりに適切な健康サポートを提供していく仕組みです。
具体的には、健康診断結果にもとづく再診の推奨や、パーソナライズされた運動・食事の提案といった予防・治療プログラムの実施などが挙げられます。
コラボヘルスが生まれた背景
コラボヘルスが生まれた背景には、少子高齢化による医療費の増加、生活習慣病の増加といった社会的な問題があります。日本は超高齢社会を迎えており、企業で働く従業員の平均年齢は上がり、生活習慣病などの疾病リスクを抱えながら働く人も増えました。
そこで保険者に求められるようになったのが、加入者の健康増進を図り、予防医療を推進することによって医療費を抑制することです。
一方、いずれくる深刻な労働者不足に備えなければならない企業も、貴重な従業員の健康を守り、一人ひとりが長くいきいきと働ける体づくりをフォローしていく必要があります。
保険者には、長年の取り組みによって蓄積された健康づくりのノウハウや医療データがあり、企業は保険者の運営を助ける人材や資源を有しています。保険者と企業が一体となって健康増進に取り組めば、より効率的に効果が期待できるという考え方にもとづき、生まれたのがコラボヘルスです。少子高齢化と労働人口の減少、医療費の増大といった社会課題の対策になる取り組みとして今、コラボヘルスに関心が高まっています。
コラボヘルスのメリット
コラボヘルスの推進は、保険者、企業、従業員の3者にメリットをもたらします。それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
保険者におけるコラボヘルスのメリット:保健事業の推進がよりスムーズになる
保険者にとってのコラボヘルスのメリットは、事業者の協力が得られることによって、保健事業がスムーズに推進できるようになることです。例えば、下記のような効果が期待できます。
<保険者にもたらされるメリット例>
- 健康診断をはじめとした保健事業への参加を企業から従業員に呼びかけてもらうことにより、参加率が上がる
- 事業主が保有する従業員の労務情報をデータヘルスに取り込み、より個別最適化された健康づくりの提案ができるようになる
- 事業主と財源や人的資源を共有することによって、人手不足・資金不足を補うことができる
企業におけるコラボヘルスのメリット:健康経営を効率的に推進できる
企業にとってのコラボヘルスのメリットは、これまでの保健事業において蓄積されたデータを活用することにより、健康経営を効率的に推進できることです。
また、従業員の健康状態が向上することで、労働生産性や従業員の定着率の向上も期待できます。さらには従業員の健康を第一に考えている企業として、企業のブランディングにも好影響をもたらすでしょう。
従業員におけるコラボヘルスのメリット:疾病リスクの早期発見や、予防・改善につながる
コラボヘルスの実施は、従業員にもメリットがあります。
これまで健康に無頓着だった人も、就業先からの働きかけがあれば健康維持・増進に取り組むようになるでしょう。そうした働きかけは、生活習慣病をはじめとした疾病リスクの早期発見や、予防・改善につながるはずです。また、ストレス対策プログラムやメンタルヘルスサポートなども実施すると、身体面のみならず精神面においても健康的になることが期待できます。
【おすすめ参考記事】
コラボヘルス導入の基本ステップ
ここからは、コラボヘルスを導入する際のステップを押さえていきましょう。基本的な4つのステップを紹介します。
1.コラボヘルスの推進体制を整備する
まずは、コラボヘルスを推進する体制を整備しましょう。
コラボヘルス推進の担当者を中心に、経営陣、人事・総務、保険者、労働組合などが関与する横串のプロジェクトをつくります。できれば経営層直下の組織にして、強力な意思決定のもとで活動を推進できる体制を構築することが重要です。
産業医や保健師など、専門知識を持った第三者の関与があると、施策がより充実していきます。
2.「健康白書」で健康情報を可視化する
企業が所有するデータと保険者が所有するデータを合わせて、既存事業の実施下における従業員の健康状況を可視化する健康白書をつくります。健康白書を作成すれば、内部で情報を共有できるだけでなく、健康経営に関する取り組みを外部に発信することもできます。
3.コラボヘルスにおける目標・計画を立案する
事業主と保険者でコラボヘルスにおける共通の目標を立てます。例えば、保険者は「医療費削減」、事業主は「健康経営」とそれぞれ最終的な目的が異なることを理解した上で、「喫煙率の減少」や「健康診断の受診率向上」など、双方の目標の過程で共通する指標を模索しましょう。
コラボヘルスを成功させるポイント
コラボヘルスを成功させるには、押さえておくべきポイントもあります。下記のポイントを意識して活動を推進することが大切です。
健康意識を高めるための社内キャンペーンや教育を行う
保険者が充実した施策を立案し、事業者が従業員に参加を推奨しても、従業員の健康に対する意識が低いままではコラボヘルスの成功は困難となるでしょう。
まずは、健康に働くことの大切さや、健康を維持することによって得られるメリットなどについて、社内に周知するための教育やキャンペーンを展開することをおすすめします。「健康で、仕事もプライベートも楽しめる自分でいたい」「もっと動ける体を手に入れたい」といった意識を高めてからコラボヘルスを行うと、健康プログラムなどへの参加率の向上や、参加者のモチベーションアップが見込めます。
データを活用した継続的なモニタリングと改善を行う
コラボヘルスは継続性が重要です。事業を実施した後は必ずデータを確認し、継続的にモニタリングを実施しましょう。結果が思わしくない事業については、早期に改善策を検討してPDCAサイクルを回すことも大切です。
コラボヘルスを推進している健保組合と企業の事例
ここでは、コラボヘルスを実践している企業と保険者の事例をご紹介します。どのような体制づくりや施策が効果を発揮するのか、具体的に見ていきます。
SCSK健康保険組合の事例:企業トップの強力なリーダーシップによって保健事業の参加率を向上
SCSK健康保険組合は、母体企業のSCSK株式会社と連携し、従業員の健康増進改善を行ってきました。
2012年度に同健保組合が実施した特定健診で、受診者のうちの2割がメタボリックシンドロームのリスク数に応じて保健指導が入る「動機付け支援」や「積極的支援」に該当していることが判明。また、これらの対象者のうち運動習慣のない人が8割近く、喫煙習慣がある人が3割弱いることもわかりました。それをきっかけに、同健保組合は抜本的な改善策を模索し、過去に従業員の健康増進で大きな成果を出すなど、10年連続で「健康経営銘柄」に選定されているSCSK株式会社に連携を要請しました。
その結果、会社がいかに従業員の健康を大切に考えているかを綴った社長からの手紙を被保険者(従業員)に送る、禁煙成功者に5万円相当の福利厚生ポイントを提供するなど、事業主側からの強力な支援を受けることに成功。禁煙キャンペーンや、ウォーキングキャンペーンといった健康施策においても従業員の高い参加率を達成しました。
今後も取り組みを継続して定着化を図り、役職者や従業員だけではなくその家族にまで波及させていくことを見据えています。
【参照】厚生労働省「被用者保険におけるデータ分析に基づく保健事業事例集(データヘルス事例集)」|厚生労働省(2013年9月)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/dl/jirei24.pdf
【参照】【参照】厚生労働省保険局「データヘルス・健康経営を推進するためのコラボヘルスガイドライン」|厚生労働省(2017年7月)
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000171483.pdf
【参照】全国健康保険協会「健診後の保健指導・健康相談」|全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat420/r36/
花王健康保険組合の事例:健保組合と事業主とが一体でコラボヘルスを推進
花王健康保険組合は、花王株式会社と連携して被保険者の健康づくりをするコラボヘルスをかねてより展開してきました。これは、健保組合と事業主が一体となって活動することにより、被保険者の健康づくりへの参加意識が高まることを重視したためです。
このコラボヘルスの大きな特徴はデータの有効活用です。健保組合の持つ疾病データ、医療費データと事業主の持つ健診データ、問診データ、就業データなどを集約し、会社や事業所別、男女別、年齢階層別、職種別などに編集して各地の保健スタッフに提供しています。また、データの着眼点や事業計画立案の訓練のために「白書勉強会」といった集合研修も実施しています。
【参照】厚生労働省「被用者保険におけるデータ分析に基づく保健事業事例集(データヘルス事例集)」|厚生労働省(2013年9月)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/dl/jirei23.pdf
パナソニック健康保険組合の事例:事業主、労働組合、健保組合の三位一体でコラボヘルスを推進
パナソニックグループは、グループ全体の職場の健康づくり運動「健康パナソニック21」を、事業主、労働組合、健保組合の三位一体で2001年度から推進しています。
「健康パナソニック21」は、それぞれの役員による推進委員会を組織した上で、3者から実務責任者が出て推進タスクフォースを構成。これも3者のスタッフによる事業所安全衛生委員会を立ち上げて活動することで、共通課題を共有しながら着実に成果を出しています。
同グループのコラボヘルスは、2011年度から健康づくりの対象を従業員の家庭にまで広げており、従業員の家族の健診受診や家庭での健康づくりにもつとめている点が特徴です。2024年度から名称を新たにし、スタートした「健康パナソニック」では、ライフステージに応じた将来を見据えた「健康への自己投資」を推進中。食環境や喫煙環境の改善活動を展開しています。
【参照】厚生労働省「被用者保険におけるデータ分析に基づく保健事業事例集(データヘルス事例集)」|厚生労働省(2013年9月)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/dl/jirei26.pdf
【参照】パナソニック健康保険組合「健康パナソニック」|パナソニック健康保険組合
https://phio.panasonic.co.jp/health/kenpana/index.html
コラボヘルスの今後の展望
超高齢社会の日本において、コラボヘルスはこれから一層、重要視されていくと見られます。今後、医療制度や社会保険制度の改革が進み、医療データの利活用が推進されれば、より高精度な健康状態の把握が可能となり、パーソナライズされた健康増進プログラムや予防策の提案に反映されていくはずです。
また、予防医療や健康管理のデジタル化もコラボヘルス拡大の一翼を担うと考えられます。
AIのほか、あらゆるモノがインターネットに接続される仕組みである「IoT(Internet of Things)」などのテクノロジーを活用した予防医療サービスの開発に取り組む民間企業も増加中です。すでに一部の医療機関では、AIを搭載した画像診断システムが医師や放射線技師の診断をサポートし、病気の早期発見・予防に寄与しています。
これから先、デジタル技術を最大限に利用して、生活習慣病のリスクがある人に食生活や運動習慣の注意喚起をしたり、行動変容を促したりすることが日常となっていくでしょう。
コラボヘルスは、健康経営の推進に不可欠な取り組みです
豊富なノウハウとデータを持つ保険者と、従業員に対する指揮系統を持つ事業者とが協力して健康づくりを推進するコラボヘルスは、企業の生産性向上と持続可能な社会の成長を実現するために不可欠な取り組みです。
健康経営施策と連携することで、少子高齢化による労働力不足など、日本社会が抱える課題を解決していく可能性もあります。人事や経営層をはじめとした企業の責任者はこれから先、医療や健康の専門家の協力を得ながら、より良いコラボヘルスを目指していくことが一層求められていくでしょう。
「マイナビ健康経営」は、人と組織の「ウェルネス(健康)」をさまざまなサービスでサポートしています。健康経営やコラボヘルスにおける有用な施策などについても、お気軽にご相談ください。
&res=1280x720&is_new_uid=true&_tcuid=202504040821125696&_tcsid=202504040821126634)