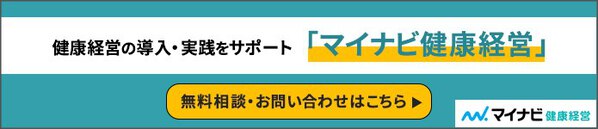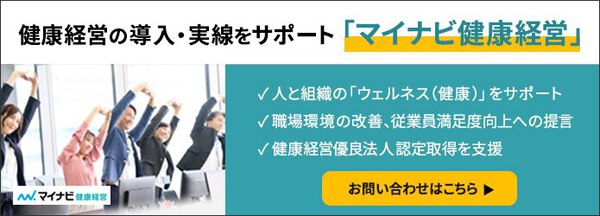ドナー休暇制度とは?企業における重要性と制度の仕組みを詳しく解説
ドナーとは、臓器や骨髄、血液などの提供者のことを指します。昨今、骨髄バンクに登録しているドナーが実際にドナー候補となった際、移植のために必要な通院・入院を気兼ねなく行えるよう、「ドナー休暇制度」を設ける企業が増えてきました。
経済産業省の「令和5年度 健康経営度調査」においても、「休暇の取得促進」の項目のひとつとして骨髄等移植のドナー休暇制度等を設置しているか否かが問われており、健康経営の側面からも注目すべき制度であることがわかります。
本記事では、ドナー休暇制度が企業と個人にどのような価値をもたらすのかを詳しく解説。実際に、骨髄移植などを行う際のスケジュールや、ドナー休暇制度を導入するメリット、ドナー休暇制度導入・取得における課題なども具体的に紹介していきます。
【参照】経済産業省「令和5年度 健康経営度調査(従業員の健康に関する取り組みについての調査)」|経済産業省
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/kenko_iryo/kenko_toshi/pdf/009_s02_00.pdf
目次[非表示]
ドナー休暇制度とは、骨髄や末梢血幹細胞の提供にあたって取得できる特別休暇のこと
ドナー休暇制度とは、骨髄バンクを通じて骨髄や末梢血幹細胞を提供する際に取得できる特別休暇(法定外休暇)のことです。
血液疾患に苦しむ人にとって、HLA(白血球の型)が一致するドナー候補からの末梢血幹細胞の提供は希望の光です。しかし、HLAは両親から半分ずつ遺伝するため、血縁関係があっても一致する確率は低く、血縁関係のない人に至っては数百から数万分の1の確率でしか一致しません。
そこで重要なのが、ドナー登録を促進し、ドナー候補の母数を増やすことです。骨髄等の提供は54歳以下まで可能ですが、年齢が上がるほど健康リスクによって提供が叶わないケースが多いことから、若年層の登録者を増やす必要があります。
しかし、奇跡的にHLAが一致したドナー登録者がドナー候補となり、骨髄や末梢血幹細胞を提供するためには、日中に10回前後、医療施設にて検査や入院をする必要があります。このことがハードルとなり、HLAが一致したにもかかわらず提供をあきらめる人が少なくないのです。
ドナー休暇制度は、善意の協力者であるドナー登録者が心理的、肉体的に負担なく休暇を取れるよう、日本骨髄バンクが普及を進める取り組みです。企業が認める「特別休暇」を使って休める環境を整えることで、ドナーとなる人は堂々と社会貢献活動をすることができます。
【参照】JMDP日本骨髄バンク「提供までのながれ」|JMDP日本骨髄バンク
https://www.jmdp.or.jp/donation/flow/about/
ドナー休暇制度の整備に必要なこと
ドナー休暇制度は、法定休暇ではないため、制度を設ける際には、企業が就業規則に内容を盛り込み、従業員への周知と労働基準監督署へ届け出ることが必要です。休暇日数の上限や取得方法は企業によって異なります。一般的には、5~10日程度が休暇日数の目安となるでしょう。
ドナーは、説明や採血、入院などでの休みであることを証明する書類をもらい、勤め先に提出します。コーディネート前には「予定通知」を、終了後には「証明書」が発行されるため、企業の規定に応じて提出します。
【参照】厚生労働省「ドナー休暇制度」|厚生労働省(2019年11月)
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category4/20191122_3.pdf
【参照】JMDP日本骨髄バンク「ドナー登録に来られたことを証明する書類」|JMDP日本骨髄バンク
https://www.jmdp.or.jp/donation/donorsupport/certificate.html
ドナー休暇制度の導入・取得における課題
ドナー休暇制度の導入や、導入後の取得に際しては企業が直面する課題もあります。ドナー休暇制度導入・取得における主な課題は下記の3点です。
自社の人手不足
深刻な人手不足に悩む中小企業の中には、「ドナー休暇制度を導入したい気持ちはあるが、1人でも休まれると仕事が回らない」というジレンマもあるでしょう。特にドナー休暇は取得日数が多く、期間も長期にわたるため、躊躇する企業も多いと見られます。
しかしドナー休暇制度の導入は、長期的に企業価値を高める取り組みです。ドナー休暇制度の導入は人材採用にも効果があると捉え、新規採用や業務効率化と並行して推進していくことが大切です。
従業員の理解不足
ドナー休暇制度の導入後は、従業員が遠慮なく休暇を申請できるような風土を醸成していくことが求められます。
骨髄バンクの活動や移植の必要性などに対する理解度が従業員によって異なると、休暇取得の障壁となる可能性があるからです。
ドナー休暇制度を導入した際は、制度の目的や意義を社内に説明する機会は必ず設けるようにしましょう。さらに、休暇を申請した仲間を尊敬し、応援するといった雰囲気づくりの醸成も必要です。
体調管理維持や経済的負担の大きさ
ドナーとして登録した後は、適合者が現れるまで移植に適した健康な心身を維持する必要があります。ドナー提供の連絡がきたタイミングで体調が思わしくなければ、移植をすることはできません。病気やケガの治療の最中である場合、意思に反して断念せざるをえないこともあるでしょう。
また、ドナー休暇は法定外休暇であり、有給か無給かは企業の判断に委ねられます。無給の場合、休暇が増えることで給与が減ってしまうことを負担に感じる人もいるかもしれません。しかし自治体によっては、骨髄移植や末梢血幹細胞のドナーや、ドナー休暇制度を導入している企業に助成金を交付しているケースもあります。企業の担当者はドナー休暇制度を作る前に一度調べてみることをおすすめします。
【参照】JMDP日本骨髄バンク「自治体・民間団体による助成制度」JMDP日本骨髄バンク
https://www.jmdp.or.jp/donation/donorsupport/assistance.html
骨髄や末梢血幹細胞を提供するまでの流れ
ここからは、ドナーに選ばれてから骨髄・末梢血幹細胞を提供するまでの流れを見ていきましょう。
ドナー登録後、HLAが適合する患者が見つかると、「ドナー候補となった」ことの通知が届きます。対象者はその内容を確認したら、提供意思や家族の意向、日程、健康状態などを骨髄バンクに返信します。
その後、コーディネーターや医師からの説明に問題がなければ、病院で採血を実施。採血結果にもとづき、最も移植にふさわしいと医学的に判断された人がドナーに選ばれます。骨髄提供になるか、末梢血幹細胞の提供になるかはこのときに決まります。骨髄提供か末梢血幹細胞の提供が決まった後のスケジュール例は、下記のとおりです。
<骨髄提供の場合のスケジュール例>
骨髄提供日の1~3週間前に、自己血輸血のための採血を行います。採取日の1~2日前になったら健康チェックのために入院し、骨髄の採取を待ちます。入院期間は通常3~4日ほどです。
<末梢血幹細胞提供の場合のスケジュール例>
3~4日ほどの通院、または入院をして、白血球を増やす薬を注射します。末梢血幹細胞を採取するタイミングは、白血球を増やす薬を注射してから4~5日目です。
入院で注射をする場合は4泊5日~6泊7日、通院の場合は2~4日通院し、さらに1泊2日~3泊4日ほどの入院期間が必要となります。
【参照】JMDP日本骨髄バンク「ドナーのためのハンドブック」|JMDP日本骨髄バンク(2023年9月)
https://www.jmdp.or.jp/donation/handbook/
ドナー登録の対象者
ドナー登録できるのは、下記の条件に該当する人です。
<ドナー登録の条件例>
- 骨髄・末梢血幹細胞の提供内容を十分に理解している人
- 年齢が18歳以上、54歳以下で健康状態が良好な人
- 体重が男性45kg以上/女性40kg以上の人
ただし、上記の条件を満たしていても、登録後の健康状態や過去の病歴、飲んでいる薬などによってはドナーになることができません。また、登録していても提供者にならなかった場合、満55歳の誕生日で登録が取り消されます。
なお、骨髄・末梢血幹細胞を提供するには、本人だけでなく家族の同意も必要です。
ドナー登録ができない人
ドナー登録は、登録の条件をクリアしていても、誰しもがなれるものではありません。下記に該当する方は、ドナー登録をすることは難しいでしょう。
病気やケガなどの治療中、または処方薬使用中の人
高血圧に対する降圧剤や慢性疾患治療を目的とした服薬、精神疾患治療やケガの治療のための服薬・通院といった、治療や服薬が一過性でない場合。
下記の病歴がある人
悪性腫瘍(がん)、白血病、再生不良性貧血などの血液の病気、膠原病(慢性関節リウマチなど)、自己免疫疾患、先天性心疾患、心筋梗塞、狭心症などの循環器疾患、脳卒中、C型肝炎など一部のウイルス肝炎、エイズ、マラリアなどの感染症といった病歴。
血圧が高い、または低い人
最高血圧151mmHg以上/最低血圧101mmHg以上、または最高血圧が90mmHg未満の人。
<その他のドナー登録ができない条件>
- 輸血を受けたことがある人
- 貧血の人
- 食事や薬等により呼吸困難などの症状が出たことがある人や、高度の発疹の既往がある人
- 過度の肥満(体重kg÷身長m÷身長mが30以上の人)
- 妊娠中および出産後1年未満の人、授乳中の人
- 腰の手術を受けたことがある人
【参照】JMDP日本骨髄バンク「ドナーのためのハンドブック」|JMDP日本骨髄バンク(2023年9月)
https://www.jmdp.or.jp/donation/handbook/
【参照】JMDP日本骨髄バンク「ドナー登録できる方の条件」|JMDP日本骨髄バンク
https://www.jmdp.or.jp/reg/requirement/
ドナー休暇制度を導入するメリット
ドナー休暇制度を導入すると、企業にはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、3つのメリットを紹介します。
従業員がドナー活動に専念でき、エンゲージメント向上も期待できる
会社がドナー休暇制度を導入してサポートすれば、従業員はドナーとしての活動に心置きなく集中することができます。
骨髄バンクを介して移植を必要とする患者は、毎年2,000人近くに上ります。対して、骨髄バンクのドナー登録者数は約54万人(2023年3月末時点)ですが、移植に至る件数は希望者の半数にすぎません。
ドナー登録をしている従業員にとって、HLAが一致したにもかかわらず「仕事を休めない」という理由で断らざるをえなくなれば、その無念さは計り知れないでしょう。一方、ドナー休暇制度が充実している会社であれば、従業員の真摯な思いを受け止める企業であることが伝わります。その結果、会社への思い入れである従業員エンゲージメントの向上も期待できます。
【参照】政府広報オンライン「命をつなぐ骨髄バンク あなたのドナー登録を待っている人がいます」|政府広報オンライン(2024年10月)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/6.html
社会的貢献が認められ、企業のイメージが向上する
利益第一主義による不祥事の報道が後を絶たない現在、企業には事業活動を通じて社会的責任を果たすことが求められるようになりました。自社の利益のみならず、社会や環境と調和しながら持続的に成長していくことは、今の時代の企業に必要なことです。
従業員一人ひとりの社会貢献活動を支えるドナー休暇制度は、企業のCSR(社会的責任)として高く評価される取り組みです。企業イメージを良くする効果もあり、ステークホルダーや求職者からの自社への信頼が高まることも期待できます。
骨髄バンクの活動促進に貢献できる
骨髄バンク事業は、白血病などの血液疾患で移植を待つ患者と、健康な末梢血幹細胞を提供する意思があるドナーを結びつける公的事業です。1992年の開始以来、血液の病気に苦しむ多くの患者とその家族を救ってきました。
しかし、現在のドナー登録者はほとんどが40~50代で、遠くない未来に登録者数が減少していくことが危惧されています。そこで自社の従業員が骨髄バンクのドナーとして登録すれば、多くの命を救う骨髄バンクの活動促進に貢献することができます。
【参照】JMDP日本骨髄バンク「あなたにしか救えないいのちがあります。」|JMDP日本骨髄バンク(2024年10月)
https://www.jmdp.or.jp/
【参照】政府広報オンライン「命をつなぐ骨髄バンク あなたのドナー登録を待っている人がいます」|政府広報オンライン(2024年10月)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/6.html
ドナー休暇制度導入企業の事例現状
最後に、ドナー休暇制度を導入している企業の事例をご紹介します。各企業は実際にどのような休暇制度を設けているのか具体的に見ていきましょう。
スパイスファクトリー株式会社の事例:有給休暇とは異なる特別休暇を付与
デジタル・インテグレーション事業のスパイスファクトリー株式会社は、従業員の声をもとに、命をつなぐ機会を後押しするドナー休暇制度に注目。社会貢献性が高い活動に励む意思のある従業員をサポートすることは企業の責任であるとして、有給休暇とは異なる特別休暇を最大5日間付与するドナー休暇制度を制定しました。
【参照】スパイスファクトリー株式会社「社会貢献を重視するIT企業として特別休暇を付与しドナー不足の社会課題に取り組む」|スパイスファクトリー株式会社(2024年6月)
https://spice-factory.co.jp/news/17706/
株式会社ツムラの事例:ドナー登録から入院後の健康診断までにかかる日を有給休暇に制定
医薬品を製造販売する株式会社ツムラは、原則年14日まで有給取得が可能な骨髄ドナー休暇を制定しています。同社の骨髄ドナー休暇は、骨髄バンクへのドナー登録から入院後の健康診断までにかかる日が対象です。入院日数が増えるなど、やむを得ず休暇が14日を超える場合でも、会社が認めれば14日を超えた日数も休暇として認められる点が特徴です。
【参照】厚生労働省「特別な休暇制度導入事例 一覧」|厚生労働省(2023年3月)
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/pdf/233.pdf
株式会社イオンファンタジーの事例:取得可能な休暇日数に上限のないドナー休暇を導入
ショッピングセンター内のアミューズメント施設や、プレイグラウンドの運営を行っている株式会社イオンファンタジーは、2022年7月にドナー休暇を導入。かつてドナーの経験をした従業員からの「ドナー休暇があればよかった」という声をきっかけとして制度が導入されました。同社のドナー休暇は、取得可能な休暇日数に上限がなく、ドナー提供に必要な日数を有給休暇として取得できる点が特徴です。
【参照】厚生労働省「特別な休暇制度導入事例 一覧」|厚生労働省(2023年2月)
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/pdf/225.pdf
ドナー休暇制度は、社会課題解決を促進する企業のCSR活動
ドナー休暇は、命を救う活動に取り組む従業員を支援し、骨髄バンクの活動を守る制度です。日本における導入企業・団体は855社(2024年8月時点)ですが、企業と従業員の双方にメリットがある取り組みとして、今後ますます導入は進んでいくでしょう。
健康経営推進の一助として、またCSR活動のひとつとして、ドナー休暇制度の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
「マイナビ健康経営」は、人と組織の「ウェルネス(健康)」をさまざまなサービスでサポートしています。ドナー休暇制度導入の課題などについても、お気軽にご相談ください。
【参照】JMDP日本骨髄バンク「ドナー休暇・公欠制度」JMDP日本骨髄バンク(2024年8月)
https://www.jmdp.or.jp/donation/donorsupport/donorleave.html
<監修者> |
【免責及びご注意】 |
&res=1280x720&is_new_uid=true&_tcuid=202504040612509074&_tcsid=202504040612508119)