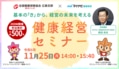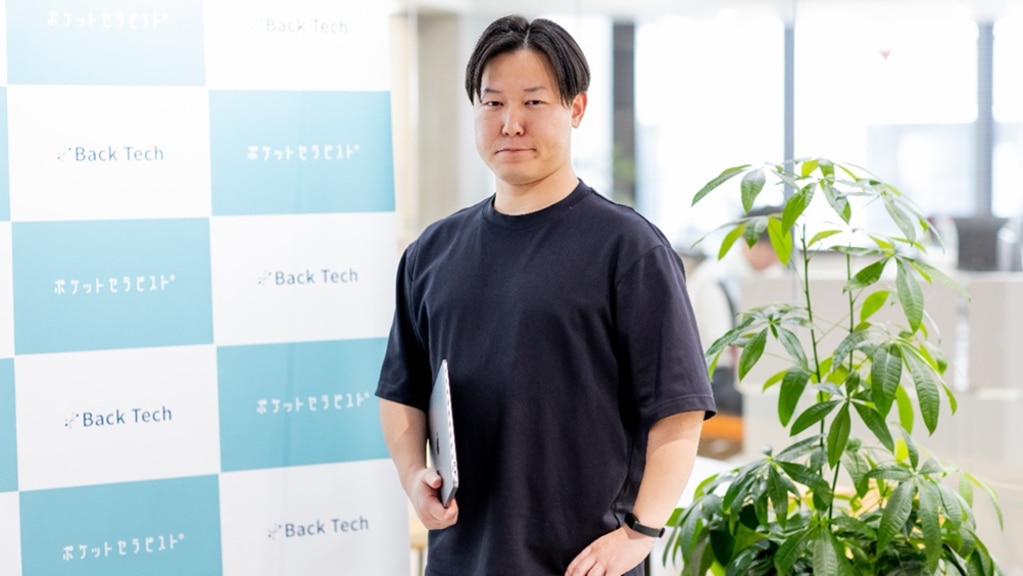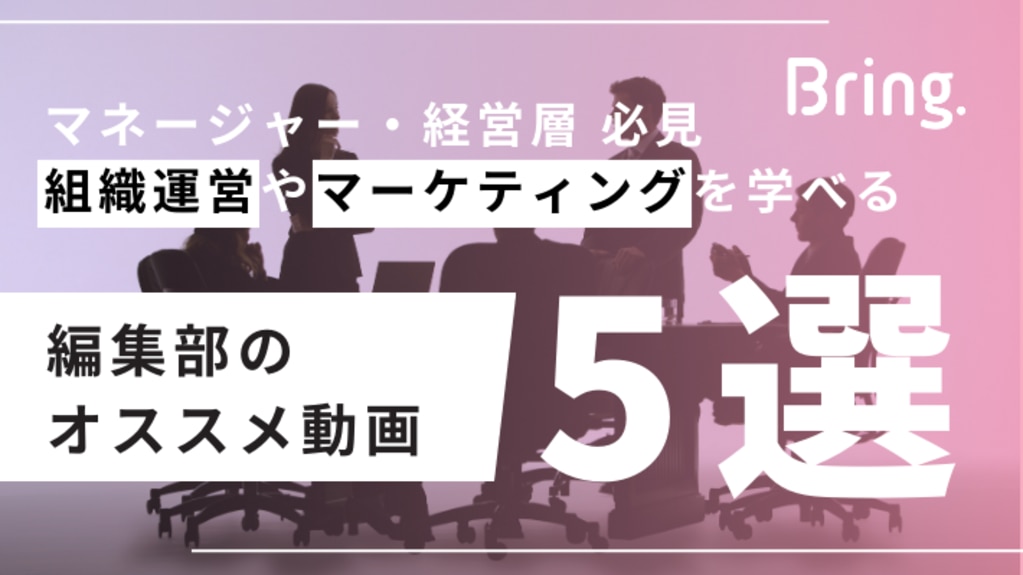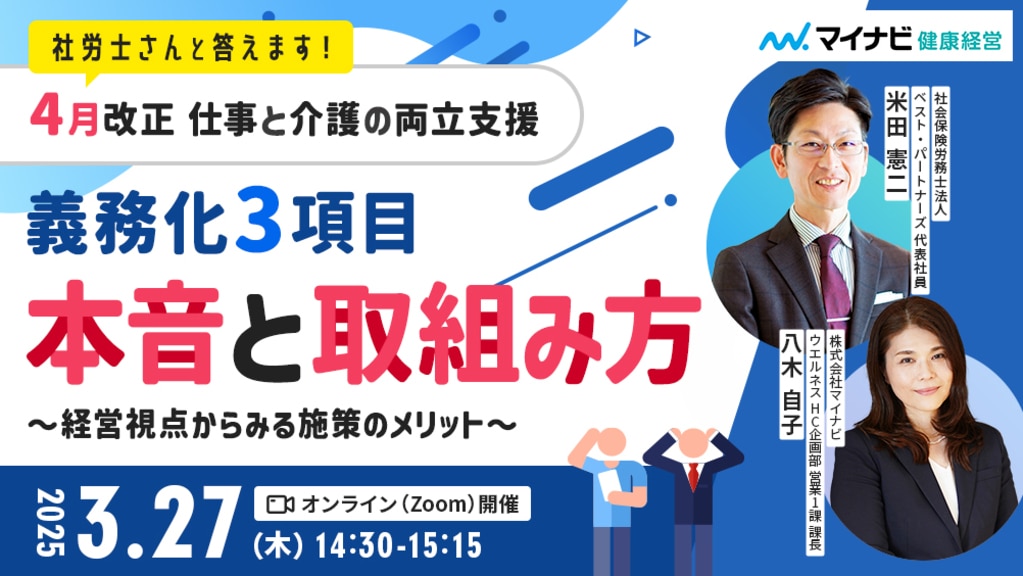主体性重視の健康推進策で「健康応援企業」へと進化するSOMPOひまわり生命
撮影/和知 明(株式会社BrightEN photo) |
2016年に新たなビジョン「健康応援企業」を掲げ、その実現に向け健康経営へ注力してきたSOMPOひまわり生命保険株式会社。「健康経営優良法人 大規模法人部門(ホワイト500)」に8年連続で認定されるなど、その取り組みは社外からも高く評価されています。同社の健康経営への思い、そして具体的な施策内容や推進のポイントについて、野田美智子さん(執行役員 CHRO 人財開発部長)に伺いました。

野田 美智子(のだ・みちこ) SOMPOひまわり生命保険株式会社 執行役員 CHRO 人財開発部長。 |
目次[非表示]
インシュアヘルスの提唱と健康経営の関係
伝統的な生命保険会社の在り方に加え、「健康応援企業」への変革を遂げたい――。この思いこそが、当社で健康経営を推進するきっかけになりました。そもそも生命保険は、人生における「万が一」をサポートする存在。それに加えて当社では、「万が一」を可能な限りなくしたり後ろ倒ししたりすることでも、お客さまの人生を応援したいと考えたのです。保険本来の機能(Insurance)に、健康を応援する機能(Healthcare)を組み合わせたInsurhealth®(インシュアヘルス)を提唱しようと2016年に舵を切り、インシュアヘルス商品のご提案を始めました。
健康応援企業として新たな価値を提供するためには、その原動力となる社員や家族が健康であることも大切です。健やかで仕事へ打ち込める状態でなければ、お客さまを全力で応援し、健康の価値を伝えることが難しくなってきます。そこで当社では、上記の舵切りに合わせて健康経営を積極的に推進。人的資本経営を支える大切な「基盤」として注力してきました。健康診断などの結果を分析して課題を特定し、それを解決できるような取り組みを継続的に実施する他、定期的に目玉となるような施策を取り入れていることも特徴です。
例えば、2016年から導入しているのがウェアラブル端末です。全社員へ1万円相当のウェアラブル端末を無償貸与し、各々の健康に関するデータを「見える化」できる環境を整えました。特に、社会人が課題を抱えやすい運動不足の解消に有用だったようで、「毎日の歩数が増えてダイエットにつながった」といった声が上がっています。社内外で定期的に歩数対抗戦も開催しており、約70%の社員が参加しています。
また2023年には、社員を対象にした健康に関するアンケートをもとに「SOMPOひまわり体操」を考案。腰痛、肩こり、筋力不足といった悩みが多かったことから、それらを解消できるような動きを取り入れ、オリジナルの体操としてまとめたものです。毎月のミーティングやイベントで実施する他、個人で取り組む社員も少なくありません。
そして、2016年から段階的に取り組みを強化してきたのが、禁煙です。当初の喫煙率は20%を超える状態でしたが、丁寧な個別フォローや非喫煙者の積極的な採用などを背景に、2023年度には6.9%まで減少しました。禁煙に向けた施策を、その意思がない人に推奨することは容易ではありません。「いきなり明日から全面禁煙」といった急進的なやり方では実現性が低いので、バランス感覚を持って進めることが肝心です。当社の場合は、まず部門長クラス以上から就業時間内禁煙を徹底し、その後に全社員へ広めていくといったように、段階を踏むことを意識しました。徐々に禁煙の意義を知ってもらうことで、「自分もやってみようかな」と考える猶予期間を設けた点がポイントです。
<健康経営KPI数値項目>
 【画像引用】SOMPO ひまわり生命「健康経営」- 実績・効果 KPIの取組み状況 <健康経営KPI数値項目>
【画像引用】SOMPO ひまわり生命「健康経営」- 実績・効果 KPIの取組み状況 <健康経営KPI数値項目>
https://www.himawari-life.co.jp/company/kenko/
自由度の高い学びでヘルスリテラシーを向上
健康経営の専門部署を設けていることも、当社の本気度の表れと言えるかもしれません。2020年に人財開発部内で発足した「健康経営グループ」です。グループ長の橋本友紀さん(健康経営エキスパートアドバイザー)を筆頭に、5人のメンバーが健康経営に専念して業務に当たっています。いわゆる産業保健スタッフではなく、営業職経験者やグループ会社からの出向者など、多様性のある面々がさまざまな知見を持ち寄っている点が特徴です。この健康経営グループが中心となり、SOMPOグループ各社や健康保険組合とも連携しつつ、全社を挙げて取り組みを進めているわけです。
 健康経営の具体的な取組みを語る「健康経営グループ」グループ長の橋本友紀さん
健康経営の具体的な取組みを語る「健康経営グループ」グループ長の橋本友紀さん
実際に健康経営に着手してみて感じるのは、特定の部署や個人だけが頑張るのではなく、社員同士が互いに関心を持てるような仕組みをつくることの大切さです。最初に明確なトップメッセージを打ち出すことは重要ですが、その後は会社や上司が旗振りするよりも、社員一人ひとりが当事者意識を持って能動的に取り組むことが肝心です。こうした姿勢の結果、健康の重要性や各施策がスムーズに浸透していったのだと思います。健康経営グループを軸としつつ、全国の各部門に健康経営の推進担当者を設置したことも、職場ごとに取り組みを進めてもらう体制づくりの一環です。
また、社員のヘルスリテラシー向上に努めることは、本人の健康に寄与するだけでなく、お客さまへの適切な情報提供にもつながります。もともと当社にはお客さまのためになることを積極的に学ぼうとする社員が多いのですが、さらなる後押しのため各種セミナーやミーティングを数多く開催しています。さらに、「オンライン職場留学」という部門横断的な学びの場もあります。これは、社内のシステムを活用し、全国どの部門で開催される勉強会にも自由に参加できる仕組みのこと。例えば、健康経営グループの報告会に宮崎支社の営業職が参加したり、金沢支社で開催されるがん予防の勉強会に東京にいる本社内勤社員が参加したりといった様子も日常的に見られます。
健康に関する社員の関心は高く、以前、がん罹患者の方のお話を伺うセミナーを開催した際は、全国から約200人も参加者が集まりました。
こうした取り組みを背景に、社員のヘルスリテラシーは着実に上昇しつつあります。2023年度に全社員に実施した健康経営の取組みに関するアンケートでは、社員の健康実感およびヘルスリテラシーの向上が見られました。
 【画像元】SOMPO ひまわり生命「健康経営」- 実績・効果 社員のヘルスリテラシーの向上 2023年度 健康経営の取組みに関する従業員アンケートを元にマイナビ健康経営で加工
【画像元】SOMPO ひまわり生命「健康経営」- 実績・効果 社員のヘルスリテラシーの向上 2023年度 健康経営の取組みに関する従業員アンケートを元にマイナビ健康経営で加工
https://www.himawari-life.co.jp/company/kenko/
孫の誕生でも休暇取得OK!背景にある思いとは
年齢や性別にかかわらずさまざまな特性の社員がいきいきと働くためには、直接的な健康への施策だけでなく、勤務制度を整えることも重要です。例えば、近年ではがんなどの治療と仕事の両立をめざす方も珍しくなくなりました。当社では『治療と仕事の両立支援BOOK』などで情報提供する他、短時間勤務制度、シフト勤務制度、週4勤務制度、フレックスタイム制などを導入し、柔軟な働き方を実現しています。これにより、「病院で治療を受けてから出社する」といった動きもスムーズになるわけです。このうち、短時間勤務制度、シフト勤務制度、週4勤務制度については、妊娠・育児や介護中の社員も活用できる共通の制度。ライフステージの変化に伴って課題が生じても、本人が望む限り仕事が続けられるように環境を整備したいと考えています。
 社員とその家族の健康を守り、社員一人ひとりが長く健やかに働ける職場は、取引先やお客さまの健康にもつながると考え、日々実践していると語る
社員とその家族の健康を守り、社員一人ひとりが長く健やかに働ける職場は、取引先やお客さまの健康にもつながると考え、日々実践していると語る
数ある制度の中でも特徴的なのが、「まご・おいめい育児休暇」でしょう。その名の通り、孫や甥・姪が誕生したとき育児サポートのために取得できる休暇制度ですが、その背景には「男性の育児休業取得を当たり前にしたい」という思いがあります。女性にとっては一般的になりつつある育児休業ですが、男性の取得はなかなか進まないのが現状で、当社でも以前の取得率は41.3%でした。そこで、育児休業になじみのない世代にもその意義を体感してもらうため、孫や甥・姪の誕生に際しても利用可としたのです。特に、孫が生まれるような世代の社員はマネジメントを担う立場であることも多く、「まご・おいめい育児休暇」をきっかけに、周囲にも育児休業を促すといった効果が見込めます。実際、本制度の導入後、当社の男性の育児休業取得率は92.1%にまで跳ね上がりました。
このように、無理なくやりがいを持って働きやすい体制構築の成果もあってか、当社ではワークエンゲージメントのスコア(※)についても上昇傾向を維持しています。ただし、こうした制度設計においては、不公平感が生じないよう十分な配慮が欠かせません。特定の層だけが得をするような制度では長続きしませんから、より多くの社員に対して相乗効果をもたらす「1粒で何度もおいしい施策」になるよう議論を重ねています。また、福利厚生とは位置付けが異なるため、各制度の導入がどのように組織や個人の成果につながるか、といった視点も検討では忘れないようにしています。
※Gallup Q12(エンゲージメント調査項目)の平均スコア。

【画像元】SOMPO ひまわり生命「健康経営」- 実績・効果 KPIの取組み状況 <KPI以外の項目>からワークエンゲージメント項目を抜粋しマイナビ健康経営で加工
https://www.himawari-life.co.jp/company/kenko/
「働き方」と「生き方」の両方を企業として応援
健康経営に「鉄板」はない――。これが私の持論です。皆が確実に健康になれる夢のような施策は存在せず、社員の声に耳を傾けながら多くの取り組みを進める中で、ようやく成功パターンが見えてくるもの。失敗を恐れず、むしろ失敗しても当たり前くらいに考え、次につなげるポジティブな気持ちを持ち続けることが大切です。当社でも、決してすべての施策が大成功してきたわけではありません。例えば以前、オンラインで学べる講座を導入したものの、利用者数が伸びずに中止したことも。推進の方法に課題があったと捉え、異なるかたちでリベンジしたいと考えています。
私自身のキャリアを振り返ってみると、今のようなかたちで人事担当になることは予想外でした。1997年の入社時はいわゆる一般職で、名古屋支社で事務職を担当。東京本社に異動してからは、事務や広報など多様な部署に関わることに。女性活躍推進の波に乗った感覚で、自分の中でも働き方に関する価値観が次第に変わっていったように感じています。CHRO・人財開発部長という現職に就いてから日は浅いですが、「後輩が活躍しやすい・働きやすい環境を整えたい」というマインドは以前から変わらず持ち続けてきました。入社当初に私を支えてくれた先輩のように、周囲を力強くサポートできる存在でありたいと願っています。
 野田さんや健康経営グループだけでなく、社員一人ひとりが主体的に取り組む中で、健康的で働きやすい企業文化が醸成されていく
野田さんや健康経営グループだけでなく、社員一人ひとりが主体的に取り組む中で、健康的で働きやすい企業文化が醸成されていく
ワークライフバランスという言葉は一般的になりましたが、「仕事と生活は相反する存在」というイメージにつながっている部分もあるように感じます。単純に労働時間を短縮してプライベートを充実させようとするのではなく、仕事と生活の両方で充実を図れるよう、企業としても支援することが求められるのではないでしょうか。社員の「働き方」だけでなく「生き方」をも応援する姿勢が、ひいては人的資本経営という概念につながっていくのだと思います。
ホワイト500に8年連続選出された |
&res=1280x720&is_new_uid=true&_tcuid=202504060355300259&_tcsid=202504060355300227)