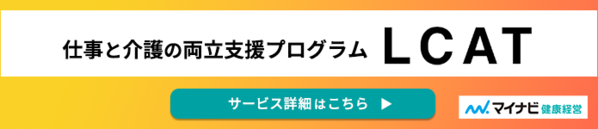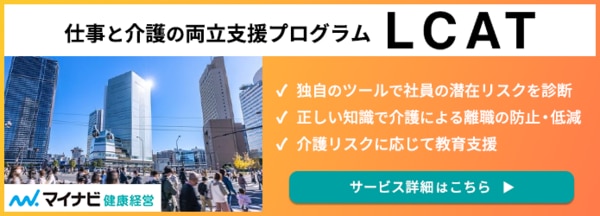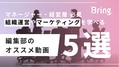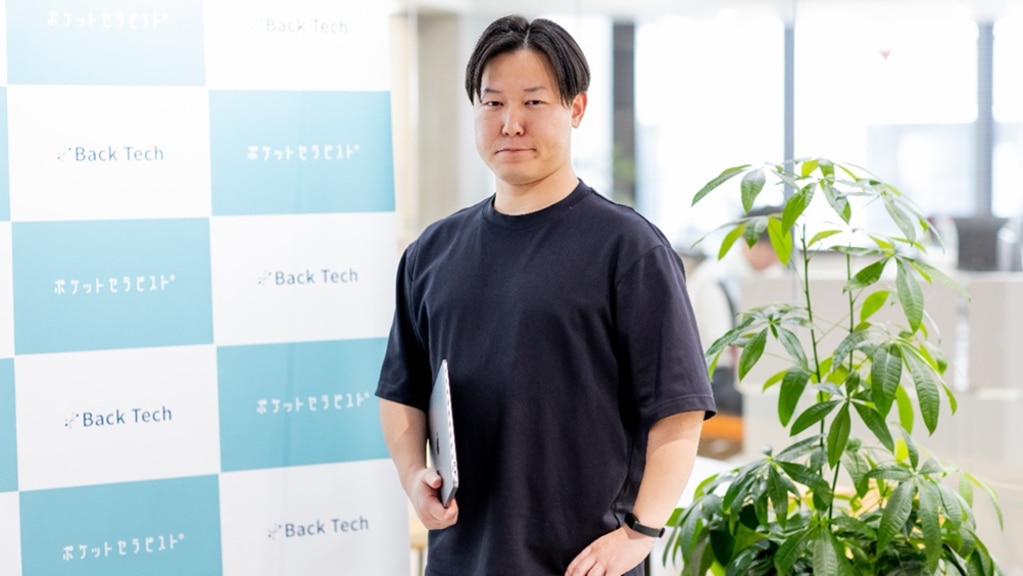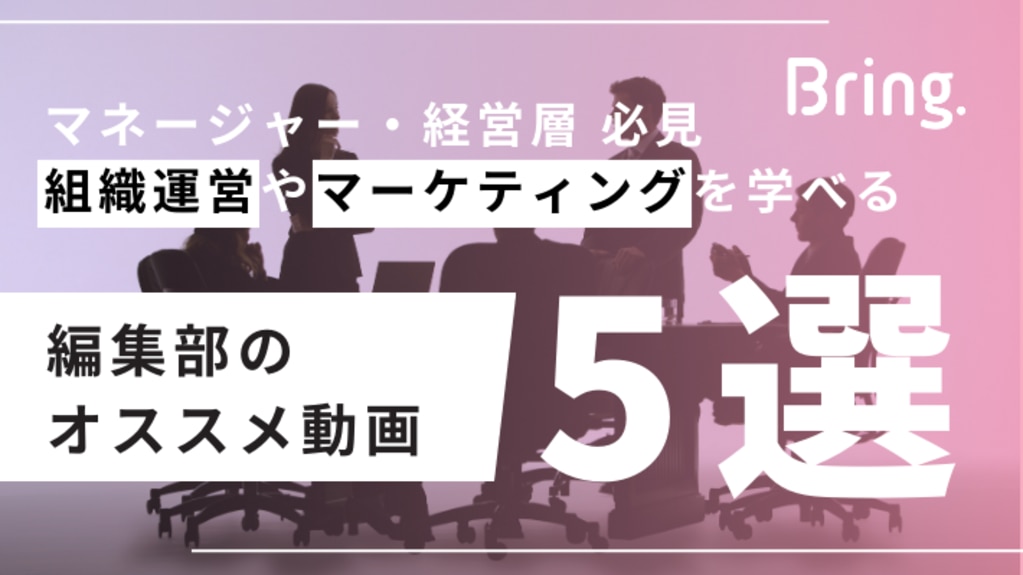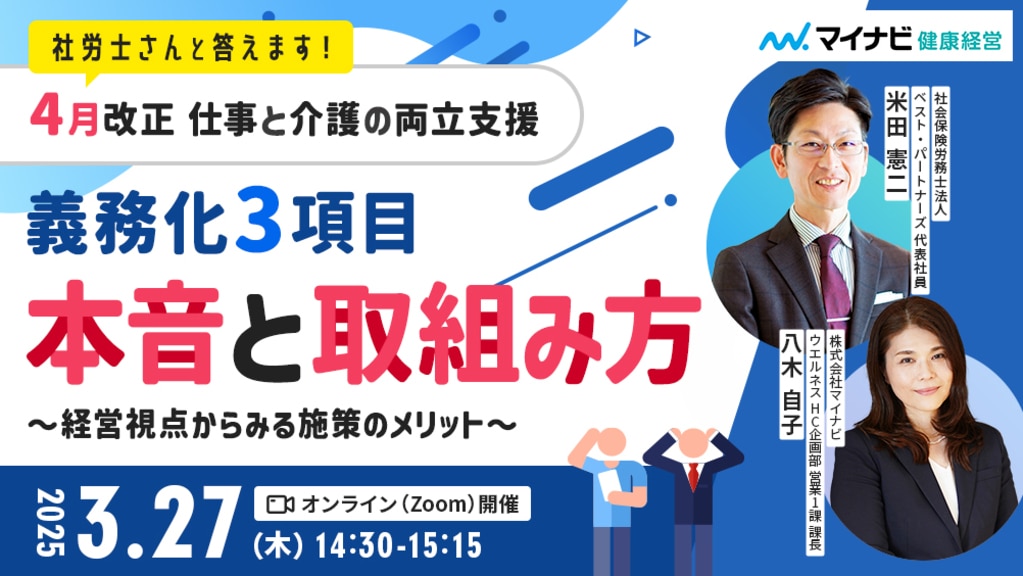介護休暇とは?取得の方法や介護休業との違い、現在の課題などを解説
日本の総人口に占める65歳以上の割合が増えるにつれ、日常生活の支援や介護を要する高齢者も増加していきます。75歳以上の約3割、85歳以上の約6割が要介護認定を受けているともいわれる今、組織の中核をなす40代、50代の働き盛りが介護を担い、仕事との両立に苦しんで離職を余儀なくされることも珍しいことではありません。
介護は突然やってきて、仕事と家庭のバランスに大きな影響を与えます。優れた人材を介護離職から守ることは、企業にとって喫緊の課題だといえるでしょう。
本記事では、企業が仕事と家庭の両立を制度として支援する介護休暇について、取得方法や得られるメリットなどを中心に解説します。
【参照】厚生労働省「図表2-1-4 年齢階級別の要介護認定率」|厚生労働省(2022年9月)
https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/21/backdata/01-02-01-04.html
目次[非表示]
介護休暇とは、短期の休みを取得できる制度
介護休暇は、病気やケガ、身体上あるいは精神上の障害などによって、家族が2週間以上の常時介護を必要とする状態にあるとき、介護を行う労働者が短期の休みを取得できる制度です。
これは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」で認められた従業員の権利であり、同法では「事業主は介護休暇(休業)申請を拒否できない」と定めています。
入浴や食事、排せつの介助といった直接的な介護だけでなく、要介護者の代わりに買い物に行く、書類の手続きをするといった場合にも利用することができます。
なお、介護休暇中の従業員は労務を提供していないため、会社側に給与を支払う義務はありません。一方、失効した年次有給休暇を使用するなど一定の範囲で有給にすることも可能であり、有給・無給の判断は企業の裁量に任されています。
いずれの場合でも、企業は事前に就業規則として介護休暇における有給・無給について明文化しておくことが大切です。
【参照】厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(令和4年4月1日)|厚生労働省(2022年4月)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000806832.pdf
介護休暇を取得できる人と、取得の対象となる家族の範囲
介護休暇を取得できるのは、下記に記載する対象家族を介護する男女の労働者です。正社員だけでなく、アルバイト、パート、派遣社員、契約社員も含まれます。
<介護休暇取得の対象となる家族>
- 配偶者(事実婚を含む)
- 父母
- 子
- 配偶者の父母
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
なお、1日ごとに契約期間が満了する日々雇用、いわゆる日雇い労働者は介護休暇の対象になりません。また、労使協定を締結している場合、下記の労働者も対象外となることがあります。
<介護休暇取得の対象外例>
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
入社6ヵ月未満の労働者
介護休暇を申請するにあたって、対象家族との同居の有無は問われません。また、必ずしも要介護認定を受けている必要もありません。判断に悩むときは、厚生労働省が定める「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」を参考にするといいでしょう。
なお、常時介護の基準を重視するあまり介護休暇の申請・取得を減らすことは、対象家族を気軽に介護でき、かつ職場復帰を促進する介護休暇の本来の目的と異なってしまいます。企業側は、この基準はあくまでも目安として捉え、できるだけ柔軟な対応をすることが好ましいといえます。
※2025(令和7)年4月1日から入社6か月未満の労働者を対象外とする要件は廃止されました。
【参照】厚生労働省「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000145708.pdf
介護休暇の取得できる日数と単位
介護休暇は、対象家族が1人の場合は年5日まで、対象家族が2人以上いる場合は年10日まで取得することができます。時間単位、または1日単位で申請が可能です。
「遠方で暮らす要支援・要介護の家族の調子が悪い」「入院することになって付き添いが必要」といった際にまとめて取得できるほか、「当事者に代わって介護サービスの申請をしたい」「ケアマネジャーと打ち合わせをしたい」といった短時間の用途でも活用できます。
介護休暇の取得方法
介護休暇は、上長や人事部門に申請して取得します。申請方法は書面に限らず、口頭で申請することも可能です。介護は突発的に必要になることも多いため、できるだけシンプルな方法で容易に取得できたほうが良いという背景があるためです。
必要な情報(申請者の名前、対象家族の続柄、介護休暇の取得から終了までの期間など)がわかれば当日朝の電話でも取得できるようにするなど、企業は申請のハードルを下げる対応が求められます。
もちろん、自社内で制度としてまだ確立しておらず、申請する側も受け付ける側も経験値が少ない場合は、定着するまで専用の書面を用意してもいいでしょう。いずれにせよ、あらかじめ就業規則で定めて社内に周知しておくことが大切です。
介護休暇と介護休業の違い
介護休暇と混同される制度のひとつに、介護休業があります。介護休業は、要介護状態の家族のサポートをするために、数週間や数ヵ月といった長期休暇を申請・取得できる制度です。介護休業は介護休暇と同様に、育児・介護休業法で定められた労働者の権利です。
介護休業取得の条件となる要介護者の範囲は介護休暇の対象者と変わりませんが、取得できる期間、取得できる従業員、給与の有無、申請方法などに違いがあります。詳しくは下記をご覧ください。
介護休業 |
介護休暇 |
|
取得期間 |
対象家族1人につき、最大通算93日まで(3回まで分割が可能) |
|
取得できない従業員 |
|
|
申請方法 |
書面(休業開始予定日の2週間前までに事業主に申出) |
口頭や書面(取得当日、口頭での申請でも構わない) |
決定通知 |
書面等で通知する必要がある |
口頭でのやりとりで許可できる |
給与 |
原則として無給(ただし、要件を満たせば介護休業給付金の申請が可能) |
原則として無給 |
介護休業の申請を受けた企業は、介護休業開始予定日と介護休業終了予定日などを確定させ、従業員に書面等で通知します。併せて、介護休業給付金の支給対象である場合は、企業がハローワークに申請する必要があることを覚えておきましょう。
介護休業給付金とは、要介護状態の家族を介護しなければならない従業員の生活を守る施策で、下記の条件を満たせば「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」が支給されます。
<介護休業給付金の支給条件>
- 雇用保険に加入している
- 2週間以上の休業が必要
- 職場に復帰する予定である
【参照】厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158665.html
【参照】厚生労働省都道府県労働局雇用環境・均等部(室)「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]」|厚生労働省(2022年10月)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685056.pdf
【参照】厚生労働省「介護休業について」|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/closed/index.html
【参照】厚生労働省「介護休暇について」|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/holiday/index.html
【参照】厚生労働省「介護休暇制度」|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355372.pdf
介護休暇と介護休業を選択する際の目安
ここまで解説したとおり、介護に伴って取得できる休みには、介護休暇と介護休業があります。前述したように、取得のしやすさや取得期間などに違いがあるため、休みを取る目的や所要時間によって使い分けが必要です。
ここからは、介護休暇・介護休業のどちらでも取得できる従業員を想定して、いずれかを選ぶべきか適したシーンをご紹介します。
介護休暇を選んだほうが良いシーン
介護休暇は、時間単位で申請でき、当日申請も可能な点が特徴です。そのため、事前に予測できない突発的な出来事や、直接的な介護以外の短時間で済む用事などで使用するのがおすすめです。
例えば、下記のようなシーンが考えられます。
-
介護保険などの手続き
介護保険の利用には申請が必要です。しかし、要介護者自身が手続きをするのは困難な場合もあり、家族が代理で手続きをすることもあるでしょう。申請の際は、被保険者証を持って要介護者が居住する市区町村役場へ行き、「要介護認定の申請」を行わなくてはなりません。役場までの距離にもよりますが、半日から1日の休みが必要となるはずです。 要介護者の突然の体調不良
要介護者が急に体調を崩したり、ケガをしたりして、いったん様子を見に行く場合は、長くても1日あればその後の対応を判断できます。状況に応じて、休暇の延長を検討するといいでしょう。病院への付き添い、送迎
病院への付き添いや送迎も、通院日に合わせて半日~1日の取得で間に合うことが多いです。要介護者の自宅が遠い場合や、検査に1日かかるといった場合も、2~3日の休暇で間に合います。介護保険の認定調査
介護保険の申請をすると、認定調査のため調査員が要介護者の自宅を訪問します。日頃の状況を正しく伝えるため、できれば家族が同席するのが望ましいでしょう。調査員の訪問は平日の昼間に30分~1時間程かかるため、介護休暇の利用が向いています。介護士・ケアマネジャーなどとの面談
要介護認定を受けると、ケアマネジャーが適切な介護サービスを受けるためのサポートをしてくれます。初回の顔合わせやケアプランの作成には、家族が立ち会う必要があります。日常生活の介護
日常生活の介護も介護休暇で認められます。身の回りの世話の一部に見守りや介助が必要である場合は、介護休暇を申請しましょう。
【参照】厚生労働省「介護休暇について」|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/holiday/index.html
介護休業を選んだほうが良いシーン
介護休業は長く休みを取れるため、自宅での介護に向けた準備期間や、自宅から施設へ介護を移行する準備期間などにも適しています。介護休業を選んだほうが良い状況としては、下記のようなシーンが考えられます。
-
介護施設への入居準備
要介護者が介護施設に入居するための準備は煩雑です。入居条件に合致していて空きがある施設を見つけたら、要介護者本人といっしょに見学をして部屋を確保し、面談を受けたり、健康状態のチェックなどを行ったりした上で契約を結びます。
面談や審査が多く、かかりつけの病院や役所などさまざまな場所に足を運ばなければならないため、手続き完了まで数ヵ月かかることもあるかもしれません。そこで、介護休業によってまとまった休みを取得できると、負担を減らすことができるでしょう。 遠距離介護から同居介護に変更するとき
遠方に住んでいた要介護者を自宅に呼び寄せて同居介護に移る場合、同居する自宅のリフォームや、要介護者の自宅の整理、引越し手続き等が必要です。何度も休みを取るよりは、介護休業を活用して一度に済ませたほうがいいでしょう。患者のみとりが近くなっている
患者のみとりが近くなっている際にも、介護休業は取得できます。病院や施設、家族などから、みとりが近づいている旨の連絡があり、できるだけそばにいたい場合は介護休業を利用してはいかがでしょうか。
【参照】厚生労働省「介護休業について」|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/closed/index.html
介護休暇において企業が留意すべきポイント
ここからは、介護休暇の申請を受けた企業側が注意すべきポイントを紹介します。大きく3つに分けて見ていきましょう。
介護休暇は義務であり、企業側は申請を拒否できない
第一に、介護休暇は法律で定められた制度であるため、企業は従業員からの申請を拒否することはできません。介護休暇の仕組みづくりが遅れていても、就業規則で明文化されていなくても「取得したい」という従業員が現れたら申請を差し戻すことはできないのです。また、介護休暇を理由として、解雇や降格といった措置をとることも禁止されています。
企業は介護のための選択的措置を講じる必要がある
従業員から介護休暇の申し出があった場合、企業は介護休暇を許可するとともに、別の選択的措置を講じる義務があります。なお、選択的措置は、利用開始から3年以上のあいだに2回以上利用できることを前提としています。選択的措置とはどのようなものなのか、一例を見ていきましょう。
<選択的措置の例>
-
所定時間の短縮(短時間勤務)
1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務の制度を設置します。 フレックスタイム制度
一定の総労働時間を定めておき、その範囲内で従業員自身が働く時間を決定します。始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げ
病院に連れて行ってから出社する、入浴介助のために早く帰るといった介護が継続的にある場合に備え、元々の始業・終業時間を調整します。介護サービス費用の助成
介護サービスを利用する際にかかる費用を助成し、従業員のコスト面の負担を軽減します。
【参照】厚生労働省「短時間勤務の措置について」|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/shortworking/index.html
介護する従業員は、所定労働時間・時間外労働などの制限がある
介護休暇を申し出た従業員は、原則として残業させることはできません。「あらかじめ制度が導入され、規則が設けられるべきものであることに留意」と厚生労働省が方針を示しているため、就業規則の対応は早めにしておきましょう。
【参照】厚生労働省「就業規則における育児・介護休業等の取扱い」|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/kiteirei/1.html
介護休暇の現状と課題
介護休暇は、2012年に全面施行された改正育児・介護休業法で事業主の義務となりました。しかし、いまだ利用者は少なく、介護休暇を取得した人の割合はわずか2.3%です。
この背景には、介護休暇という制度自体が知られていないこともあります。介護に直面した従業員がすぐに制度を利用できるよう、ぜひとも周知を徹底しましょう。また、できる限り利用要件と利用手続きを簡素化し、利用しやすい仕組みにすることも重要です。
「高齢の親が老老介護状態である」「祖母を引き取って介護しようと思う」といった家庭の事情を率直に話せる風通しの良い風土も、介護休暇申請の後押しになるはずです。
【参照】厚生労働省「介護休業給付について」|厚生労働省(2015年11月)
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000103635.pdf
【参照】厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課「改正育児・介護休業法 参考資料集」|厚生労働省(2016年8月)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000134642.pdf
介護休暇のこれからの動向
厚生労働省が発表した「企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル」では、従業員の仕事と介護の両立支援に向けて取り組むべきことを「介護離職を予防するための仕事と介護の両立支援対応モデル」として整理しています。
<介護離職を予防するための仕事と介護の両立支援対応モデル>
- 従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握
- 制度設計・見直し
- 介護に直面する前の従業員への支援
- 介護に直面した従業員への支援
- 働き方改革
また、介護に直面する前の従業員への支援として、下記のような取り組みを進めるよう提言しています。
<介護に直面する前の従業員への支援例>
- 仕事と介護の両立を企業が支援するという方針の周知
- 「介護に直面しても仕事を続ける」という意識の醸成
- 企業の仕事と介護の両立支援制度の周知
- 介護について話しやすい職場風土の醸成
- 介護が必要になった場合に相談すべき「地域の窓口」の周知
- 親や親族とコミュニケーションを図っておく必要性のアピール
同マニュアルに記載されている各社の事例も参考にしながら、主体的に働き方改革を実践してみてはいかがでしょうか。
【参照】厚生労働省「企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル」|厚生労働省(2016年3月)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000119918.pdf
<育児・介護休業法の改正 2025年4月から段階的に施行>
育児・介護休業法が改正され、2025年4月1日から段階的に施行されます。介護休暇に関しては、「介護休暇を取得できる労働者の要件緩和」として、継続雇用期間6か月未満の労働者も介護休暇を取得できるようになりました。
また事業主は、介護に直面した労働者の介護離職防止のため、介護休業制度の周知や利用の意向確認を行うなど、情報提供やビジネスケアラーのケアをするよう改正されています。
2025年10月1日からは、主に仕事と育児の両立に関する措置が整備されます。
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和7(2025)年4月1日から段階的に施行|厚生労働省(2024年11月)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
従業員が安心して働ける環境づくりは、マイナビ健康経営にご相談を
介護は突然発生するもの。その事態に慌てないよう、企業も万全の準備をしておくことが大切です。介護と仕事の両立支援策をはじめ、従業員が安心して仕事に邁進できる環境づくりを平時から進めていってはいかがでしょうか。
「マイナビ健康経営」は、人と組織の「ウェルネス(健康)」をさまざまなサービスでサポートしています。従業員の心身の健康向や生産性向上、健康経営推進を検討されている方は、お気軽にお声がけください。
【免責及びご注意】 |
<監修者> |
&res=1280x720&is_new_uid=true&_tcuid=202504051613391444&_tcsid=202504051613397378)