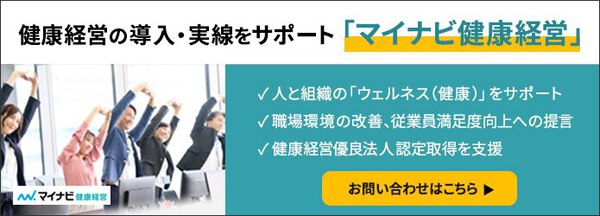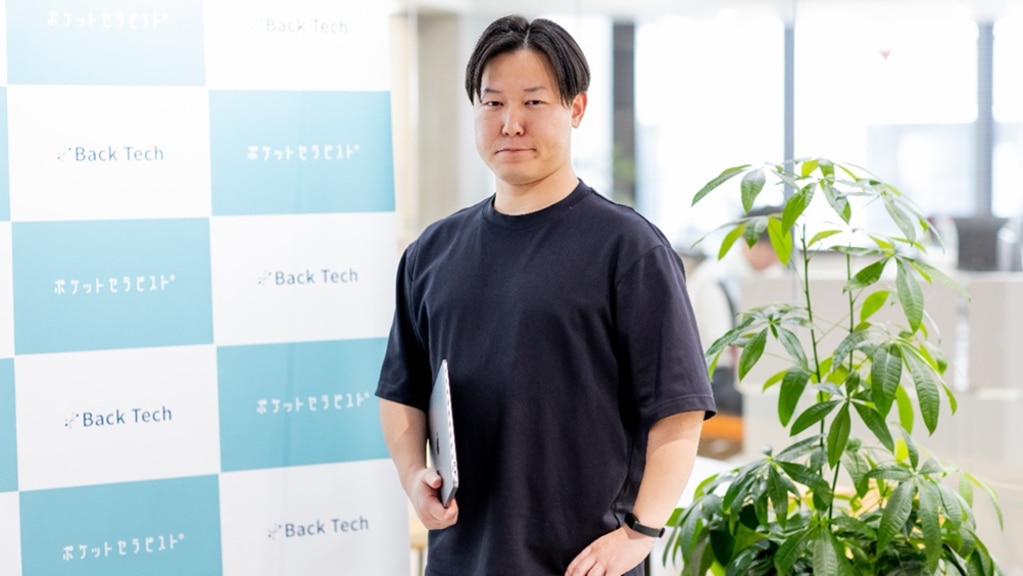育休手当はいくらもらえる?支給額の計算方法や申請の流れを解説
従業員が育休を取得すると、育休手当を受給することができます。育休期間中は給与が無給・減給になるケースが多いため、育休手当は子供が産まれたばかりの家庭の生活を支える大切な収入源となるでしょう。
しかし、育休取得を検討している人の多くは、育休手当がいくら程度であり、いつ支給されるのかといった多くの気がかりを抱いているのではないでしょうか。働き手の確保が難しい現在、働き盛りの従業員が安心して働ける環境をつくる意味でも、育休手当は企業にとっても大きなメリットとなるはずです。
本記事では、育休手当の概要や対象者のほか、期間、支給額などについて詳しく解説。育休手当支給日の目安や税金・社会保険の扱い、育休手当の申請手続きなどについても紹介していきます。
育休手当にまつわる疑問点を解消し、従業員が気持ち良く働き続けられる職場環境づくりの一助として本記事をご活用ください。
目次[非表示]
- 1.育休手当とは、育児休業取得の際に受け取れる手当のこと
- 2.育休手当の支給条件
- 2.1.育休手当の対象とならないケース
- 3.育休手当の期間
- 3.1.育休手当は1歳の誕生日の前々日まで
- 3.2.育休期間を延長できる条件
- 3.3.育休期間を延長できる制度
- 4.育休手当給付金はいくら支給されるのか?
- 4.1.育休手当給付金の計算方法
- 4.2.育休手当給付金の計算例
- 4.3.育休手当給付金の支給限度額
- 5.育休手当支給日の目安
- 6.育休手当受給時の税金と社会保険
- 7.育休手当の申請手続き
- 7.1.育休手当に必要な書類
- 7.2.育休手当の流れ
- 8.男性の育休手当
- 8.1.男性の育休手当の受給期間と支給額
- 8.2.産後パパ育休
- 9.育休手当を受給する上で覚えておきたいポイント
- 9.1.個人でも育休手当の申請はできる
- 9.2.給付金は毎月受け取ることもできる
- 9.3.第二子以降は、第一子と金額が異なることもある
- 10.育休手当は健康経営の観点からも有効
育休手当とは、育児休業取得の際に受け取れる手当のこと
育休手当とは、育児休業を取得した際に受け取ることのできる手当であり、正式名称を「育児休業給付金」といいます。会社の就業規則によりますが、特別な規定がない限り、育休中は無給もしくは減給となることが想定されます。
そこで国は、働く親が安心して育休を取得できるよう、育休手当を規定しました。育休手当があれば育休中の生活基盤が安定するため、国は育休の積極的な取得を支援しています。
なお、育休手当を規定する育児・介護休業法は、年を追って改正されています。2022年10月の改正では1歳までの育児休業を分割で取得できるようになりました。それまで育児休業は原則1回しか取得できませんでしたが、2022年10月からは父親・母親それぞれ2回までの取得が可能となっています。
また、2023年4月の改正により、従業員数が1,000人を超える事業主には、男性の育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられました。さらに、2025年4月からは、従業員数が300人を超える事業主にも同様に義務付けられます。改正はこれから先も行われていく可能性があるため、育児・介護休業法については定期的なチェックをおすすめします。
【参照】厚生労働省「育児休業制度特設サイト」|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/
【参照】厚生労働省「男性の育児休業取得率等の公表について」|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00006.html
育休手当の支給条件
育休手当を受け取ることのできる対象者は、性別に関係なく、1歳未満の子供を育てるために育休を取得する雇用保険の加入者本人です。雇用保険加入者が対象のため、自営業やフリーランスの方は対象外となります。
なお、育休手当の対象となるには、一定の条件があります。
育児手当を受給するには、下記の要件を全て満たすことも支給対象の条件となっているため、確認をしておきましょう。
<育休手当受給の要件>
- 育児休業開始日前2年間に、11日以上働いた月数が12ヵ月以上あること
- 育児休業期間中に毎月、休業開始前の1ヵ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
- 就業日数が支給単位期間(1ヵ月)ごとに10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下であること
- 有期雇用契約で勤務している場合は、上記3つの要件に加えて、同じ事業主のもとで1年以上継続して働いており、子供が1歳6ヵ月に達する日までにその労働契約が満了することが明らかでないこと
上記の要件を満たした上で育休を取得すれば、母親、父親を問わず育休手当を受給することができます。
【参照】厚生労働省 都道府県労働局「育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します」|厚生労働省(2024年1月)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r02_01_04.pdf
育休手当の対象とならないケース
育休手当は、前述の要件を全て満たしていれば何度でも受給できるわけではありません。下記のようなケースは育休手当の対象とならないため、注意が必要です。
<育休手当の対象から外れるケース例>
-
育児休業が始まる時点で退職する予定がある
育休手当は、育児休業終了後に職場へ復帰することを条件とした給付金です。育児休業が始まる時点で退職の予定がある場合は、育休手当の支給対象となりません。 -
育休中でも給与が8割以上支給されている
育休手当の1支給単位期間に「休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上」の賃金が会社から支払われている場合、支給額は0円となります。
【参照】厚生労働省「Q&A~育児休業給付~」|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
育休手当の期間
育休手当はどれくらいの期間、受給することができるのでしょうか。具体的な育休手当の対象期間や、育休期間を延長できる条件は下記のとおりです。
育休手当は1歳の誕生日の前々日まで
育休手当の対象期間は、基本的に「育休の取得中」です。子供が1歳になる日の前日まで支給されますが、民法第143条の規定では、満年齢に達するのは誕生日の前日とされています。そのため、実際の支給期間は、1歳の誕生日の前々日までとなっている点は押さえておきましょう。
なお、支給は育休の取得日数を対象としているため、自己都合で育休の期間を短縮すると、育休手当の支給期間も同じように短縮されます。
【参照】厚生労働省「Q&A~育児休業給付~」|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
育休期間を延長できる条件
育休期間は延長することも可能です。下記のようなケースに該当する場合は、子供が1歳6ヵ月(最長2歳)になるまで育休期間を延長できる可能性があるため、育休手当の支給期間も同様に延長されることが期待できます。
<育児休業が延長になるケース>
- 待機児童などの問題で子供が1歳、もしくは1歳6ヵ月になっても保育所への入所ができない場合
- 子供の主たる養育者が死亡したとき
- 子供の主たる養育者が、負傷・障害等によって子供の養育が困難な状態に陥ったとき
- 配偶者が子供と同居しないことになったとき
- 育休中に新たな妊娠・出産によって、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定がある。または、8週間の産前産後休暇の期間にかかるとき
なお、子供が1歳6ヵ月に達した後も育休を延長して取得する場合は、その子供が2歳になるまでのあいだ、育休を延長することも可能です。育休が延長されているときは、保育所に入所できないといった一定の要件を満たしている場合、育休手当の支給期間も同様に延長されます。
また、上記の要件に該当しない場合でも、「パパ・ママ育休プラス」の制度を利用すれば、子供が1歳2ヵ月になるまで育休を取得し、育休手当を受け取ることもできます。
例えば、子供が1歳になるまで母親が育休を取得し、母親の復職と同時に子供が1歳2ヵ月になるまで父親が育休を取得した場合、母親と父親はそれぞれ育休手当を受け取ることができます。
【参照】厚生労働省岐阜労働局「育児休業給付金の延長申請について」|厚生労働
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/content/contents/000588771.pdf
育休期間を延長できる制度
育休期間を延長できる条件に該当しない場合でも、「パパ・ママ育休プラス」という制度を利用すれば、育休の延長が可能となり、育休手当の支給も受けられます。
「パパ・ママ育休プラス」は、2009年7月の育児・介護休業法改正で新設された制度です。両親が共に育児休業を取得する家庭が一定の条件を満たした場合、子供が1歳2ヵ月になるまで育休期間を延長できます。
また、通常の育休と同様、育休開始日から180日間は月額給与の67%、181日目から支給終了日までは50%の育休手当が支給されます。
<「パパ・ママ育休プラス」の利用要件>
- 育児休業を取得しようとする労働者(以下、本人)の配偶者が、子の1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)以前において育児休業をしていること
- 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
- 本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
なお、「配偶者」には、法律上の配偶者だけでなく事実上の婚姻関係も含みます。
「パパ・ママ育休プラス」を利用する場合、例えば下記のようなパターンが考えられます。
<「パパ・ママ育休プラス」の利用パターン>
- 母親が産休後に育休を1年間取得して復職し、交代で父親が2ヵ月の育休を取得する
- 母親が産休後に育休を取得し、途中から1歳2ヵ月まで父親も育休を取得する
- 母親が産休後に育休を取得し、6ヵ月くらいから祖父母に預けて復職した後、8ヵ月から1歳2ヵ月まで父親が育休を取得する
上記のように、両親の育休期間が連続している必要はありませんし、重複しても構いません。
ただし、母親の育児休業開始日が父親より先の場合、母親は「パパ・ママ育休プラス」の対象にはならないことに注意が必要です。この場合、母親が育休を取得できる期間は子供が1歳に到達する日までとなります。
1歳2ヵ月まで育休を取得できるのは、原則として後から育休を取得した配偶者のみであることに注意してください。
また、「パパ・ママ育休プラス」は、父親と母親の両方が育休を取得することを前提とした制度なので、どちらかが専業主婦(夫)の場合や、自営業やフリーランスで雇用保険に加入していない場合は対象外となります。
【参照】厚生労働省「パパ・ママ育休プラス」|厚生労働省
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0146/0019/papamama.pdf
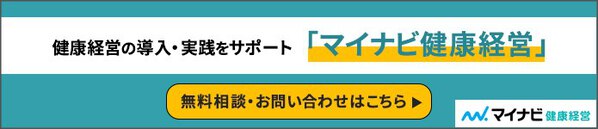
育休手当給付金はいくら支給されるのか?
育休手当は、いくらくらい支給されるものなのでしょうか。続いては、育休手当給付金の計算方法や計算例、支給限度額について解説します。
育休手当給付金の計算方法
育休手当給付金は、休業を開始した際の賃金に一定の割合を乗じて計算します。具体的な計算式は下記のとおりです。
<育休手当給付金の計算式>
- 育休開始から180日以内:育休手当=休業開始時の賃金日額×支給日数×67%
- 育休開始から181日以降:育休手当=休業開始時の賃金日額×支給日数×50%
休業開始時の賃金日額とは、育休開始前6ヵ月間の賃金を180日で割った額です。賃金は、残業手当や通勤手当、住宅手当などを含む給与額面を指しています。手取り額ではない点には注意してください。
【参照】厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」│厚生労働省(2024(令和6)年8月1日改訂版)https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001276629.pdf
育休手当給付金の計算例
具体的に給付金の目安が分かるよう、育休手当給付金の計算例をご紹介します。育休手当が1ヵ月にどれくらい支給されるのか、下記を参考に計算をしてみましょう。
<賃金1ヵ月30万円の場合の計算例>
- 休業開始時の賃金日額:180万円(30万円×6ヵ月)÷180日=1万円
- 育休開始から180日以内の1ヵ月の支給額:1万円×30日×67%=20万1,000円
- 育休開始から181日以降の1ヵ月の支給額:1万円×30日×50%=15万円
- 1年間育休を取得した場合の総額:20万1,000円×6ヵ月+15万円×6ヵ月=210万6,000円
育休手当給付金の支給限度額
育休手当給付金には支給額と、その計算のもとになる賃金の額に限度があります。2025年7月31日までの休業開始時賃金日額の上限額は1万5,690円、下限額は2,869円です。支給日数が30日の場合の支給上限額と支給下限額の例は下表のとおりです。
■賃金額の上限と下限の例
支給率67% |
支給率50% |
|
上限額 |
31万5,369円 |
23万5,350円 |
下限額 |
5万7,666円 |
4万3,035円 |
支給限度額を超えた場合は、育休手当は一律に上限額までとなります。下限額に満たない場合は、一律に下限額まで引き上げられて支給されます。
【参照】厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」│厚生労働省(2024(令和6)年8月1日改訂版)https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001276629.pdf
育休手当支給日の目安
育休手当は、基本的に2ヵ月分まとめて支給されます。母親の場合、育休は産休期間の8週間が明けてから開始するため、初回給付金の入金は、出産日からおよそ4~5ヵ月後を目安にしておくといいでしょう。
なお、育休手当給付金の申請期限は、育休開始日から4ヵ月経過後の月末までです。その期限を過ぎると交付が認められないため注意が必要です。
また、育休手当は1回目の申請だけで支給が続くわけではありません。1回目では育休開始から2ヵ月分の休業状況を対象にハローワークが審査を行い、振込が行われます。
2回目以降は、基本的には2ヵ月単位で支給を申請し、休業状況の審査が行われた後に支給額の振込が行われます。
【参照】厚生労働省「Q&A~育児休業給付~」|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
【参照】厚生労働省 ハローワーク インターネットサービス「育児休業給付」|厚生労働省
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_childcareleave.html
育休手当受給時の税金と社会保険
育休手当を受給すると、税金や社会保険の扱いがどうなるかは気になるポイントです。
結論をいうと、育休手当の給付金は非課税扱いとなります。そのため、所得税や復興特別所得税、住民税を納付する必要はありません。
また、育休中に会社から賃金が支払われていない場合は、雇用保険料の納付は不要です。
さらに、健康保険料や年金保険料も申請をすれば、免除となることもあります。免除されるには事業主による年金事務所への申請が必要となりますが、被保険者・事業主の両方の負担が免除されるため、忘れずに申請をしておきましょう。
【参照】マイナビ転職「育休手当(育児休業給付金)とは?申請方法や受給期間を解説」│株式会社マイナビ(2024年7月24日)
https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/153/
育休手当の申請手続き
育休手当を申請するにはハローワークに書類を提出するなど、一定の手続きが必要です。具体的にどのような書類が必要で、どのような流れで申請を行うのか見ていきましょう。
育休手当に必要な書類
育休手当を申請する際には、下記の書類が必要となります。事業主、被保険者共に必要書類を用意しておきましょう。
<育休手当の申請に必要な書類>
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育休手当支給申請書
- 1・2に記載した賃金の額および賃金の支払い状況を証明できる賃金台帳やタイムカードなどの書類
- 母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類
上記の1~3の書類は、事業主が用意します。育休手当の被保険者の必要書類は4のみです。
【参照】厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」|厚生労働省(2024(令和6)年8月1日改訂版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001126859.pdf
育休手当の流れ
育休手当の申請を行う際の基本的な流れは、下記のとおりです。手続きは大きく、5つの流れに沿って行われます。
<育休手当の申請手続きの流れ>
- 被保険者が育児休業の取得を会社に伝える
- 事業主がハローワークに申請に必要な書類を提出する
- 受給資格があると認められたら、育児休業給付支給決定通知書と育児休業給付次回支給申請日指定通知書が事業所に交付される
- 指定口座宛に育休手当が給付される
- 2回目以降は、事業主が2ヵ月ごとに賃金額や賃金状況を確認できる書類を添えて育児休業給付金支給申請書を提出する
【参照】厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」│厚生労働省(2024(令和6)年8月1日改訂版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/0011276629.pdf
男性の育休手当
2023年4月の育児・介護休業法改正により、男性の育休取得を支援する機運が高まっています。本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対して、育休取得の意向を確認するよう企業に義務付けられたこともあり、2023年度の男性の育児休業取得率は約30%で過去最高となりました。ここからは、男性が育休を取得した場合の育休手当について解説します。
男性の育休手当の受給期間と支給額
女性は生後8週間の産休を経て育休を取得しますが、男性は配偶者の出産予定日から子供が1歳になる誕生日の前日まで育休を取得できます。出産日が予定日からずれた場合には、申請日から育休がスタートします。
また、育休手当については、育休期間を通して受け取ることが可能です。育休の支給額は、女性と同じく、育休開始から180日間は賃金の67%、その後は50%となります。
産後パパ育休
「産後パパ育休」は、育児・介護休業法の改正により2022年10月1日から施行された制度です。正式名称は「出生時育児休業」で、従来の育休と併用して、子供の出生後8週間以内に最大で4週間休業できます。
産後パパ育休は、通常の育休とは別に、2分割して取得することも可能で、母親の都合に合わせて取得できるのがメリットです。また、下記の条件を満たせば、産後パパ育休中も育休手当の支給を受けることができます。
<産後パパ育休中の育休手当の支給要件>
- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業している時間数が80時間以上の)完全月が12ヵ月以上あること
- 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下であること(これは、28日間の休業を取得した場合の日数・時間であり、28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなる)
支給を受ける場合、出生日から起算して8週間後の翌日以降、かつ出生時育児休業期間を含む月の給与支払日以降から、2ヵ月後の月末までに申請をします。
なお、通常の育休中は、原則就業できませんが、産後パパ育休は下記の要件を満たせば就業が可能です。
<産後パパ育休中の就労要件>
- 産後パパ育休中の就労は、所定労働日数・所定労働時間の半分まで
- 休業の開始日や終了予定日の就労可能時間が、所定労働時間数に満たないこと
【参照】厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」|厚生労働省(2022年12月改定)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
育休手当を受給する上で覚えておきたいポイント
育休手当を確実に受給するためには、申請方法や給付時期について知っておく必要があります。ここからは、育休手当の受給に際して、覚えておきたいポイントを3つご紹介します。
個人でも育休手当の申請はできる
育休手当は、個人で申請することも可能です。例えば、勤務先で初めての育休手当受給者で知見がない、スタートアップ企業で申請をする部署が確立されていないといった場合は、従業員が個人で手続きをする必要があるかもしれません。
個人で申請する場合、まずはハローワーク、もしくはハローワークインターネットサービスで育児休業給付金支給申請書と育児休業給付受給資格確認票を入手します。さらに、勤務先に依頼をして必要書類を集め、勤務先の所在地を管轄するハローワークに、すべての書類を提出したら申請完了です。
給付金は毎月受け取ることもできる
育休手当の受け取りは、原則ヵ月に1回となっていますが、希望をすれば1ヵ月ごとにできます。この場合、申請を毎月行う必要が生じるため、作業をする担当者の負担が増える可能性があります。
毎月育休手当を受給したい場合は、あらかじめ事業主に相談してもらいたい旨を、従業員に周知しておきましょう。
第二子以降は、第一子と金額が異なることもある
第二子以降の出産・育児で休業する場合、第一子とは手当の金額が変わることがあります。例えば、第一子の育児休業から復帰後の時短勤務中に第二子の妊娠がわかり、新たに育休を取得するパターンです。
この場合、育休手当の算出期間となる休業前の6ヵ月は時短勤務のため、第一子のときよりも賃金が少なくなり、支給額が減ることがあります。
育休手当は健康経営の観点からも有効
育休手当があることを知っていれば、従業員は安心して育児に専念できます。育休手当は原則として1歳の誕生日の前々日までの支給となりますが、育休を延長できる条件にあてはまる場合、あるいは夫婦共に育休を取得して「パパ・ママ育休プラス」が適用された場合には、育休手当の延長も可能です。
また、男性が通常の育休を取得した際の育休手当の受給期間や支給額に加え、産後パパ育休を取得した際の育休手当の支給要件などについても確認しておきましょう。育児期間が充実すれば、従業員のエンゲージメントも高まるかもしれません。
「マイナビ健康経営」は、人と組織の「ウェルネス(健康)」を総合的にサポートしています。従業員の心身の健康向上をお考えの際には、お気軽にお問い合わせください。
「マイナビ健康経営」のお問い合わせはこちら
【免責及びご注意】 |
<監修者> |
&res=1280x720&is_new_uid=true&_tcuid=202504031706433932&_tcsid=202504031706432224)