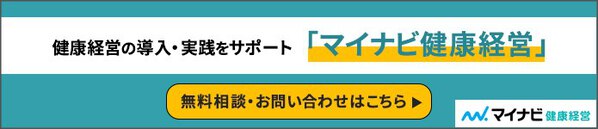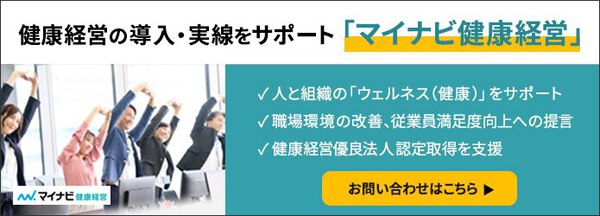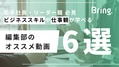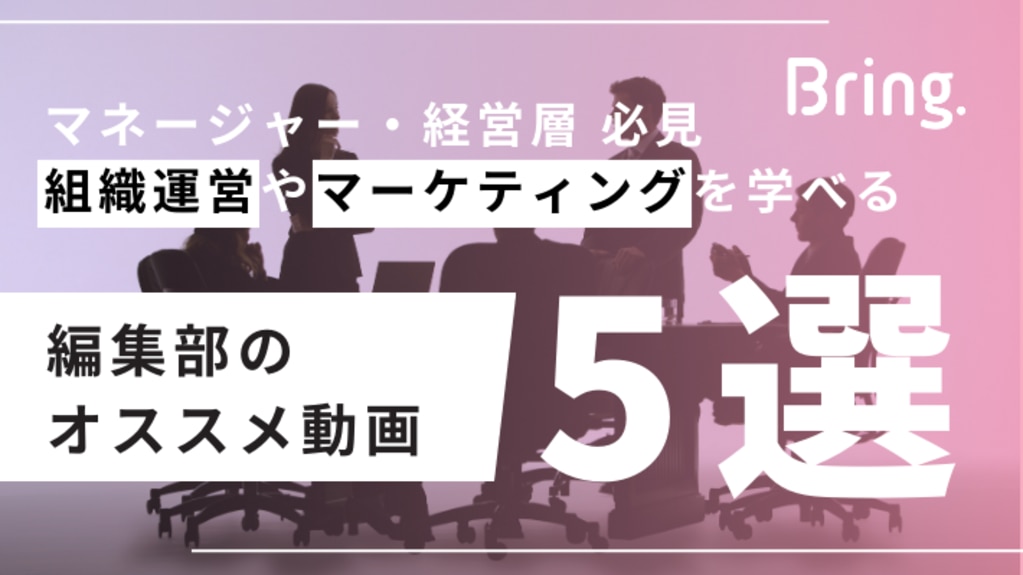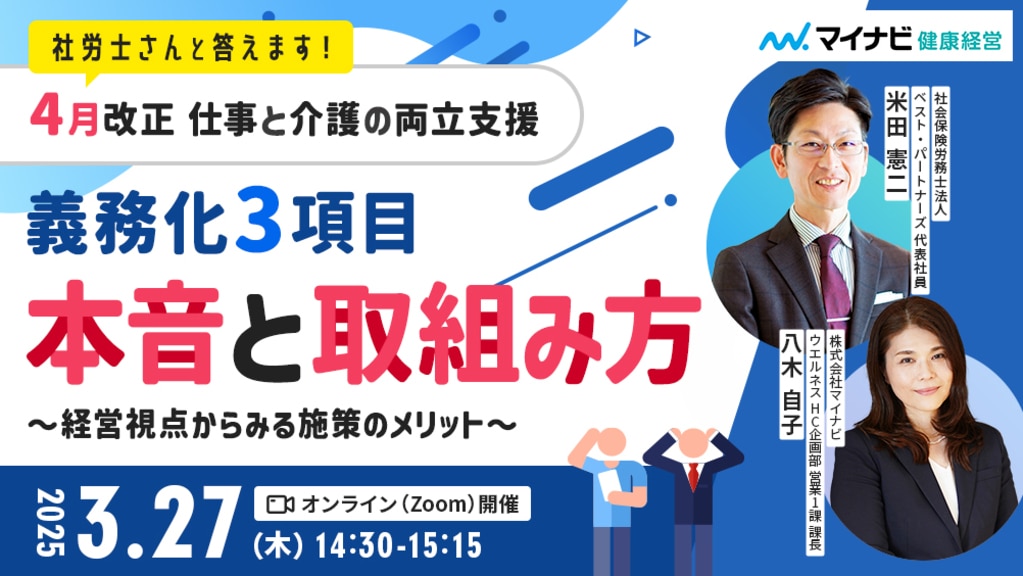会社の禁煙対策とは?法律や受動喫煙を防止するための進め方を解説
喫煙に対する社会の意識が高まる中、企業にも適切な禁煙対策が求められています。2018年の健康増進法の改正により、受動喫煙防止の取り組みがマナーからルールへと変わりました。2020年4月からは、飲食店やオフィス、事業所などの施設において原則屋内禁煙の規制が適用されています。
しかし、企業の禁煙対策を進める際には、「従業員に禁煙を義務付けることは法的に問題ないのか?」「受動喫煙対策をどのように進めるべきか?」など、さまざまな疑問が生じるかもしれません。
本記事では、企業が禁煙対策を行う必要性やメリット、法的リスクの有無、具体的な進め方について詳しく解説します。
目次[非表示]
- 1.会社で禁煙対策をする必要性とは?
- 2.会社が禁煙対策をするメリット
- 2.1.従業員の健康維持につながる
- 2.2.法的なリスクを回避できる
- 2.3.企業イメージの向上につながる
- 2.4.健康経営優良法人の認定を受けやすくなる
- 3.社員に禁煙を求めることへの違法性の有無
- 4.会社における禁煙対策
- 4.1.禁煙ルールを明確にする
- 4.2.喫煙所を設ける
- 4.3.喫煙エリアに年齢制限をかける
- 4.4.喫煙者に対する禁煙サポート
- 5.会社で受動喫煙を防止する取り組みの進め方
- 5.1.推進計画を策定する
- 5.2.担当部署を指定する
- 5.3.対策を定期的に確認する
- 5.4.喫煙場所の標識を設置する
- 5.5.従業員への啓蒙や情報提供を行う
- 5.6.求人募集で受動喫煙防止対策を明示する
- 6.会社の禁煙対策に関する助成金
- 7.企業の禁煙対策は健康経営の第一歩
会社で禁煙対策をする必要性とは?
企業における禁煙対策の必要性は、法改正や社会の動向の変化によってますます高まっています。2018年に改正された健康増進法により、受動喫煙対策が企業の義務として求められるようになりました。この法律は段階的に施行され、2020年4月1日から企業の屋内禁煙義務が本格的に施行されています。
この法律により、企業では原則として屋内を禁煙とし、喫煙が許可されるのは喫煙専用室および加熱式たばこ専用喫煙室のみと定められました。また、喫煙可能な場所には適切な標識の掲示が義務付けられ、施設の管理者には十分な受動喫煙防止策が求められるようになりました。このように、企業は職場環境を適切に整備し、従業員や来訪者の健康を守る社会的責任があります。
さらに、健康志向の高まりを受けて、禁煙に積極的な企業が社会的に評価される傾向も強まっています。健康経営の観点からも、禁煙対策の実施は従業員の健康促進や職場環境の改善につながる重要な施策といえるでしょう。
【参照】厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」|厚生労働省
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
会社が禁煙対策をするメリット
企業が禁煙対策を進めることは、従業員の健康を守り、企業価値の向上につなげる有益な手段のひとつです。ここからは、会社が禁煙対策をするメリットについて紹介します。
従業員の健康維持につながる
企業が禁煙対策をすることは、従業員の健康維持に貢献します。禁煙対策を行うことで、喫煙率が低下し、従業員の健康被害を減らすことが期待できるでしょう。
喫煙は、肺がんをはじめとするさまざまながん、心臓病や脳卒中などの循環器疾患、喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの呼吸器疾患などにかかるリスクを高めます。これらの健康リスクが高まると、従業員の体調不良や病欠、離職などが増加し、労働生産性の低下や労働力の減少につながりかねません。そのため禁煙対策は、従業員の健康維持に加え、企業の生産性向上や持続可能な職場環境の構築のためにも重要な取り組みです。
法的なリスクを回避できる
企業が禁煙対策を講じることは、法的リスクを回避するために欠かせません。適切な禁煙対策を講じなかった事業者に対しては、法的な罰則が生じる可能性もあります。
例えば、健康増進法では、喫煙室の設備が基準を満たしていない場合などに、最大50万円の過料が科せられることもあります。また、企業が十分な受動喫煙対策を行わなかった場合、従業員からの通報や、従業員の健康が害されたとして安全配慮義務違反にもとづく訴訟のリスクもあるため、適切な対策を実施することが重要です。
企業イメージの向上につながる
禁煙対策を実施することで、企業は健康意識の高い職場環境を提供していることを対外的にも示せます。特に近年では、企業の社会的責任や持続可能な経営への取り組みが注目されています。禁煙対策に取り組むことで、従業員の健康に配慮する企業としての姿勢が明確になり、社内外からの信頼獲得につながるでしょう。これにより、取引先や求職者からの評価が高まり、企業のブランド価値の向上が期待できます。
健康経営優良法人の認定を受けやすくなる
禁煙対策は、企業のブランド価値を高めるだけでなく、健康経営の推進にもつながります。例えば、健康経営優良法人認定制度では、従業員の健康管理を経営戦略の一環として重視する企業が評価されます。この制度において、禁煙対策は、認定を受けるための評価項目のひとつです。
認定要件には、「受動喫煙対策に関する実施」や「喫煙率低下に向けた取り組み」などが含まれており、企業がこれらに積極的に取り組むことで、認定取得の可能性が高まります。また、認定を受けることで、企業は公的な評価を得られるだけでなく、採用力の向上や補助金の活用、金融機関からの優遇措置といった実質的なメリットも享受できます。
【参照】政府広報オンライン「屋内は原則禁煙!受動喫煙防止のルールを守りましょう」|内閣府大臣官房政府広報室(2024年10月1日)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201907/2.html
【参照】厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙 改正法のポイント」|厚生労働省
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/
【参照】株式会社日本総合研究所「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)今年度の概要」|株式会社日本総合研究所
https://kenko-keiei.jp/wp-content/uploads/2024/09/applicationvideo2025_chusho.pdf
社員に禁煙を求めることへの違法性の有無
企業が従業員に対して禁煙を求める際、法的に問題がないか気になる方も多いでしょう。結論として、就業時間中や社内での禁煙を義務付けることは違法ではありません。企業には職場環境を適切に管理する権限があり、労働者にも業務時間中に職務に専念する義務があるため、喫煙による離席を制限することは合理的とされています。また、改正健康増進法により、職場での受動喫煙対策は企業の義務となっており、禁煙ルールの明確化は法的に正当性があるといえます。
一方で、休憩時間や就業時間外の喫煙まで企業が禁止することは、労働者の私生活に介入する行為とみなされ、違法となる可能性もあるため注意が必要です。そのため、就業時間外の禁煙を促進する場合は、禁煙外来の費用補助や禁煙支援プログラムの提供など、強制ではなく支援の形で進めることが大切です。
会社における禁煙対策
企業が禁煙対策を実施する際には、禁煙のルールを設け、設備を整えるなどの仕組みづくりが求められます。ここからは、企業が実施すべき具体的な禁煙対策について解説します。
禁煙ルールを明確にする
企業における禁煙対策では、まず社内の禁煙ポリシーを明確化し、従業員に周知することが重要です。就業規則や職場の衛生管理マニュアルなどに「勤務時間中の喫煙禁止」「オフィス内全面禁煙(喫煙専用室の設置可否)」「敷地内の喫煙場所の指定」などを明文化し、全従業員が理解しやすい形でルールを設定しましょう。
また、違反時の対応も明確にすることで、ルールの徹底が図れます。例えば、「社内禁煙ルールを破った場合の懲戒手続を設ける」「違反者には段階的な指導を行う」といった対策を就業規則に記載することで、実効性が高まります。ルール策定後は、従業員への周知も欠かせません。
喫煙所を設ける
完全禁煙を実施するのが難しい場合は、喫煙専用のスペースを設置することで、受動喫煙の影響を最小限に抑えることが可能です。ただし、改正健康増進法では、喫煙室の種類ごとに厳格な基準が設けられています。
例えば、「喫煙専用室」では喫煙のみ可能で、飲食は禁止されています。一方、「加熱式たばこ専用喫煙室」では加熱式たばこの喫煙に加え、飲食も可能ですが、紙巻きたばこは吸えません。企業が喫煙所を設置する際は、換気設備の基準や分煙措置など、法律で定められた技術基準を満たすことが求められます。
喫煙エリアに年齢制限をかける
改正健康増進法では、喫煙エリアには20歳未満の者の立ち入りが禁じられています。企業が敷地内に喫煙所を設ける場合は、20歳未満の従業員や来訪者が喫煙エリアに立ち入らないよう対策を取らなければなりません。企業が適切な管理を怠った場合、行政指導や行政処分の対象となる可能性があります。
そのため、喫煙所の入り口には「20歳未満立入禁止」の標識を掲示する必要があります。また、未成年者が誤って喫煙所に立ち入らないよう、物理的な仕切りを設けたり、管理者を配置したりするなどの対策を講じることが望ましいでしょう。喫煙エリアを適切に管理し、未成年者の健康を守る環境を整えることも企業の責任のひとつです。
喫煙者に対する禁煙サポート
禁煙対策を進める際には、喫煙者が禁煙しやすい環境を整えることも重要です。企業が提供できる具体的な支援策には、禁煙外来の費用補助、禁煙セミナーの実施、ニコチンパッチやガムなどの禁煙補助用品の提供、医療機関などと連携した禁煙プログラムの導入などがあります。これらの支援を取り入れることで、禁煙を促進し、健康的な職場環境の実現につながるでしょう。
【参照】厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙 改正法のポイント」|厚生労働省
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/
会社で受動喫煙を防止する取り組みの進め方
受動喫煙は、喫煙者本人だけでなく、周囲の人々の健康にも悪影響を及ぼすため、企業には適切な対策が求められます。厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」にもとづき、企業が講じるべき具体的な進め方を紹介します。
推進計画を策定する
まず、企業は自社の職場環境を把握し、受動喫煙防止のための計画を策定することが重要です。社内の喫煙状況や従業員の意識調査を行い、どのような対策が必要かを明確にした上で方針を決定します。また、将来の達成目標や達成時期も明確にしておくことが大切です。
担当部署を指定する
企業は、受動喫煙防止対策を進めるために、担当部署や責任者を決めましょう。担当者は、職場の状況を定期的に確認し、問題があれば改善を指導します。また、その結果を経営幹部や衛生委員会に報告し、職場ごとに適切な対策を決定することが求められます。
対策を定期的に確認する
受動喫煙防止は、職場の安全衛生管理の一環として位置付けられています。企業は衛生委員会などを活用し、受動喫煙の状況を定期的に議論することが大切です。また、産業医が職場を巡視する際には、受動喫煙対策がしっかり実施されているかを確認し、必要に応じて改善を促すことが求められます。
喫煙場所の標識を設置する
企業が喫煙専用室などを設置する場合、出入口や施設の目立つ場所に標識を掲示することが義務付けられています。喫煙可能な場所を明確にすることで、従業員や来訪者の受動喫煙を防ぎ、安心できる職場環境を整えることが大切です。
従業員への啓蒙や情報提供を行う
企業は、従業員に対して受動喫煙の健康リスクや防止対策についての教育を行い、意識向上を促すことが求められます。社内研修やポスター掲示などを活用した情報発信など、継続的な啓発活動を実施すると効果的です。
求人募集で受動喫煙防止対策を明示する
企業は、求人募集の際に職場の受動喫煙対策を明示することが求められます。例えば、敷地内全面禁煙、屋内禁煙・喫煙所設置、屋内喫煙可などの情報を事前に提示することで、求職者が職場環境を正しく理解し、安心して応募できるようになります。
【参照】厚生労働省「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」|厚生労働省(2019年7月1日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf
会社の禁煙対策に関する助成金
禁煙対策を進めたい企業にとって、費用面の負担は大きな課題となることがあります。そこで活用できるのが、中小企業事業主を対象とした受動喫煙防止対策助成金です。この助成金は、職場での受動喫煙防止を目的とした施設整備にかかる費用の一部を補助する制度です。
申請可能となるのは、資本金または従業員数が一定以下の企業で、業種ごとに基準が異なります。また、改正健康増進法にもとづき、適切な喫煙対策を講じることが求められるため、申請の際には計画を明確にして、事前に要件を確認しておくことが重要です。詳細な基準や申請条件については、厚生労働省の公式ページで最新情報を確認しましょう。
【参照】厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)」|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
企業の禁煙対策は健康経営の第一歩
企業における禁煙対策は、単なる健康管理の一環だけではなく、従業員の健康維持や生産性向上、法的リスクの回避、企業イメージの向上に貢献する重要な取り組みです。改正健康増進法により、受動喫煙対策は企業の義務となっており、適切な対応が求められています。
従業員の健康を守ることは、企業の持続的な成長にもつながります。法令を遵守しながら、働きやすい環境を整えるために、計画的に禁煙対策を進めていきましょう。
「マイナビ健康経営」は、人と組織の「ウェルネス(健康)」をさまざまなサービスでサポートしています。会社の禁煙対策についても、お気軽にご相談ください。
【免責及びご注意】 |
<監修者> |
&res=1280x720&is_new_uid=true&_tcuid=202504041405251191&_tcsid=202504041405256705)