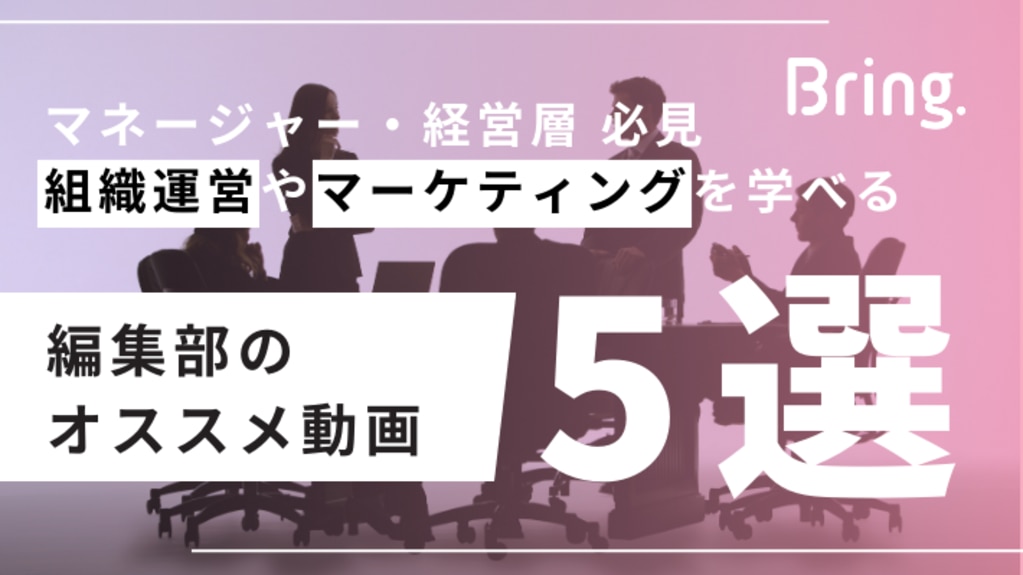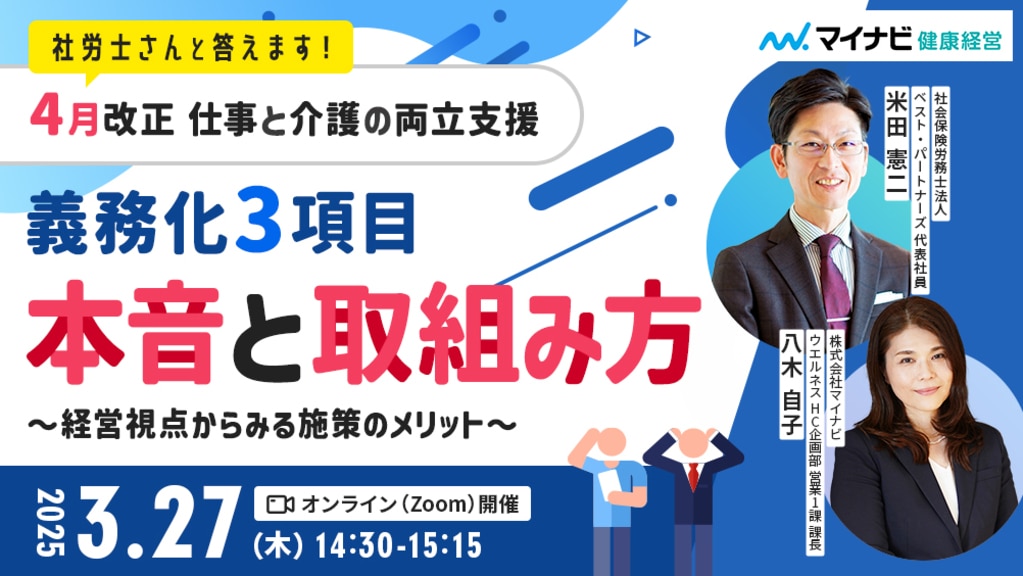出向者の給与はどう決める?企業間での取り決め、負担例を解説
グループ会社や子会社、人手不足の企業などに、自社の社員を人事異動で配置するのが「出向」です。コロナ禍をきっかけに、雇用が過剰になった企業と、市場の需要が増加して人手不足に陥った企業とのあいだで、人材をシェアする目的で出向の活用は注目されるようになりました。
出向契約を結ぶにあたって知っておきたいのが、出向の対象となる従業員の給与についてです。ここでは、給与の決め方や、出向形態ごとに異なる給与負担の例について解説します。
目次[非表示]
出向社員の給与を負担するのは出向元?出向先?
出向契約の対象となる従業員の給与は、出向元企業、出向先企業のどちらが支払うべきなのでしょうか。税務上は、出向元が出向者に支払う給与額に準じた金額を担い、出向先が給与負担金を出向元に支払う「応益負担」が原則です(※)。 しかし、出向の背景も多岐にわたるため、給与の取扱方法はひとつではありません。出向の形式が転籍出向か、在籍出向かによっても異なります。 ※応益負担の原則…享受する労働力に応じて費用を負担する考え方。出向者は100%の労働力を出向先で提供しているので、出向元が給与を負担する必要があるとする。 【参照】全国商工団会連合会「やさしい税務Q&A」|全国商工団会連合会(2018年7月) https://www.shokokai.or.jp/shokokai/pdf/201807/54-55_%E5%95%867_%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%9B%B8%E8%AB%87.pdf
転籍出向者への給与の取扱方法
続いては、給与の取扱方法はどのような種類があるのか見ていきましょう。 転籍出向は、出向元との雇用契約を終了して出向先と雇用契約を結びます。出向が決まった時点で出向元との関係は消失するため、出向元企業を退職して転職するのと同じだといえるでしょう。出向後、出向元は出向者に関する責任を負わないので、転籍出向の場合の給与はすべて出向先企業が支払います。 出向後の給与額は出向先企業の水準に合わせて設定されますが、本人の同意なく転籍出向を実行することはできません。企業は、出向先企業での労働条件について丁寧に説明し、必ず同意を得る必要があり、出向を打診された従業員には自分が不利となる出向命令を拒否する権利があります。
在籍出向者への給与の取扱方法
在籍出向は、出向元企業に籍を置いたまま、期間満了後は出向元に戻ることを前提として出向先企業とも雇用契約を結ぶ形です。この場合、前述した応益負担の原則にもとづいて、労働力の提供を受ける出向先企業が給与を負担するのが一般的でしょう。 ただし、同一条件の労働に対して、出向元と出向先で給与水準が異なる場合には注意が必要です。この場合の対応は、3つに分かれます。
- 出向元が給与を支給 出向後も籍を置く出向元企業が出向者に給与を支給します。出向先企業の給与水準が高い場合、その差額分は出向先企業から出向元企業に支払われます。
- 出向先が給与を支給 出向先企業が出向者に給与を支給します。出向元企業の給与水準が高い場合、その差額分は出向元企業から出向先企業に支払われます。
- それぞれの企業で給与負担をする 出向元企業、出向先企業、それぞれが従業員の給与を負担します。負担の割合は話し合いによって決まります。
【参照】厚生労働省「在籍型出向「基本がわかる」ハンドブック(第2版)」|厚生労働省(2021年11月) https://www.mhlw.go.jp/content/000739527.pdf
【あわせて読みたい】
出向の形態による給与負担の例
出向の形態には、「要員調整型」「業務提携型」「実習型」「人事交流型」といったものがあります。続いては、従業員の出向の形態ごとに、給与負担の例を見ていきましょう。
要員調整型
要員調整型とは、社会的な問題や季節要因によって休業や事業縮小を余儀なくされ、人員が過剰となった企業から、人手不足の異業種に従業員を出向させるタイプの出向です。コロナ禍で便を減らした航空会社から、巣ごもり需要の増加で人手不足となった物流分野への出向などがこれにあたります。
この場合、出向元企業・出向先企業ともに雇用調整が目的であり、どちらにとってもメリットがあります。そのため、給与の支払いについては、出向の目的、出向先の費用負担能力などを踏まえて、企業間の話し合いによって決まることが多いでしょう。
業務提携型
業務提携型とは、業務提携をしている、または今後業務提携を予定している企業への出向を指します。出向元の従業員に知見や技術を習得させる目的なのか、業績不振の提携先に自社が持つ技術などを伝えることが目的なのかによって、最適な給与負担の方法は異なります。
要員調整型と同じように、状況を勘案して決定するのが望ましいでしょう。
実習型
実習型とは、出向先企業での実習を通じ、技術やノウハウを習得することを目的として従業員を出向させるケースを指します。この場合、従業員は「出向先企業にお世話になる」形のため、出向元が給与を支払うことがほとんどです。
人事交流型
人事交流型とは、出向元と出向先の人的交流を目的とした出向です。この場合、どちらの企業にもメリットがあるため、負担割合などは相談の上で決定します。
なお、出向で従業員の労働条件が変わった場合、企業によっては「出向手当」を支給することがあります。厚生労働省が公表している「平成30年賃金事情等総合調査」によれば、出向手当制度を導入して従業員をサポートしている企業は、197社中89社(45.2%)に上りました。
【出典】中央労働委員会「平成30年賃金事情等総合調査」|中央労働委員会(2018年)
https://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/chingin/18/dl/03.pdf
出向社員の給与負担に関する税制上の留意点
出向契約が成立し、出向する従業員の給与を出向元企業が支払う場合、出向先企業から出向元企業に「給与負担金」として出向者の給与相当額が支払われます。この給与負担金の金額が、本来の労働に対する対価を超え、その金額に妥当な理由がないと判断された場合、課税対象になるので注意してください。
例えば、出向した従業員の月給が30万円で、これを出向元が全額負担すると仮定します。これに対して、出向先企業が出向元企業へ30万円の給与負担金を支払った場合は、その30万円は給与として扱われ非課税です。
しかし、出向元企業が支払う給与より多い40万円の給与負担金が支払われた場合、差額となる10万円に合理的な理由がない限り、寄付金扱いで課税対象となります。
課税対象となるか否かの判断ポイントは、「業務提供にもとづいている出向に対する対価(給与)であるかどうか」です。
出向によって技術やノウハウを出向先企業に提供する「経営指導料」など、客観的に妥当な説明ができ、かつ適正な金額であれば、出向元企業の損金に算入されて課税関係が発生しないことがあるでしょう。
なお、課税対象となる否かは、個別に判断されるので、不明な点は最寄りの税務署にお問い合わせください。
【参照】国税庁「第9款 転籍、出向者に対する給与等」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_09.htm
出向者に支払う給与の「較差補填金」とは?
出向契約を結ぶ際、出向元企業の給与額に比べて出向先企業の給与額が低いことがあります。このとき、差額分を出向元企業が補填することによって、就労の継続を図るのが「較差補填金」です。
較差補填金は、海外の法人や子会社に従業員を出向させた場合や、新設法人に出向させた場合などに支払われます。較差補填金はどのような状況で必要となるのか、具体的に見ていきましょう。
較差補填金が必要となる背景
海外法人や子会社に従業員を出向させた場合、赴任支度金、本人および家族の語学研修費用、フライト代、現地での住居費、子供の教育費など、さまざまな費用がかかります。出向先にもよりますが、こうした費用をすべて合わせると相当な金額になるため、例えば子会社のみで全額を担うのは負担が大きいでしょう。
また、新設法人でも、出向者の現在の給与額をそのまま負担する余裕がないことも考えられます。こうした場合、出向元が差額を較差補填金として支払い、出向元の法人の損金の額に算入するのが一般的です。
しかし、海外の現地法人や子会社に出向している従業員への較差補填金は、企業への寄付金とみなされ、損金に算入できない可能性もあります。
その際は、較差補填金の支払いが下記のような状況によるものかどうか確認してみてください。これらの状況では、寄付金とみなされない場合もあります。
<較差補填金が寄付金とみなされない可能性のある状況>
- 国内勤務において支給される給与額との差額を補填するものである
- 出向先が経営不振などで賞与の支給ができず、代わりに出向元が支給する
- 出向先が海外のため、出向元が留守宅手当を支給する
較差補填金が寄付金とみなされるには、理由があります。本来、海外で働いて生んだ成果に対する報酬は海外法人が支払うべきであり、国外源泉所得となるものだからです。
【参照】国税庁「出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い」|国税庁(2021年4月)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5241.htm
残業代、賞与、退職金の支払いはどう取り決める?
出向において、給与以外に支給される残業代、賞与、退職金といった費用の支払いは、どうすべきなのでしょうか。どの種類の手当を、出向元企業と出向先企業、どちらが支払うべきか迷うことは多いはずです。
ここでは、手当の種類ごとに、支払いの一般的な取り決めを見ていきましょう。
残業代
残業代をどちらの企業が支払うかは、出向元企業と出向先企業の話し合いによって決定します。出向元企業が負担する場合、出向先での勤務時間や休憩時間に準じて支払うことが多いです。
賞与
賞与額についても、基本的には出向元企業と出向先企業の話し合いにもとづいて決定します。しかし、賞与は企業が一定以上の利益を上げた場合に、査定にもとづいて配分されるものであり、労働力の提供を受けた出向先企業が支払うのがスマートな形だといえるでしょう。
出向元企業の賞与額と差がある場合は、出向元企業が補填額を支払うなど、細かい部分も出向契約で取り決めておくことをおすすめします。
退職金
在籍出向の場合、企業の事情で出向をしていた従業員には、出向元企業・出向先企業での勤務期間を合わせて、出向元企業が退職金を支払うことが多いでしょう。
転籍出向の場合、出向が決まった時点で出向元企業が退職金を支払うか、出向先企業を退職する際に出向元企業の勤続年数を加味して出向先企業が支払うか、大きく2つに分かれます。
出向元・出向先でよく話し合い、給与ギャップをなくそう
出向する従業員の給与については、出向元企業で支給されていた金額と、出向先企業で支給される金額に大きな差がない状態が理想です。
「出向した途端、給与額が減った」となれば、「評価されていない」と感じた従業員のモチベーションは低下してしまうでしょう。出向が決まったら、事前に出向元と出向先でよく話し合い、出向する従業員の働きに見合った金額を支給するようにしてください。
出向支援でご希望に合う人材が見つからない場合や、より専門的なスキルが必要な場合は、
「マイナビプロ人材活用」サービスもご活用いただけます。
【免責及びご注意】 記事の内容は公開日当時のものです。当社では細心の注意を払っておりますが、実践の際には所轄の税務署など各専門機関でご確認の上、ご検討・ご対応をお願い致します。万一、内容について誤りおよび内容に基づいて被った損害について、当社では一切責任を負いませんのでご了承ください。 |
<監修者> 丁海煌(ちょん・へふぁん)/1988年4月3日生まれ。弁護士/弁護士法人オルビス所属/弁護士登録後、一般民事事件、家事事件、刑事事件等の多種多様な訴訟業務に携わる。2020年からは韓国ソウルの大手ローファームにて、日韓企業間のМ&Aや契約書諮問、人事労務に携わり、2022年2月に日本帰国。現在、韓国での知見を活かし、日本企業の韓国進出や韓国企業の日本進出のリーガルサポートや、企業の人事労務問題などを手掛けている。 |
&res=1280x720&is_new_uid=false&_tcuid=202504031110536553&_tcsid=202504031110534514)