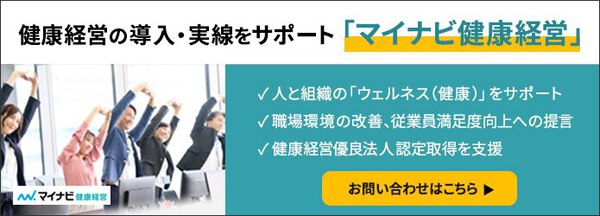なでしこ銘柄とは?選定基準や申請の流れ、認定のメリットなどを解説
ビジネスのグローバル化や労働人口の減少などを背景として、年代や性別、国籍などを問わずあらゆる人の雇用や活躍の場を広げるダイバーシティが推進されるようになっています。その一環として、女性の活躍の場を広げたいと考えている企業も多いのではないでしょうか。
ダイバーシティを推進するため、経済産業省が東京証券取引所と共同で実施しているのが、女性活躍推進に優れた上場企業を選定する「なでしこ銘柄」です。なでしこ銘柄に選定された企業は、上場企業の中でも優れた業績を残しており、それらの取り組みは企業価値向上にも寄与します。
本記事では、2024年新設の「Nextなでしこ」と併せて、なでしこ銘柄の概要や選定基準、申請の流れなどについて解説します。
目次[非表示]
- 1.なでしこ銘柄とは、女性活躍推進のリーダー企業を評価する仕組み
- 2.2025年度版なでしこ銘柄における評価のポイントと取り組み
- 2.1.企業に求められる取り組み
- 2.2.テクロノジーを活用した業務運用を推進する
- 3.「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」の概要とポイント
- 4.「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」で押さえておくべきポイント
- 5.なでしこ銘柄とNextなでしこが拓く日本の未来
- 6.なでしこ銘柄の申請の流れ
- 7.なでしこ銘柄の認定を受けるメリット
- 7.1.「注目企業」として経済産業省のレポートに公表される
- 7.2.市場評価が上がる可能性がある
- 7.3.業務パフォーマンスの向上が期待できる
- 7.4.企業ブランディングの一助になる
- 7.5.従業員満足度が向上する
- 8.なでしこ銘柄企業の成功事例とその成果
- 8.1.株式会社技研製作所の事例:女性役員がさまざまな経営課題の解決に参画
- 8.2.アサヒグループホールディングス株式会社の事例:あらゆる意思決定の場に女性が参画
- 8.3.株式会社資生堂の事例:2023年時点で女性管理職比率37.6%を達成
- 8.4.伊藤忠商事株式会社の事例:残業体質の解消や環境整備の徹底を行い、出生率が平均以上に
- 9.「なでしこ銘柄」「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」は健康経営の観点からも重要
なでしこ銘柄とは、女性活躍推進のリーダー企業を評価する仕組み
なでしこ銘柄とは、経済産業省と東京証券取引所が2012年度から共同で実施している制度です。女性活躍推進に取り組む上場企業を選定し、中長期的な価値の向上が期待できる企業として投資家に紹介することで、企業への投資促進を狙いとしています。
なでしこ銘柄の選定は、投資活動の活性化を促すとともに、企業における女性活躍推進の取り組みを前進させることも目指しており、2024年度で12回目を迎えました。
女性活躍に焦点を当てた取り組みの背景には、経済のグローバル化、少子高齢化による労働人口の減少、仕事に対する価値観の多様化などが挙げられるでしょう。
企業は経営のトレンドに乗り遅れないために、そして深刻化する人材不足に対応するためにも、国籍や人種、性別などにとらわれずに人材を雇用し、その活躍を促進するダイバーシティに取り組むことが一層、求められます。
経済産業省は、ダイバーシティを全社的かつ継続的に進めていく経営上の取り組みを「ダイバーシティ2.0」と定義し、「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」の中で実践のためのアクションを取りまとめています。なでしこ銘柄も、同ガイドラインの考え方を軸に調査・実施されてきました。
【参照】経済産業省「令和4年度「なでしこ銘柄」レポート」|経済産業省(2023年3月)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/R4nadeshikoreport.pdf
2025年度版なでしこ銘柄における評価のポイントと取り組み
2025年度版なでしこ銘柄は、2024年8月より選定が開始されています。経済産業省が公表している「令和6年度 なでしこ銘柄募集要項」によれば、評価で重視されるポイントは下記の2点です。
<なでしこ銘柄で重視される評価のポイント>
・「採用から登用までの一貫したキャリア形成支援」及び「共働き・共育てを可能にする性別を問わない両立支援」に関する取組・成果が、どちらも優れていること
・経営戦略と女性活躍を含む人材戦略との結びつき、それによる企業価値向上が自社独自のストーリーとして語られていること
ここからは、なでしこ銘柄を目指す上で求められる取り組みについて見ていきます。
【参照】経済産業省 令和6年度「なでしこ銘柄」事業事務局「令和6年度「なでしこ銘柄」募集要領【本編】」|経済産業省(2024年8月)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/r6bosyuyoryo.pdf
企業に求められる取り組み
上記の評価ポイントを踏まえて、なでしこ銘柄を目指すにはどのような取り組みが必要となるのでしょうか。なでしこ銘柄の選定には、時流を踏まえた実効性の高い施策が重視されることから、働く人が自身の事情に応じて柔軟な働き方を選択できるようにする「働き方改革」は当然ながら求められます。また、女性の社会的・文化的地位の向上を目指すSDGsの17つの目標の「5」に該当する「ジェンダー平等」などを意識した制度も、押さえておきたい取り組みといえるでしょう。
当然ながら、ライフステージの変化によってキャリアの幅が狭まったり、就業の継続をあきらめたりするような環境であるならば是正をするべきです。仕事と家庭を両立した上で女性が真に活躍できる環境をつくることは、サステナブルな社会の実現に向けた第一歩です。
人手不足の深刻化が予想される中、企業が存続していくためにも、多様な働き方を支える独自性のある取り組みを進めることが重要といえます。
テクロノジーを活用した業務運用を推進する
なでしこ銘柄を目指した取り組みとして、テクロノジーを活用した業務運用の推進も挙げられます。例えば、テレワーク環境の推進やITツールによる社内業務の運用見直しなど、テクノロジーを活用した働き方を推進することで、育児中の業務負担を軽減することにつながります。
こうした就業環境の整備は、なでしこ銘柄の評価のポイントである「共働き・共育ての支援」や「全ての従業員を対象とする柔軟な働き方を可能とした環境」の推進につながるため、積極的な検討が求められるでしょう。eラーニングなどを活用して、自宅で就業しながら知識を補える環境を整備することもおすすめです。
【参照】令和6年度「なでしこ銘柄」事業事務局「令和6年度「なでしこ銘柄」募集要領【本編】」|経済産業省(2024年8月)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/r6bosyuyoryo.pdf
「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」の概要とポイント
「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」とは、「共働き・共育てを可能にする男女問わない両立支援」が特に優れた企業のことです。
経済産業省は、企業価値向上につながる女性活躍を実現するために、「採用から登用までの一貫したキャリア形成支援」と「共働き・共育てを可能にする性別を問わない両立支援」を両輪で進めていく必要があるとしています。
そこで、令和5年度(2023年度)のなでしこ銘柄選定では後者に関する調査項目を増やし、「共働き・共育てを可能にする性別を問わない両立支援」に関する取り組みが特に秀でていた企業を「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」に選定しました。
令和6年度(2024年度)も同様に、「なでしこ名柄」とは別枠で20社程度が「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」に選定される予定です。
【参照】経済産業省「女性活躍に優れた上場企業を選定「なでしこ銘柄」」|経済産業省(2024年9月)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/nadeshiko.html
「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」で押さえておくべきポイント
「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」として選定されるには、女性従業員の産休・育休後の復職やキャリア構築の支援、男性の育休取得促進など、女性のキャリア中断を防ぐ取り組みが重要となります。
出産・育児を希望することでキャリアが中断されるような状況は、女性活躍が進まない大きな原因の1つだからです。
経済産業省は、「共働き・共育てを可能にする性別を問わない両立支援を推進している」こと、そして「共働き・共育てをする従業員に限らず、全ての従業員が自分の望む働き方を選択できる環境づくりを推進している」といった点を「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」評価のポイントとしています。
なお、これの評価ポイントは、必ずしも女性を対象としたものではない点は押さえておきましょう。制度の利用者が女性に集中することによって、結果的に女性が仕事と家事育児の両立を図らなければならない事態は避けなければなりません。共働きのパートナーがそれぞれ希望するキャリアと子育てを両立するための支援であることが重視されています。
なでしこ銘柄とNextなでしこが拓く日本の未来
停滞が続く日本経済の起爆剤として、女性の労働者数の増加は欠かせない命題だといえます。潜在的な労働力として大きな可能性を秘めている女性の社会進出が進まなければ、少子高齢化で労働力不足が進む人口構造の変化に対応することは困難です。
一方、2024年に総務省統計局が公表した労働力調査によれば、調査週間中に少しも仕事をしなかった非労働力人口3,997万人のうち就業希望者数(就業を希望しているが、求職活動をしていない者)は234万人で、うち153万人が女性でした。また、今よりもっと働きたいと考える追加就労希望就業者数195万人のうち131万人も女性であり、単純計算で280万人以上の女性が就業を希望していることになります。
ダイバーシティの推進によって女性活躍の可能性を拡充することは、企業の労働力不足はもちろん、日本社会の未来をも切り拓く取り組みになるといえるでしょう。企業は取り組みを進めるとともに、社内に残るジェンダー差別意識を解消し、制度としても、風土としても平等に女性を評価できる環境をつくっていくことが求められています。
【参照】総務省「労働力調査(詳細集計)2024年(令和6年)4~6月期平均」|総務省(2024年8月)
https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/4hanki/dt/pdf/gaiyou.pdf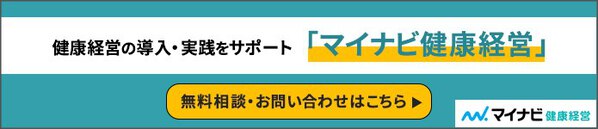
なでしこ銘柄の申請の流れ
「なでしこ銘柄」、「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」の申請については、いずれかのみの応募も、両方への応募も可能です。ただし、なでしこ銘柄に選定された企業は、「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」の選定からは外れます。
ここでは、「なでしこ銘柄」と「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」に申請する際の流れについて見ていきましょう。
<申請から選定までの流れ>
-
令和6年度女性活躍度調査に回答し、メールで提出
選定の対象となるのは、プライム市場、スタンダード市場、グロース市場に上場している全ての企業です。
なでしこ銘柄に応募する場合は、共通調査票に加えて、なでしこ銘柄調査票も記入し、メールで提出します。「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」のみに応募する際は、共通調査票への回答のみで済みます。
-
審査
全上場企業約3,900社から応募があった企業をスクリーニングし、審査対象企業を絞り込みます。その後、提出された調査票をもとにスコアリングし、審査が行われます。
「なでしこ銘柄」は30社程度(18業種各1~2社程度)、「Nextなでしこ共働き・共育て支援企業」は20社程度(18業種各0~2社程度)が選定される予定です。
「なでしこ銘柄」、「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」選定発表までのスケジュール
令和6年度「なでしこ銘柄」と「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」のスケジュールは下記のとおりです。
■選定発表までのスケジュール
日時 |
プロセス |
2024年8月 |
応募開始 |
2024年10月 |
応募締め切り |
2024年10月~2025年2月 |
審査 |
2025年2月下旬~3月上旬 |
選定企業決定、担当者にメール通知 |
2025年3月下旬 |
ロゴマーク送付、発表会実施・選定企業公表 |
【参照】令和6年度「なでしこ銘柄」事業事務局「令和6年度「なでしこ銘柄」募集要領【本編】」|経済産業省(2024年8月)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/r6bosyuyoryo.pdf
なでしこ銘柄の認定を受けるメリット
なでしこ銘柄の認定を受けると、さまざまなメリットがあります。ここでは、大きく5つのメリットを紹介します。
「注目企業」として経済産業省のレポートに公表される
なでしこ銘柄に選定された企業は、「注目企業」として経済産業省のレポートに記載されます。経営戦略の中心に女性活躍を位置づけ、ダイバーシティ経営を実践していることを広く社会にアピールできます。
市場評価が上がる可能性がある
経済産業省が発表した総評レポートによれば、なでしこ銘柄に選定された企業の株価指数は、TOPIX(東証株価指数)よりも高い傾向にあることがわかっています。投資判断において女性活躍を重視する投資家は多いため、なでしこ銘柄の選定は自社の市場評価の向上につながる可能性があります。
【参照】令和6年度「なでしこ銘柄」事業事務局「令和6年度「なでしこ銘柄」募集要領【本編】」|経済産業省(2024年8月)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/r6bosyuyoryo.pdf
業務パフォーマンスの向上が期待できる
なでしこ銘柄に選定される企業は、社内制度の見直しや、業務システム改善など、働く環境が整備されるため、業務パフォーマンスの向上が期待できます。
2023年度なでしこ銘柄に選定された企業27社の売上高営業利益率を東証プライム銘柄の平均値と比較すると、なでしこ銘柄選定企業は市場の平均値を3.2%ポイント上回りました。配当利回りに目を移しても、プライム市場平均と比較して2.5%ポイント上回っています。
【参照】令和5年度「なでしこ銘柄」事業事務局「令和5年度「なでしこ銘柄」レポート」|経済産業省(2024年3月)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/r5nadeshikoreport.pdf
企業ブランディングの一助になる
なでしこ銘柄に選定されると、「女性に優しい企業」「従業員の働きやすさに配慮している企業」として自社のブランディングを確立できます。なでしこ銘柄は、充実した女性活躍推進の取り組みを率先して行っている証となります。そのため、「働きたい」「働き続けたい」と考えている女性をはじめ、就職活動中の学生や転職希望者などに対して好印象を与え、顧客からの評価も高まるでしょう。
従業員満足度が向上する
女性にとって働きやすい職場にすることを目的として見直した制度や環境は、男性の就労環境の改善にもつながることが期待できます。リモートワークの導入や残業の削減、育休取得の推奨などによって男女ともに働きやすい職場環境になれば、従業員満足度の底上げによって離職率の低下や、定着率の上昇も期待できるでしょう。
なでしこ銘柄企業の成功事例とその成果
なでしこ銘柄に選定された企業はどのような施策に取り組んできたのでしょうか。また、それらの施策によって各企業にはどのような成果が生まれたのか、4つの成功事例から見ていきます。
株式会社技研製作所の事例:女性役員がさまざまな経営課題の解決に参画
株式会社技研製作所は、女性役員が初代プロジェクトマネージャーとなり、女性主体の部門横断型プロジェクトを発足。リーダーや管理職に必要なスキルを習得する場として、女性役員がさまざまな経営課題の解決に参画しました。また、目標の1つであった男性育休取得推進は取得率100%を達成し、90日以上の育休期間を取得する社員が全体の8割を超えるなど、性別に限らない働き方の多様化を推進しています。
アサヒグループホールディングス株式会社の事例:あらゆる意思決定の場に女性が参画
アサヒグループホールディングス株式会社は、「女性活躍推進」を目的とした人材戦略において、「女性経営層へのサクセッションプラン策定」「(女性社員の)量の不足分の採用による補完」「(女性管理職の)質の不足分に対する施策と、制度見直しを含む環境整備」を実施。
重要ポストの候補者を育成するサクセッションプランに女性の候補を入れることや、中長期的な経営者の育成と外部からの人材獲得、さらには女性社員向けにリーダーシップ開発・キャリア支援研修を実施することなどによって、戦略を推進しています。
これらの施策の影響によって、意思決定の場に女性が参加することで多様な意見が取り入れられるようになり、2022年グッドデザイン賞の「グッドデザイン・ベスト 100」といったさまざまな賞を受賞するなど、企業価値の向上に寄与しています。
株式会社資生堂の事例:2023年時点で女性管理職比率37.6%を達成
株式会社資生堂は、国内の資生堂グループ全体で女性活躍推進に向けた改革を進めています。具体的には、あらゆるポストにおける女性比率50%、女性社員のキャリア意識向上・昇進意欲85%、男性育児休業取得率100%を指標として掲げています。また、課長層に向けた女性リーダー育成塾「NEXT LEADERSHIP SESSION for WOMEN」などの施策を実践。経営知識の修得をはじめ、自分らしいリーダーシップスタイルの発見や発揮を促しています。さまざまな施策の結果、女性管理職比率は、2023年1月時点で37.6%となっており、2030年には管理職全体の50%が女性となることを目指しています。
伊藤忠商事株式会社の事例:残業体質の解消や環境整備の徹底を行い、出生率が平均以上に
伊藤忠商事株式会社は、2010年から開始した働き方改革で、20時以降の残業を禁止し、早朝勤務を推奨する「朝型勤務」を導入。早朝勤務に対するインセンティブとして割増賃金や軽食配布も行い、残業体質が解消して女性社員が働き続けられる環境が整いました。さらに託児所の設置といった仕事と育児を両立できる環境の整備も進め、その結果、合計特殊出生率は2021年に1.97となり、全国平均を大きく上回りました。
また、2021年には、取締役会の任意諮問委員会として「女性活躍推進委員会」を設置。同委員会は社外取締役を委員長とするほか、委員も半数以上が社外役員となっており、社外の第三者視点を重視して女性活躍推進に取り組んでいる点が特徴です。
【参照】経済産業省「令和5年度「なでしこ銘柄」選定企業事例集」|経済産業省(2023年11月)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/r5nadeshikojirei.pdf
「なでしこ銘柄」「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」は健康経営の観点からも重要
女性活躍の推進と共働き、共育て支援は、女性が活躍できる機会を増やし、日本経済の発展にも寄与する重要な取り組みです。健康経営にもつながる重要な観点であり、社外からの評価や従業員満足度の向上にも効果が期待できるため、この機会にぜひ「なでしこ銘柄」「Nextなでしこ」選定を目指してみてはいかがでしょうか。
「マイナビ健康経営」は、人と組織の「ウェルネス(健康)」をさまざまなサービスでサポートしています。「なでしこ銘柄」「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」の選定につながる女性活躍のための施策についても、お気軽にご相談ください。
&res=1280x720&is_new_uid=true&_tcuid=202504041210111209&_tcsid=202504041210115758)