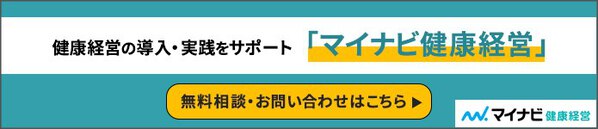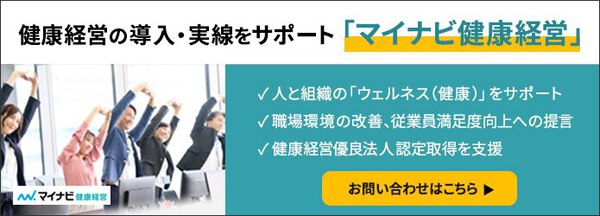ハラスメントとは?定義や種類、関連する法律、企業の対策を解説
近年、社会問題として取り上げられることが多くなったハラスメントは、企業内で放置するとさまざまなリスクを招くおそれがあります。従業員のエンゲージメントが低下して離職が増えるだけでなく、風評被害によるブランドの毀損や企業価値の低下につながる可能性もあります。健康経営の観点からも、ハラスメントに対する適切な対応は欠かせません。
本記事では、ハラスメントの種類と定義、関連する法律、企業における効果的なハラスメント対策について詳しく解説します。
目次[非表示]
- 1.ハラスメントとは、人を不快にさせる嫌がらせやいじめなどの行為
- 2.企業におけるハラスメントの実態
- 3.職場におけるハラスメントの種類
- 3.1.パワーハラスメント(パワハラ)
- 3.2.セクシュアルハラスメント(セクハラ)
- 3.3.マタニティハラスメント(マタハラ)
- 3.4.パタニティハラスメント(パタハラ)
- 3.5.ケアハラスメント(ケアハラ)
- 3.6.モラルハラスメント(モラハラ)
- 3.7.ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)
- 3.8.ロジカルハラスメント(ロジハラ)
- 3.9.テクノロジーハラスメント(テクハラ)
- 3.10.時短ハラスメント(ジタハラ)
- 3.11.アルコールハラスメント(アルハラ)
- 3.12.エイジハラスメント(エイハラ)
- 3.13.リストラハラスメント(リスハラ)
- 3.14.マリッジハラスメント(マリハラ)
- 3.15.ソーシャルハラスメント(ソーハラ)
- 3.16.ハラスメントハラスメント(ハラハラ)
- 4.ハラスメントが企業にもたらすリスク
- 4.1.損害賠償請求や国からの指導・勧告によるレピュテーションリスクがある
- 4.2.従業員の生産性が低下する
- 4.3.人材流出に伴う人手不足
- 4.4.対処のための人件費が発生する
- 5.ハラスメントに関連する法律
- 5.1.労働施策総合推進法(パワハラ防止法)
- 5.2.労働安全衛生法
- 5.3.男女雇用機会均等法
- 5.4.育児・介護休業法
- 5.5.刑法・民法
- 6.ハラスメントを防止するために企業が行うべき措置
- 6.1.企業の方針の明確化・周知・啓発
- 6.2.相談に応じて適切に対応するための体制の整備
- 6.3.ハラスメント事案への迅速で適切な対応
- 6.4.併せて講ずべき措置
- 7.従業員が心身ともに健康に働くために、ハラスメント対策は必須
ハラスメントとは、人を不快にさせる嫌がらせやいじめなどの行為
ハラスメントとは、人を不快にさせる嫌がらせやいじめなどの言動の総称です。職場においては、対象となる相手を傷つけたり、不利益を与えたりすることによって、就業環境を害する行為がハラスメントに該当します。
行為がハラスメントにあたるかどうかは、行為者側の意図ではなく、被害者の受けた影響や就業環境への悪影響によって判断されます。行為者が「コミュニケーションの一環だった」「悪気はなかった」と主張しても、その言動が相手に精神的・身体的苦痛を与え、就業環境を悪化させるものであれば、ハラスメントと認定される可能性があるでしょう。
職場のハラスメントには、「三大ハラスメント」ともいわれるパワーハラスメント(パワハラ)、セクシュアルハラスメント(セクハラ)、マタニティハラスメント(マタハラ)をはじめさまざまな種類があります。
特に、パワハラ、セクハラ、マタハラに加え、パタニティハラスメント(パタハラ)やケアハラスメント(ケアハラ)に関しては、それぞれ特定の法律にもとづいて定義され 、企業に防止措置義務が課されています。
一方、近年耳にすることが増えたモラルハラスメント(モラハラ)や、ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)、アルハラ(アルコールハラスメント)などは、法令で明確に定義されていません。しかし、これらの行為も相手の人権を侵害し、心身に苦痛を与える行為であることには変わりないため、社会通念に照らしてハラスメントと認識されています。状況によっては、行為者や企業が法的責任を問われる場合もあるため注意が必要です。
これらすべてのハラスメントは、内容や影響の程度によって、民法上の不法行為として損害賠償を求められる可能性もあります。企業は、ハラスメントを防止するための対策を積極的に講じ、従業員が安心して働ける職場環境を整えることが重要です。
【参照】厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)「職場におけるハラスメント対策パンフレット」|厚生労働省(2024年11月)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001338359.pdf
企業におけるハラスメントの実態
厚生労働省が2023年度に実施した職場のハラスメントに関する実態調査によれば、「過去3年間にハラスメントの相談があった」と答えた企業におけるハラスメントの内訳は、パワハラ64.2%、セクハラ39.5%、顧客などからの著しい迷惑行為27.9%、妊娠・出産・育児休業などのハラスメント10.2%、介護休業などのハラスメント3.9%でした。ハラスメントが社会問題化し、法整備が進められてきたにもかかわらず、依然としてさまざまなハラスメントが職場内で発生していることがわかります。
また現在、約7割以上の企業で「相談窓口の設置と周知」、約6割以上の企業で「ハラスメントの内容、職場におけるハラスメントをなくす旨の方針の明確化と周知・啓発」が行われています。
一方、6割近くの企業が挙げている課題は「ハラスメントかどうかの判断が難しい」ことです。適切なハラスメント対策を講じるためには、まずハラスメントの種類を理解し、対象となる行為を正確に把握する必要があるでしょう。
【参照】PwC コンサルティング合同会社「令和5年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書(概要版)」|厚生労働省(2024年3月)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001256085.pdf
職場におけるハラスメントの種類
職場で起こるハラスメントには、さまざまな種類があり、それぞれについて適切に理解しておくことが必要です。ここからは、職場で起こる可能性がある16種類のハラスメントについて、概要を紹介します。
パワーハラスメント(パワハラ)
パワハラは、職場における上下関係などの優位性を利用して行われる嫌がらせやいじめなどの言動の総称です。労働施策総合推進法では、以下3つの要素を満たすものをパワハラと定義し、事業者に防止措置を講じることを義務付けています。
<パワハラの要素>
- 優越的な関係を背景とした言動である
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えている
- 当該言動によって労働者の就業環境が害される
また、パワハラの典型的な類型としては、以下6つが挙げられます。
<パワハラの6類型>
- 暴行や傷害などの「身体的な攻撃」
- 脅迫や名誉毀損、侮辱、暴言などの「精神的な攻撃」
- 隔離や仲間外し、無視などの「人間関係からの切り離し」
- 業務上明らかに不要または不可能なことを強制したり、仕事を妨害したりする「過大な要求」
- 仕事を与えない、または能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じるなどの「過小な要求」
- プライベートなことに過度に立ち入る「個の侵害」
パワハラは、必ずしも上司から部下に対して行われるとは限りません。業務を円滑に進める上で相手の協力が不可欠な場合や、集団での圧力によって拒否や抵抗が難しい状況では、同僚や部下が行為者になることもあります。
【おすすめ参考記事】
セクシュアルハラスメント(セクハラ)
セクハラは、法律上、労働者の意に反した性的な言動による嫌がらせによって、労働者の就業環境が害されたり、就業上の不利益を受けたりすることを指します。男女雇用機会均等法において、職場のセクハラに対して防止措置を講じることは事業者の義務です。
職場におけるセクハラは、大きく「対価型」と「環境型」に分けられます。
-
対価型
セクハラを受けた労働者が拒否・抵抗したことにより、解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、不合理な配置転換といった不利益を被る場合です。職場において上司が部下に性的な関係を迫り、拒否されたことを理由に、部下を降格させるなどのケースが対価型の例です。 -
環境型
行為者の性的な言動で労働者の就業環境が害され、意欲や集中力の低下といった業務遂行上の問題が生じる場合です。例えば、同僚が批判や抗議を受け入れず、性的な画像をパソコンの待ち受けに設定しているために仕事に集中できないといったケースがあります。
マタニティハラスメント(マタハラ)
マタハラは、職場において行われる上司・同僚からの言動により、妊娠・出産、育児休業などに関連して労働者の就業環境が害されることをいいます。該当するのは、妊娠・出産の事実、および育児休業などを利用することと、上司や同僚からの嫌がらせとなる言動に因果関係がある場合です。
また、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法により、企業にはマタハラの防止措置を講じる義務があります。
マタハラには、「制度等の利用への嫌がらせ型」と「状態への嫌がらせ型」があります。
-
制度等の利用への嫌がらせ型
産前休業や育児休業をはじめ妊娠・出産や育児に関する制度の利用に対して嫌がらせを行うケースです。例えば「時短勤務になるなら昇進はない」などと、上司や同僚から不合理な扱いを受けるケースなどが挙げられます。または、取得をあきらめざるをえない環境に追い込んだり、雑務ばかりさせたりする場合もそのひとつです。 -
状態への嫌がらせ型
妊娠や出産、育児に伴い、体調や働き方の変化があった女性労働者に対して、直接的かつ継続的に嫌がらせをするものです。「妊娠したら他の人を雇うので早めに辞めてもらいたい」「妊娠するなら忙しい時期を避けてほしかった」などと上司や同僚が声をかけるケースなどが挙げられます。
パタニティハラスメント(パタハラ)
パタニティ(Paternity)は英語で「父性」を表し、パタハラは職場で男性労働者が育児参加のために育児休業や時短勤務制度を利用することに対する嫌がらせや不利益な扱いを指します。育児・介護休業法により、企業はパタハラを防止する措置を講じる義務があります。
具体的には、男性労働者が育児休業や時短勤務などを申請した際に、上司や同僚が「時短で勤務するなら降格だ」「男が育児休業をとる必要があるのか」と言ったり、不条理な人事異動や評価を行ったりするケースなども該当します。
ケアハラスメント(ケアハラ)
ケアハラは、職場において仕事と介護(ケア)を両立する人に対する嫌がらせや不利益な扱いを指します。両立に必要な制度を取得させない、介護に対する無理解から心ない発言をする、といった労働者の就業環境を妨げる言動が該当します。育児・介護休業法により、企業はケアハラに対する防止措置を講じる義務があります。
例えば「介護休業を取得したら出世できない」などと言われたり、介護のための時短勤務を理由に重要なプロジェクトから外したりするといったケースです
モラルハラスメント(モラハラ)
モラハラは、倫理・道徳に反する言葉や態度、文書などによって人の尊厳や人格を傷つける、精神的な嫌がらせです。例えば、職場で同僚の容姿や人間性、能力を否定する発言をしたり、周囲に人がいる場所で部下を過剰に叱責したりするケースが挙げられます。また、特定の同僚を仲間外れにしたり無視をしたりする場合も含まれます。
ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)
ジェンハラは、性別を理由とする、差別的な言動をはじめとした嫌がらせです。例えば「男のくせにこんな目標も達成できないのか」「女なら進んでお茶くみをしろ」というように、性別によって役割を決めつける言動が代表的です。また、性別をもとに昇給や昇進を判断したり、仕事の内容や配分に差をつけたりすることもジェンハラといえます。
ロジカルハラスメント(ロジハラ)
ロジハラは、反論の余地を与えない正論で相手の逃げ場を奪い、精神的な苦痛を与えて自信を奪ったり、不快感を与えたりする嫌がらせです。例えば、ミスをした従業員に対して「いつまでに再発防止策を考え、ミスが再発したらどうするのか」などと過剰に問い詰めたり、部下に意見を言わせておきながら「それは間違っている」と相手の意見を切り捨てたりするケースが挙げられます。
テクノロジーハラスメント(テクハラ)
テクハラは、ITリテラシーが高い人から低い人に対する嫌がらせです。ITリテラシーがないことを直接的に否定する行為や、ITに関する取り扱いが不得手であることがわかっていて業務を押し付ける行為などがこれにあたります。また、ITに関する知識のない従業員が参加する会議で、あえて難解な用語で説明して相手を阻害する行為などもこれにあたります。
時短ハラスメント(ジタハラ)
ジタハラは、働き方改革の一環として勤務時間を強制的に短縮する嫌がらせです。到底終わらない業務量であることをわかっていながら、残業せずに定時退社を強要することによって発生します。例えば、「定時に終わらないのは能力が低いせいだ」と叱責したり、部下が自主的に業務を持ち帰りサービス残業せざるをえない状況を作りながら、それを黙認したりするケースが挙げられます。
アルコールハラスメント(アルハラ)
アルハラは、飲酒に関する嫌がらせや人権侵害です。主に企業の飲み会などの場面で発生します。例えば、組織の上下関係を盾に飲酒を強要したり、場を盛り上げるために一気に飲酒させたりするケースが挙げられます。また、意図的な酔いつぶしや、飲めない人に対するからかい、酔った上での迷惑行為もアルハラのひとつです。
エイジハラスメント(エイハラ)
エイハラは、年齢に関する固定観念や偏見を押しつける差別的な言動や嫌がらせです。例えば、「ゆとり世代は困る」などと、特性の世代を一括りにして侮辱する行為が挙げられます。また、一定の年齢以上の人を「おじさん」「おばさん」と呼んで小ばかにしたり、「もういい年なのに」と揶揄したりする行為も該当します。
リストラハラスメント(リスハラ)
リスハラは、リストラ対象者が自主退職を決断するよう、追い詰める嫌がらせです。例えば、不当な配置転換をしたり、執拗な退職勧奨をしたりするケースが挙げられます。また、意図的に業務負担を増やしたり、執務環境を悪化させたりすることもリスハラのひとつです。
マリッジハラスメント(マリハラ)
マリハラは、結婚にまつわる嫌がらせです。例えば、独身者に対して結婚しない理由をしつこく聞いたり、「結婚するのは当たり前だ」と一方的な価値観を押し付けたりするケースが挙げられます。また、「独身だから休日出勤できるよね」と、未婚を理由に従業員の仕事に不利益をもたらす場合も含まれます。
ソーシャルハラスメント(ソーハラ)
ソーハラは、SNSを通じて行われる嫌がらせです。例えば、職場の上司や先輩からSNSの友達申請をされることで、私生活でも不要な緊張やストレスが生じるケースを指します。また、上司から投稿に対する「いいね」を強要されたり、投稿の内容を職場で勝手に話題にしたりするなどといった例もあります。
ハラスメントハラスメント(ハラハラ)
ハラハラは、企業のハラスメント対策を悪用した嫌がらせです。正当な行為や指導であっても「ハラスメントだ」と過剰に訴えて問題化しようとする行為です。例えば、同じミスを繰り返す部下に上司が注意した場合や、部下のスキルアップのために高い目標を設定する場合などに発生します。
【参照】厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)「職場におけるハラスメント対策パンフレット」|厚生労働省(2024年11月)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001338359.pdf
【参照】厚生労働省 こころの耳「モラルハラスメント」|厚生労働省
https://kokoro.mhlw.go.jp/glossaries/word-1694/
ハラスメントが企業にもたらすリスク
ハラスメントが発生した場合、被害者である従業員はもちろん、未然に防げなかった企業にも大きなリスクがあります。ここからは、ハラスメントが企業にもたらすリスクについて解説します。
損害賠償請求や国からの指導・勧告によるレピュテーションリスクがある
企業にとっては、ハラスメントが発生し、それによる損害賠償請求や行政処分が公になることでブランド毀損や企業価値の低下を招く、レピュテーションリスクが大きな懸念点だといえるでしょう。
ハラスメントの被害者は、安全配慮義務違反(労働契約法5条)または使用者責任にもとづき、企業に対して損害賠償請求を行う可能性があります。また、セクハラ・パワハラ・マタハラ・パタハラ・ケアハラについては、事業者に防止措置を講じることが義務付けられています。措置を講じていないと判断された場合、厚生労働大臣による指導や勧告を受ける可能性があります。
従業員の生産性が低下する
ハラスメントが起こると、被害者や周囲の従業員のモチベーションが低下し、仕事への集中力が欠けるようになります。その結果、ミスやアクシデントが増加し、組織全体の生産性が大幅に低下することで、業務の効率やチームワークにも悪影響を及ぼすでしょう。
人材流出に伴う人手不足
ハラスメントによってメンタル不調者や休職者・退職者が増加すると人手不足となり、業務の遂行が困難になる可能性があります。さらに、企業に対するネガティブな評判が広がることで、新たな人材の採用が難しくなり、長期的な事業運営にも支障をきたすことがあります。
対処のための人件費が発生する
ハラスメント対応は企業の重要な課題ですが、企業の規模によっては調査・対応にあたるリソースの確保が難しいこともあります。そのため外部の専門家に依頼した結果、予期しない人件費が発生し、企業の財務負担となる可能性もあります。
ハラスメントに関連する法律
適切なハラスメント対策を行うため、企業の担当者はハラスメントに関連する法律を把握しておくことが必要です。ここでは、ハラスメントに関連する5つの法律を紹介します。
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)
パワーハラスメントの防止・対策は、2019年に改正された労働施策総合推進法により事業主の義務となりました。この法律では、パワハラ防止措置を講じることが義務化されており、企業は予防策を取る必要があります。また、労働施策総合推進法第30条の2以下の規定は「パワハラ防止法」とも呼ばれます。
労働安全衛生法
労働安全衛生法は、労働者が安全で健康に働ける環境を提供するため、企業に対して多岐にわたる義務を課しています。特に第10条以下において、企業には労働者の安全・衛生に関する管理者・責任者などを設置する義務があります。これらの管理者・責任者がハラスメントの相談窓口となるケースも少なくありません。
男女雇用機会均等法
男女雇用機会均等法は、性別に基づく差別を禁じる法律で、企業には男女平等な雇用機会を提供する責任があります。特にセクハラやマタハラについては、第11条で防止措置を講じる義務が事業者に課されています。また、企業はハラスメント防止のための体制を整え、必要な対応を実施しなければなりません。
育児・介護休業法
育児・介護休業法は、育児や介護と仕事との両立を支援する法律です。育児・介護休業法第25条では、労働者が育児休業や介護休業を取得する際のハラスメントであるマタハラ・パタハラやケアハラが禁じられており、適切な防止策を講じる措置が事業者に求められます。
刑法・民法
ハラスメントが暴行や脅迫、名誉棄損・侮辱、強制わいせつなどに該当する場合、行為者は刑法に照らして刑事責任が問われる可能性もあります。また、行為者は民法第709条にもとづく不法行為として、損害賠償責任を問われることがあり、企業も使用者責任を問われて訴訟提起などをされれば金銭的な損失が生じる可能性もあるでしょう。
【参照】厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)「職場におけるハラスメント対策パンフレット」|厚生労働省(2024年11月)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001338359.pdf
ハラスメントを防止するために企業が行うべき措置
ハラスメント防止のために企業が行うべき措置の内容は、「事業主が雇用管理上講ずべき措置」として厚生労働大臣の指針に定められています。以下の措置を迅速に実施できるよう準備しておきましょう。
企業の方針の明確化・周知・啓発
従業員に対して、職場におけるハラスメントの内容と、「ハラスメントを許さない企業方針」を明確に示しましょう。基本的な姿勢を毅然と伝えることによって、従業員が安心して働ける雰囲気を醸成できるだけでなく、行為者への抑止力にもなることが期待できます。
相談に応じて適切に対応するための体制の整備
ハラスメントは、人によって受け止め方が異なる場合もあり、周囲に助けを求めにくい可能性があります。相談窓口を設け、些細なことでも相談してほしいと従業員に伝えましょう。相談者の気持ちに沿った適切な対応ができるよう、窓口担当者と人事部門が連携を図れる仕組みづくりや、窓口担当者の教育も重要です。
ハラスメント事案への迅速で適切な対応
ハラスメントが起きてしまったら、事実関係を迅速に確認し、すみやかに被害を受けた従業員の心身をケアします。行為者から物理的に遠ざけるなどの対応も必要です。
そして行為者に対しては、ルールにもとづいて厳正に処分するとともに、自身のハラスメント行為について理解させることが大切です。また、ハラスメントへの理解を深める研修の実施など、再発防止に向けた措置を実施しましょう。
併せて講ずべき措置
当事者などのプライバシーを保護するため、必要な措置を講じます。具体的には、相談スペースの隔離、相談窓口が守秘義務を遵守して対応することなどについて周知しておくと良いでしょう。また、従業員がハラスメントの相談をしたことを理由に不当な扱いをされない旨を、就業規則などにおいて規定し、周知・啓発することも大切です。
従業員が心身ともに健康に働くために、ハラスメント対策は必須
ハラスメントは、従業員の仕事に対するモチベーションを奪うだけでなく、企業価値に大きなダメージを与える可能性がある深刻な問題です。ハラスメント対策は企業の義務でもあり、健康経営の一環として真摯に対応する必要があります。企業の担当者は、まずはハラスメントの種類や講ずべき対策を把握した上で、ハラスメントが発生しない環境づくりを進めましょう。
「マイナビ健康経営」は、人と組織の「ウェルネス(健康)」をさまざまなサービスでサポートしています。ハラスメント対策に取り組む際には、ぜひお気軽にご相談ください。
【免責及びご注意】 記事の内容は公開日当時のものです。当社では細心の注意を払っておりますが、実践の際には所轄の税務署など各専門機関でご確認の上、ご検討・ご対応をお願い致します。万一、内容について誤りおよび内容に基づいて被った損害について、当社では一切責任を負いませんのでご了承ください。 |
<監修者> 丁海煌(ちょん・へふぁん)/1988年4月3日生まれ。弁護士/弁護士法人オルビス所属/弁護士登録後、一般民事事件、家事事件、刑事事件等の多種多様な訴訟業務に携わる。2020年からは韓国ソウルの大手ローファームにて、日韓企業間のM&Aや契約書諮問、人事労務に携わり、2022年2月に日本帰国。現在、韓国での知見を活かし、日本企業の韓国進出や韓国企業の日本進出のリーガルサポートや、企業の人事労務問題などを手掛けている。 |
&res=1280x720&is_new_uid=true&_tcuid=202504041509499551&_tcsid=202504041509496816)