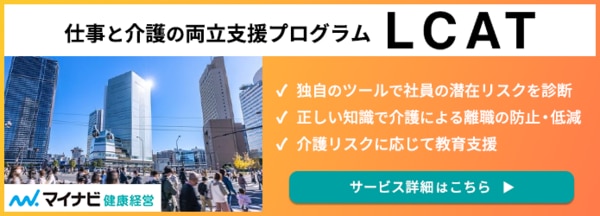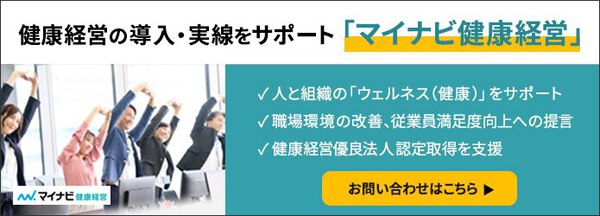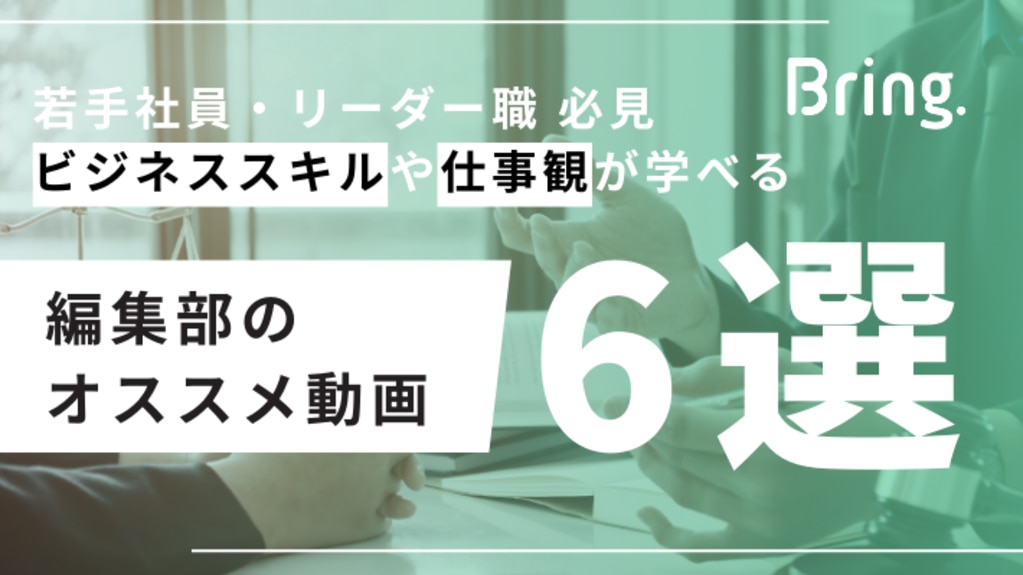介護離職のリスクとは?防止するための制度や企業の対策を解説
少子高齢化が進む中、家族の介護のために仕事を辞める「介護離職」は、企業や従業員にとっての大きな問題です。介護離職は、収入の減少やキャリアの断絶、介護者と社会との隔絶など、介護者の生活に大きな影響を与える可能性があります。また、優秀な人材が介護離職を選ぶことは、企業や社会にとっても大きな損失となるでしょう。企業は大切な人材を守るために、従業員が介護に直面する前に、適切な制度や環境を整えることが求められます。
本記事では、介護離職が個人に与えるリスクとともに、介護離職を防止するための国の制度、企業が取り組むべき対策について詳しく解説します。
目次[非表示]
- 1.介護離職とは、家族の介護のために仕事を辞めること
- 2.介護離職が生じる理由
- 3.介護離職を防止するための制度
- 3.1.介護休業
- 3.2.介護休暇
- 3.3.所定外労働の制限(残業免除)
- 3.4.育児・介護休業法の改正
- 4.介護離職を防止するための助成金
- 5.介護離職を防止するための企業の対策
- 5.1.実態把握
- 5.2.制度設計・見直し
- 5.3.介護に直面する前の従業員への支援
- 5.4.介護に直面した従業員への支援
- 5.5.働き方改革
- 6.介護離職を防止する仕組みと風土づくりで、大切な人的資本を守ろう
介護離職とは、家族の介護のために仕事を辞めること
介護離職とは、家族の介護と仕事との両立が困難になり、介護に専念するためにやむなく仕事を辞めることです。介護の内容は、要介護者の状態や介護認定のレベルに応じて異なりますが、どのケースでも介護者にかかる負担は非常に大きいものです。こうした中で、「仕事の代わりはいても、家族を介護できるのは自分しかいない」と精神的に追い込まれ、離職を選択せざるをえなくなるケースが少なくありません。
そうした場合に、介護のための休暇やテレワークなどの制度が確立されていたり、従業員の疲弊に気づいて声かけをする環境が整っていたりすれば離職を防げる可能性があるでしょう。しかし、多くの企業ではこうしたサポートが十分に追いついていないのが現状です。
実際、2022年10月に実施された総務省統計局の調査では、介護をしている約629万人のうち約365万人が仕事と介護を両立させていますが、介護や看護を理由に過去1年間に離職した人は、10万6,000人にものぼることがわかりました。
団塊の世代が後期高齢者となる2025年には、介護を必要とする人がさらに増加することは確実です。そのため、早期に適切な対策を講じることで、従業員のキャリアや人生を守り、優秀な人材の流出を最小限に抑えることが大切です。
【参照】総務省「令和4年就業構造基本調査結果の要約」|総務省
https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2022/pdf/kall.pdf
介護離職が生じる理由
なぜ、介護離職は起きるのでしょうか。厚生労働省「令和3年度 仕事と介護の両立等に関する実態把握のための調査研究事業 労働者調査」では、介護離職の理由を尋ねる質問に対して、「勤務先の両立支援制度の問題や介護休業などを取得しづらい雰囲気」が43.4%で最も多くを占めました。
次いで、「介護保険サービスや障害福祉サービスなどが利用できなかった、利用方法がわからなかったなど」が30.2%、「介護が必要な家族、その他家族・親族の希望等があった」が20.6%となっています。
また、職場にどのような取り組みがあれば仕事を続けられたかを聞く質問に対しては、「仕事と介護の両立支援制度に関する個別の周知」との回答が55.1%で半数以上を占めました。「仕事と介護の両立支援制度に関する研修」も31.7%にのぼります。
この結果からも、仕事と介護を両立する従業員を企業がサポートするためには、職場の支援制度の整備はもちろん、それを活用できる環境を整えることが求められます。
【参照】三菱UFJリサーチ&コンサルティング「仕事と介護の両立等に関する実態把握のための調査研究事業 労働者調査 結果概要」|厚生労働省(2022年3月)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000988664.pdf
介護離職のリスク
前項で紹介した厚生労働省の調査においては、介護離職をした後の変化として、「精神面」「肉体面」「経済面」とも「非常に負担が増した」「負担が増した」と答えた人が7割近くに上っています。ここからは、介護離職をした従業員に起こりえるリスクについて詳しく見ていきます。
心身の負担
介護離職のリスクのひとつが、心身の負担の増加です。仕事を辞めて介護に専念するようになると、必然的に介護者と要介護者が一対一で向き合う時間が増えます。介護の状況によりますが、食事や入浴、排せつなどのサポートが必要になる場面が多くなり、介護者の負担が大きくなりかねません。場合によっては、長時間気を張り続けることになり、心身の負担を感じやすくなるケースもあります。
経済的な困窮
経済的な困窮も介護離職のリスクです。仕事を辞めて収入が途絶えると、自身の貯蓄や親の年金を頼りに生活するケースも少なくありません。また、介護離職によって厚生年金の加入期間が短くなると、将来的に自分の年金が減額される可能性もあります。さらに、親を看取った後は、親の年金も途絶えるため、再就職しない場合は自身の老後資金が不足するリスクがあります。
社会からの孤立
社会からの孤立も介護離職のリスクといえます。家族の介護度が重い場合、介護者は24時間365日介護に従事する必要があり、社会と関わりを持つ時間がなくなることも少なくありません。親以外の人とのコミュニケーションが減ると、孤立感が助長されることもあるでしょう。
【参照】三菱UFJリサーチ&コンサルティング「仕事と介護の両立等に関する実態把握のための調査研究事業 労働者調査 結果概要」|厚生労働省(2022年3月)https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000988664.pdf
介護離職を防止するための制度
介護離職を防ぐため、国はさまざまな制度の拡充を図っています。しかし、前述した調査にあったように、介護に関連するサービスが利用できなかったり、利用方法がわからなかったりするために、介護離職を選ぶ人は少なくありません。離職した人の大半が「仕事と介護の両立支援制度に関する個別の周知」があれば仕事を継続できたと答えています。このことから、制度の周知が介護離職を防ぐカギになるといえるでしょう。
企業担当者は、まずは制度をよく理解し、サポートを必要とする従業員に、適切な制度をすすめられる知見を身につけることが大切です。ここでは、介護離職を防止するための制度を紹介します。
介護休業
介護休業は、家族が負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(要介護状態)の場合に、家族1人につき最大3回、通算93日まで休みを取得できる制度です。雇用保険に加入していて一定の要件を満たす従業員であれば、介護休業給付金として介護休業期間中に休業開始時賃金日額の67%が支給されるため、休業中の収入減を補うために活用できます。
介護休暇
介護休暇は、要介護状態の場合に、家族の通院などで単発の休みが必要なときに使える制度です。要介護状態にある対象家族1人につき年に5日まで、2人以上になると年に10日まで、1日または1時間単位で取得できます。介護休暇が必要なシーンは突発的に起こることが多いため、口頭での申請も可能です。
所定外労働の制限(残業免除)
要介護状態の場合において介護で残業が難しいときには、残業の免除が認められる「所定外労働(残業)の制限」を利用できます。免除ではなく、1ヵ月について24時間、1年間について150時間を超える時間外労働をさせない「時間外労働の制限」もあります。いずれの場合も、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、企業が請求を拒むことはできません。
短時間勤務などの措置
企業は以下のいずれかの制度を定め、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が希望すれば、所定労働時間の短縮などの措置を講じなければなりません。これらの制度は、要介護状態にある対象家族1人につき、利用開始の日から連続する3年以上の期間において2回以上利用できるようにする必要があります。
<企業が整備すべき制度>
- 短時間勤務制度
- フレックスタイム制度
- 始業・終業時刻の繰り上げ、繰り下げ(時差出勤の制度)
- 従業員が負担する介護サービスの費用の助成、その他これに準ずる制度
育児・介護休業法の改正
2025年4月から、育児・介護休業法の改正に伴って以下3つが事業者の義務となります。担当者はこれらの義務化に向けて確実に準備することが必要です。
-
介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備
介護と仕事の両立について相談できる窓口の設置や、従業員に向けた研修を実施する。 -
介護に直面した旨の申し出をした従業員に対する個別の周知・意向確認の措置
従業員からの申し出があった場合に、介護休業などの制度を周知して利用の意向を確認する。 -
介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
従業員からの申し出を待たず、介護が現実味を帯びてくる40歳を目安に情報提供を開始する。
また、上記のほかにも、要介護状態の家族を介護する従業員がテレワークを選択できるようにすることが努力義務化されたほか、勤続6ヵ月未満の従業員も介護休暇を申請できるようになります。
【参照】厚生労働省「介護休業制度」|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/index.html
介護離職を防止するための助成金
介護と仕事の両立支援を進める企業に対して、国は支援制度を設けています。「両立支援等助成金」は、従業員が介護休業を取得または職場復帰しやすいよう、取り組んでいる事業者をサポートする助成金です。
作成した介護支援プランにもとづいて介護休業や介護休暇、短時間勤務制度を導入したり、休業からの復帰を支援したりする場合など、一定の要件を満たす企業に支給されます。企業は、こうした助成金の活用も検討しながら、介護をする従業員が安心して働ける環境整備を進めましょう。
【参照】厚生労働省「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」|厚生労働省https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeIRAA0/view
介護離職を防止するための企業の対策
厚生労働省が策定した「企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル」では、介護離職を予防するために企業が取り組むべき主な事項として以下5つが挙げられています。ここからは、介護離職を防ぐための企業の対策を紹介します。
実態把握
介護離職を防ぐための出発点となるのが、従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握です。まずは、介護と仕事を両立する従業員の数や、利用できる制度についての理解度、直面している問題などを把握します。アンケートなどを通じて、生の声を聞くことが大切です。
制度設計・見直し
把握した実態を踏まえて、必要があれば制度を再設計します。見直すポイントは、両立支援制度が法的な基準を満たしているか、制度の周知は十分かといった点です。また、利用条件や手続きはシンプルか、従業員のニーズに応えた制度になっているかという点も確認しておきましょう。さらに、従業員が気軽に相談できる窓口の設置や、社内研修を通じた制度の啓発を行うことで、「制度があるだけ」ではなく「実際に活用される制度」への改善が期待できます。
介護に直面する前の従業員への支援
介護は誰もが直面する可能性がある問題です。一人ひとりが介護の問題を自分に置き換えて考えることで、介護に直面した仲間を思いやる従業員が増えるでしょう。また、早い段階から制度について知らせることで、制度を利用しやすい環境が醸成されます。現時点では介護と無縁の従業員も、事前に企業から情報提供を受けて介護に関する知見を深めることで、いざというときに離職を選択せずに済むでしょう。
情報提供の方法には、社内報を通じた広報や研修のほか、従業員が自身のペースで仕事と介護の両立に必要な知識を学べるeラーニング型の両立支援システムの利用もおすすめです。「LCAT(エルキャット)」は、設問に回答した分析結果を通じて、自分のリスクを客観的に把握できます。また、診断結果に応じてeラーニングコンテンツが動画形式で提案されるため、必要な知識を効率良く習得できます。
介護に直面した従業員への支援
すでに介護をしている従業員に対しては、相談しやすい体制を整備すると同時に、公的な介護支援サービスや自社の両立支援制度の存在を知らせて利用を推奨します。また、介護者は「第三者の前で親を悪く言うのは避けたい」「排泄や入浴の介助については、悩んでいても仕事仲間には言いづらい」といった意識が働き、一人で悩みを抱え込む傾向も少なくありません。
そこで企業は、従業員が社外の専門家へ相談できる外部サービスを活用することも検討しましょう。例えば、介護と仕事の両立支援サービスである「仕事と介護の両立支援パック」の導入で、両立相談のプロや専門研修を受けた相談員による相談窓口の利用が可能です。また、従業員が介護の事前知識を学べるセミナーや、従業員の介護に関するステータスを確認できる簡易チェックも提供しています。こうした外部サービスを利用することで、両立支援にリソースを避けない企業でも法定義務を包括的に満たすことができます。
働き方改革
介護によって働く時間や日数に制限があってもやりがいをもって仕事ができるよう、職場の考え方や環境を改善します。残業時間の削減や年次有給休暇の取得促進、介護休業中の従業員に対する業務の情報共有の徹底、「お互い様」の気持ちで支え合える風土を作りましょう。
【参照】厚生労働省「企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル」|厚生労働省(2016年3月)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000119918.pdf
介護離職を防止する仕組みと風土づくりで、大切な人的資本を守ろう
介護離職は、企業を支える優秀な人材のキャリアに影響を与え、貴重な人材を流出させる可能性があります。介護に直面した従業員が「制度を利用すれば働き続けられる」と感じられる仕組みや風土を整えることが、かけがえのない人的資本を守り、企業が成長していくために重要です。
マイナビ健康経営が提供する「My Wells」では、「あらゆる働く組織の課題解決」に取り組んできた実践的ノウハウと情報を活かし、個人と企業のWellをサポートしています。自社と従業員の未来を守る介護と仕事の両立に取り組む際には、ぜひお気軽にご相談ください。
|
【免責及びご注意】 記事の内容は公開日当時のものです。当社では細心の注意を払っておりますが、実践の際には所轄の税務署など各専門機関でご確認の上、ご検討・ご対応をお願い致します。万一、内容について誤りおよび内容に基づいて被った損害について、当社では一切責任を負いませんのでご了承ください。
|
<監修者> |
&res=1280x720&is_new_uid=true&_tcuid=202504010357035964&_tcsid=202504010357037744)