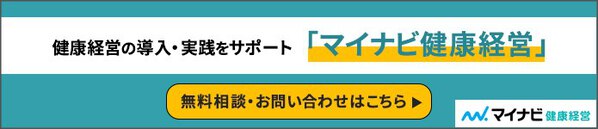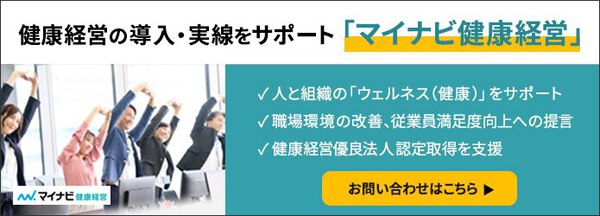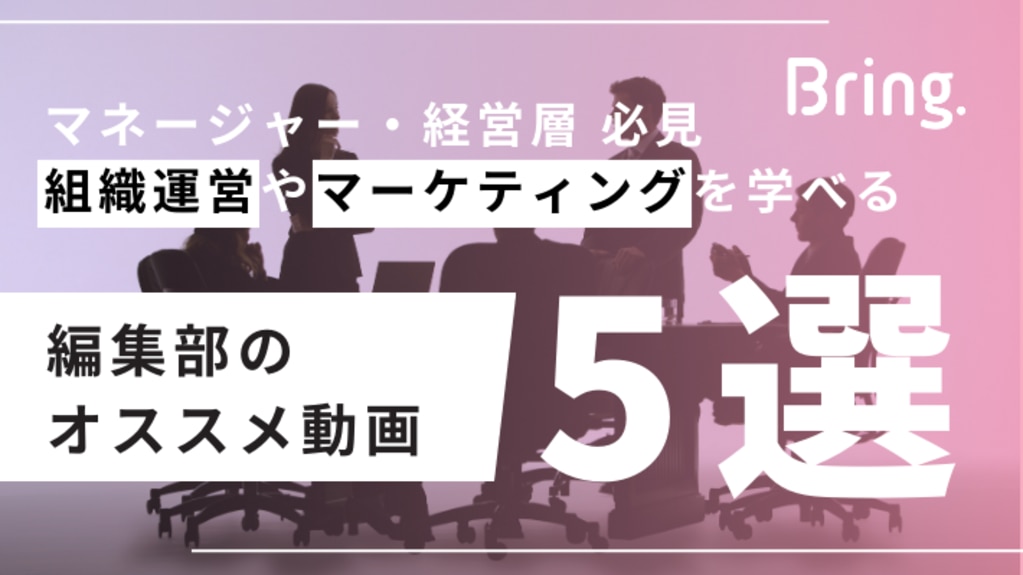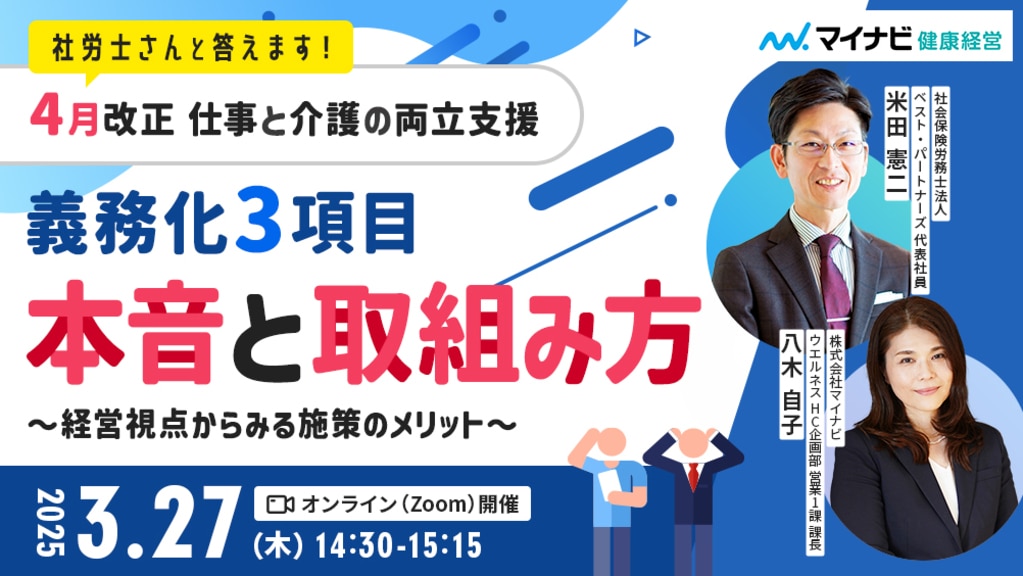健康経営の進め方とは?推進計画の作り方や効果的な施策を解説
生産年齢人口の減少や従業員の高齢化などを背景として、日本企業は長期的な人手不足のリスクにさらされています。これに伴い、従業員の健康に目を向ける経営者が増加し、「健康経営」に取り組む企業が増加しました。
今回は、これから健康経営を実践しようと考えている企業の担当者の方や、スタートした健康経営を継続するための施策を知りたい経営者の方などに向けて、健康経営の効果や健康経営の進め方(推進計画)、具体的な施策について詳しくご紹介します。
【参照】経済産業省ヘルスケア産業課「健康経営の推進について」|経済産業省(2022年6月)
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/kenkokeiei_gaiyo.pdf
目次[非表示]
- 1.健康経営の目的とは?
- 2.企業における健康経営の効果
- 2.1.従業員の長期休業や欠員による人手不足の防止
- 2.2.業務効率化による生産性の向上
- 2.3.企業の医療費負担の削減
- 2.4.企業のイメージアップ
- 3.健康経営の進め方
- 3.1.1. 申請から認定までのスケジュールの全体像をつかむ
- 3.2.2. 健康経営に取り組む目的などをまとめる
- 3.3.3. 健康宣言を行い、社内外に健康経営への取り組みを表明する
- 3.4.4. 組織体制を整える
- 3.5.5. 健康課題を把握し、課題を明確化する
- 3.6.6. 計画策定・健康づくりの推進を行う
- 3.7.7. 取り組みの評価・改善を行う
- 4.健康経営を進める上で効果的な施策
- 4.1.定期検診の受診率を100%にする
- 4.2.定期検診の再診を促す
- 4.3.ストレスチェックを実施する
- 4.4.健康増進や過重労働防止への数値目標を設定する
- 4.5.セミナーなどを実施し、従業員の健康意識を高める
- 4.6.労働時間や休暇日数を見直す
- 4.7.社内コミュニケーションを促進する
- 4.8.メンタル不調者に対応できる体制を整える
- 4.9.治療と仕事の両立を支援する
- 4.10.保健指導を実施する
- 4.11.食生活改善の指導を行う
- 4.12.従業員に運動機会を提供する
- 4.13.感染症を予防する
- 5.人手不足への不安に備えて、人的資源を守る健康経営を実践しよう
健康経営の目的とは?
健康経営は、企業の経営において欠かせない「人」に注目し、「従業員の健康づくり」はもちろん、「人を資本として新しい企業価値を創造すること」や、「新たな付加価値を創造するために人資本への再投資を行う」という考え方です。従業員の心身の健康を経営的視点から考え、戦略的に実践することを目指すのが健康経営です。
これまでコストとされてきた従業員の心身の健康管理へ積極的に投資し、長くすこやかに働き続けてもらうという、今の時代に沿った新しい考え方ともいえます。
健康経営は、日本再興戦略、未来投資戦略にも位置付けられています。今や、働き手の健康寿命の延伸は、日本全体で取り組むべき喫緊の課題であるといえるでしょう。
企業における健康経営の効果
企業が健康経営に取り組むことで、どのような効果が得られるのでしょうか。具体的には下記のような効果が考えられます。
従業員の長期休業や欠員による人手不足の防止
健康経営の効果として真っ先に実感できるのは、従業員の健康が増進することによって、病気などによる長期休業や退職を未然に防げることです。従業員の高齢化が進めば、当然ながら従業員の病気のリスクも増加します。思わぬ病気が発覚し、通院のためにやむなく仕事から離れる従業員が増えることもあるかもしれません。そうした欠員が重なれば、企業の生産活動は停滞し、利益の減少につながる可能性も高まります。
そこで、健康経営に取り組めば、従業員一人ひとりの健康意識を高め、長く元気に働ける体づくりをサポートできます。健康経営を進めていけば、病気のリスクを早期に発見できるなど、短期間の治療での早期職場復帰も望めるでしょう。
業務効率化による生産性の向上
心身になんらかの不調を抱えている従業員は、意欲はあってもパフォーマンスがついてきません。結果として、通常なら1時間で終わる業務に何時間も費やしたり、成果物にミスが散見されたりと、業務の質が著しく低下することもあるでしょう。
一方、心身ともに健康な従業員は、肉体的にも精神的にも充実していて、高い集中力で仕事に臨めます。すると、スピーディーかつ正確な作業でミスを減らし、生産性を高めることが期待できます。
企業の医療費負担の削減
日本の医療費は「国民皆保険」で、国民全員が公的医療保険に加入することにより、病気や事故の際の高額な医療費負担を、実際の1~3割程度まで軽減することができます。
いつでも、誰でも、どこでも自由に医療機関を受診できる「フリーアクセス」や、医療サービスの「現物給付」と併せて、非常に優れた制度といえるのではないでしょうか。
しかし、だからといって多くの人が頻繁に医療機関を受診して治療を受ければ、公的医療保険の担い手である政府、自治体、企業の支出の増加が懸念されます。国の医療費が上がり続ければ、企業の経営に与える影響も大きくなるでしょう。
【参照】厚生労働省「医療保険制度の長期安定を目指して」|厚生労働省(2023年1月)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/index.html
企業のイメージアップ
経済産業省は、健康経営に積極的に取り組む上場企業を「健康経営銘柄」、上場企業以外にも優良な健康経営を実践している法人を「健康経営優良法人」として認定・公表しています。
つまり、健康経営を実践すると、「従業員の健康を大切にする会社」として広く知ってもらうことができるのです。これにより、企業の体外的なイメージがアップし、経営への良い波及効果が期待できます。
健康経営の進め方
ここからは、健康経営に取り組む際の基本的な流れについてご紹介します。健康経営の認定法人を目指す際は、まず全体的な流れを把握しておきましょう。
1. 申請から認定までのスケジュールの全体像をつかむ
上場企業の「健康経営銘柄」、大規模法人および中小規模法人の「健康経営優良法人」の認定を受けるには、5~6月にかけて行われる健康経営度調査・認定要件の検討結果を受け、9~10月にかけて申請をします。その後、審査期間を経て、年明け2~3月に認定法人の発表があります。
スケジュール全体の全体像をつかんでおき、申請受付に間に合うように、取り組みを推進しましょう。
2022年の申請から認定までのスケジュールは、健康経営優良法人認定事務局(日本経済新聞社)の「Action!健康経営」で確認できます。
2. 健康経営に取り組む目的などをまとめる
健康経営に取り組むことによって何を目指すのか、目的を明確にしておきましょう。取り組みの背景や目指すゴールが不明瞭だと、社内の体制づくりや一体感の醸成に支障をきたす可能性が高いからです。
まずは、下記のような内容を関係者間で言語化し、社内への周知に備えていってください。
<言語化しておきたい健康経営推進の背景や目的>
- なぜ健康経営に取り組もうと考えたのか
- 健康経営に取り組むことで、どんなことを実現したいのか
- 取り組みを主体となって推進する部署はどこか(プロジェクトチームを発足させるか)
- プロジェクトチームを作る場合、どんなメンバーが必要か
- 長期的な活動計画について
健康経営推進の言語化については、この時点で細かく設定しようとしすぎると、肝心のスタートが遅れてしまいます。長期的な計画に重点を置き、言語化は大枠を提示する程度にとどめておいてください。
3. 健康宣言を行い、社内外に健康経営への取り組みを表明する
続いて、健康経営に取り組むことを、社内外に向けて宣言します。前述した健康経営優良法人に認定されるための申請では、中小規模法人部門においても大規模法人部門においても、社内外に向けた健康宣言が認定の必須条件です。
加入している健康保険組合や、全国健康保険協会が「健康宣言事業」を実施している場合は活用するといいでしょう。健康宣言事業とは、企業が取り組む健康経営の内容を明文化し、発信するサポートをするものです。
【参考】全国健康保険協会「健康宣言」|全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/pickup/healthinesscorp/
4. 組織体制を整える
健康宣言を行った後は、健康経営を推進する社内体制を整備します。始めに、取り組みを主導し全体の活動の指揮をとる部署を決めましょう。プロジェクトチームを発足する場合は、社内のメンバーだけでなく産業医や保健師など、外部人材の登用も含めてメンバーを検討することも視野に入れてみてください。
取り組みを主として進めるメンバーに「健康経営アドバイザー」の資格を取得させたり、「健康経営エキスパートアドバイザー」の資格を持つ人材を招聘したりすると、取り組みの質が向上します。
5. 健康課題を把握し、課題を明確化する
組織体制を整えたら、自社内の健康課題を分析し、明確化します。代表的な企業の健康課題には、下記のようなものがあります。
<企業の健康課題の例>
- 健康診断の受診率が低い
- 健康診断でメタボリックシンドロームと診断された従業員が多い
- ストレスを強く感じている従業員が目立つ部署がある
- 特定のチームの残業時間が多すぎる
- 休職者が増えている
- 離職者数が増加している
- 有給消化率が低い
- 休日出勤の割合が高い
なお、洗い出した健康課題に対して、一気に改善の取り組みを進めるのは現実的ではありません。優先順位をつけて取り組む順番を決定しましょう。
最初から難しい課題に挑戦すると成果がついてこず、社内の士気が下がる原因にもなるため、確実に解決できそうな課題の優先順位を上げることをおすすめします。優先順位をつける際には、下記の視点で課題を見直します。
<課題の見直しに必要な視点>
- 実行のための体制は整っているか(すぐに整えることができるか)
- 対象となる人は十分にいるか
- 効果が期待できそうか
- 数年後までの見通しが立つか
6. 計画策定・健康づくりの推進を行う
明らかになった健康課題のうち、優先順位の高いものから順に具体的な取り組みを計画します。
例えば、健康診断でメタボリックシンドロームと診断された従業員に対して、適性体重を維持するための栄養バランスの良い食事をアドバイスしたり、残業時間が増える原因を見つけてシステムを導入し、効率化を図ったりといったことが考えられます。
7. 取り組みの評価・改善を行う
実施した取り組みは、必ず振り返りを実施し、課題に対して実施した施策が適切だったか、成果がどの程度まで現れ始めているかといった点を、定性的な視点から評価します。
健康経営の取り組みの中には比較的すみやかに効果が出るものもありますが、ほとんどが長期的な取り組みになりますので、定期的なチェックを怠らないようにしてください。取り組みの成果を高めるには、できるだけ短いスパンで見直しを図り、実効性を高めていくことが大切です。
健康経営を進める上で効果的な施策
ここでは健康経営を進めるために、効果的な施策の例を紹介します。健康経営を推進するための施策の具現化にお役立てください。
定期検診の受診率を100%にする
労働安全衛生法第66条にもとづき、企業の経営者は自社で勤務する労働者に対して健康診断を実施する義務があります。また、労働者にも、企業が実施する健康診断の受診義務があります。
ところが、実際には実施率・受診率ともに100%には達していません。特に、規模の小さい企業ほど、定期健康診断が未実施の傾向にあります。健康診断の受診は、健康経営において最も基本的な取り組みとされ、2022年度には健康経営銘柄および大規模法人部門の健康経営優良法人、中小規模法人部門の健康経営優良法人、それぞれの認定要件に「健康診断受診率100%」が設定されました。
健康経営優良法人を目指すなら、まずは健康診断の確実な実施と従業員への受診勧奨に努めましょう。
「仕事が多忙だから」「時間がもったいないから」といった理由で受診を避ける従業員には、健康診断を受けられるように業務の割り振りを考慮し、時間的な余裕を十分に与えることが大切です。
【参照】経済産業省「健康経営銘柄2022選定及び健康経営優良法人2022(大規模法人部門)認定要件」|経済産業省(2022年)
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/daikibo2022_ninteiyoken.pdf
定期検診の再診を促す
検診の目的は、結果をもとに疾病の早期発見・早期治療につなげることです。定期検診の受診率を100%に近づけるとともに、異常所見があり「要精密検査」「要治療」の結果が出た従業員には再診を促しましょう。
ストレスチェックを実施する
2015年12月の労働安全衛生法改正に伴い、従業員50人以上の企業に対して毎年1回、全従業員を対象としたストレスチェックの実施が義務付けられました。
ストレスチェックは、ストレスに関する質問に選択回答し、従業員のストレスの程度を把握するものです。従業員にみずからのストレスへの気づきを促し、メンタル不調による休職、離職を未然に防ぐことを目的としています。
【参照】中央労働災害防止協会「ストレスチェックサービス ストレスチェック制度とは?」|中央労働災害防止協会
https://www.jisha.or.jp/stress-check/about.html
【あわせて読みたい】
健康増進や過重労働防止への数値目標を設定する
自社の健康課題を改善するためには、具体的な数値目標の設定も大切です。数値目標の例としては、下記のようなものが挙げられます。
<数値目標例>
- ウォーキングイベントへの参加率を80%まで高める
- 健康診断の再検査受診率を100%にする
- 有給休暇を全員が5日以上取得できるようにする
セミナーなどを実施し、従業員の健康意識を高める
健康診断や再検査の受診率も、メンタルヘルスの問題も、当事者である従業員の意識が低いままでは改善が進みません。
外部講師を招いて、メンタルヘルスケア講習や食生活講座などを開催したり、eラーニングの受講環境を整えたりして、従業員に健康について学ぶ機会を提供しましょう。健康診断の意義や再診の重要性については、産業医に講演してもらうのも効果的です。
労働時間や休暇日数を見直す
長時間労働や休日返上での激務は、従業員が心身のバランスを崩す原因になります。ノー残業デーを設定する、残業時間が多い従業員には産業医との面談を推奨するなど、ワークライフバランスを維持できる働き方をサポートしましょう。
社内コミュニケーションを促進する
健康経営施策の継続的な実践には、健康づくりをみんなで楽しむ前向きな職場風土が欠かせません。健診の受診や再診を呼びかけるだけでなく、従業員を巻き込むイベントを計画して社内のコミュニケーションを活性化させましょう。
例えば、歩数や歩いた距離を競うイベントは比較的簡単に導入できる上、部署を越えた交流にもつながりやすいです。
メンタル不調者に対応できる体制を整える
メンタルの不調は、本人も気づかないうちに進行し、仕事の質や生産性に大きな影響を及ぼします。従業員が精神的に追い込まれないような環境づくりに努めるとともに、不調者が出た場合に備えて社内制度を整えましょう。
医療関係者との面談の場を設けたり、勤務時間や業務内容に配慮したりして、無理のない回復をサポートすることが大切です。
治療と仕事の両立を支援する
健康経営を実践したからといって、従業員の心身の不調をゼロにできるわけではありません。病気の治療が必要な従業員が出た場合に備えて、治療と仕事が両立できる体制も整えておきましょう。
具体的には、傷病休暇を通院に利用できるようにする、治療期間中の業務内容や勤務時間について柔軟に対応する、当人および当人の上司や同僚のための専用相談窓口を作るなどの対応が有効です。
保健指導を実施する
健康診断や人間ドックで「生活習慣病の発症リスクが高い」と診断された人に対して、保健師や管理栄養士が生活習慣の改善をサポートする特定保健指導を受ける機会を提供する方法もあります。その際、指導時間を出勤認定したり、勤務シフトを調整したりして、仕事を気にせず指導を受けられるようにしましょう。
食生活改善の指導を行う
メタボリックシンドロームの改善には、食生活の見直しが効果的です。特定保健指導の受診勧奨に加えて、下記のような取り組みを実施してみてはいかがでしょうか。
<食生活改善の取り組み例>
- 野菜摂取量が増えるよう、社員食堂のメニューを改善する
- 栄養バランスのとれた仕出し弁当を安価に導入する
従業員に運動機会を提供する
仕事が忙しく、運動が不足している従業員のため、社内で運動の機会を作る方法もあります。朝礼後にラジオ体操、お昼休みにストレッチというように、全員で運動する時間を作ると、運動の好き嫌いにかかわらず体を動かすことができます。
感染症を予防する
ノロウイルスやインフルエンザなど、強力な感染症が社内に蔓延すると、会社の営業がストップすることになりかねません。流行時期以外にも感染症を防ぐ意識を持ち、予防接種の推奨をはじめ、従業員の手のアルコール消毒や検温の習慣化といった対策を怠らないようにしましょう。
人手不足への不安に備えて、人的資源を守る健康経営を実践しよう
健康経営は、人材という資産を守り、育てる上で重要な要素です。しかし、健康経営に初めて取り組む企業は、推進計画を策定する方法や健康経営の具体的な進め方など、何から手をつけるべきかわからずに悩むことも多いでしょう。
健康経営の実践を検討している方は、ぜひ「マイナビ健康経営」にご相談ください。人材紹介で培った豊富なノウハウとネットワーク、企業の特性に合わせて提供できる多様なサービスで、貴社の健康経営の推進をサポートします。
<監修者> |
&res=1280x720&is_new_uid=true&_tcuid=202504051006274427&_tcsid=202504051006275479)